
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 自分のキャリアプランを考えている学生や若手社会人
- 採用活動や人材定着に悩んでいる企業の人事担当者
- 「学歴と働き方」の関係性について、客観的なデータで知りたい方
- 自分の勤続年数が平均と比べてどうなのか、気になっている方
「高学歴な人ほど、一つの会社に長く勤める」「最近の若者はすぐに会社を辞めるって言うけど、学歴で違いはあるの?」
そんな疑問を、あなたも一度は抱いたことがあるかもしれません。実は、その答えは厚生労働省が毎年発表している公的なデータの中に、ハッキリと示されています。学歴によって、会社に在籍する平均年数には、驚くほど明確な傾向が見られるのです。
この記事では、最新の「賃金構造基本統計調査」をもとに、学歴別の平均勤続年数をランキング形式で分かりやすく解説します。さらに、その数字の裏側にある、学歴ごとのキャリア観や働き方の違いについても深掘りしていきます。このデータは、あなたのキャリア戦略を考える上で、きっと重要なヒントになるはず。さあ、日本のリアルな働き方の実態を見ていきましょう。
まずは結論!学歴別・平均勤続年数ランキング
早速ですが、厚生労働省の「令和5年 賃金構造基本統計調査」から、男性労働者の学歴別・平均勤続年数を見てみましょう。
- 第1位:大学院卒 … 15.1年
- 第2位:大学卒 … 13.0年
- 第3位:高専・短大卒 … 12.5年
- 第4位:高校卒 … 11.9年
いかがでしょうか。やはり、一般的に言われている通り「学歴が高いほど、平均勤続年数が長い」という明確な傾向が見て取れます。特に大学院卒の平均勤続年数の長さは際立っていますね。では、なぜこのような差が生まれるのでしょうか。その背景を読み解いていきましょう。
なぜ?大学院卒・大学卒の勤続年数が長い理由
大学院卒や大学卒の勤続年数が長い背景には、いくつかの理由が考えられます。
一つ目は、「専門性」です。大学院や大学で身につけた専門知識を活かせる研究職、開発職、あるいは医師や弁護士といった専門職に就くケースが多いです。これらの職種は、スキルや知識が蓄積されるほど社内での価値が高まり、簡単には替えが効かない存在になります。そのため、一つの組織で長くキャリアを築くインセンティブが働きやすいのです。
二つ目は、「企業規模と待遇」です。新卒採用市場において、今なお多くの大企業は採用の門戸を大卒以上に絞る傾向があります。大企業は福利厚生が手厚く、給与水準も比較的高いため、従業員の定着率が高くなるのは自然な流れと言えるでしょう。
高卒・専門卒の勤続年数が比較的短い背景とは?
一方で、高校卒や高専・短大卒の勤続年数が相対的に短いのは、決してネガティブな理由だけではありません。
彼らのキャリアには「柔軟性」があります。特定の学問分野に縛られず、製造業、建設業、サービス業など、幅広い職種に就くことができます。そのため、「この仕事は自分に合わない」と感じた時に、比較的早い段階でキャリアチェンジしやすい、という側面があります。
また、現場での実践的なスキルが重視される職種では、より良い給与や働きやすい環境を求めて、同業他社へ転職すること自体がキャリアアップの王道であるケースも少なくありません。勤続年数の短さは、裏を返せば、自分に合った働き方を求めて、フットワーク軽く積極的にキャリアを形成している結果とも言えるのです。
このデータから私たちが本当に考えるべきこと
ここまで見てきたように、学歴と平均勤続年数には一定の相関関係があります。しかし、最も重要なのは、これが単なる「平均値」であり、あなたの人生を決めるものでは全くない、ということです。
このデータから私たちが学ぶべきなのは、優劣ではなく「キャリア戦略の違い」です。
もしあなたが「安定性」を重視するなら、大学院卒のキャリアパスのように、専門性を高めて一つの組織で長く貢献することを目指すのが有効な戦略かもしれません。
逆に「多様な経験」や「スピーディーなスキルアップ」を望むなら、高校卒のキャリアパスのように、勤続年数にこだわらず、自分を高く評価してくれる場所へと積極的に移っていくことも、また正しい戦略なのです。
大切なのは、こうした客観的なデータで自分の属性の傾向を知った上で、「では、自分はどんな働き方をしたいのか?」という問いを、自分自身に投げかけること。その問いの答えこそが、あなたのキャリアの羅針盤になるはずです。


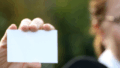
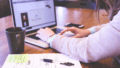
コメント