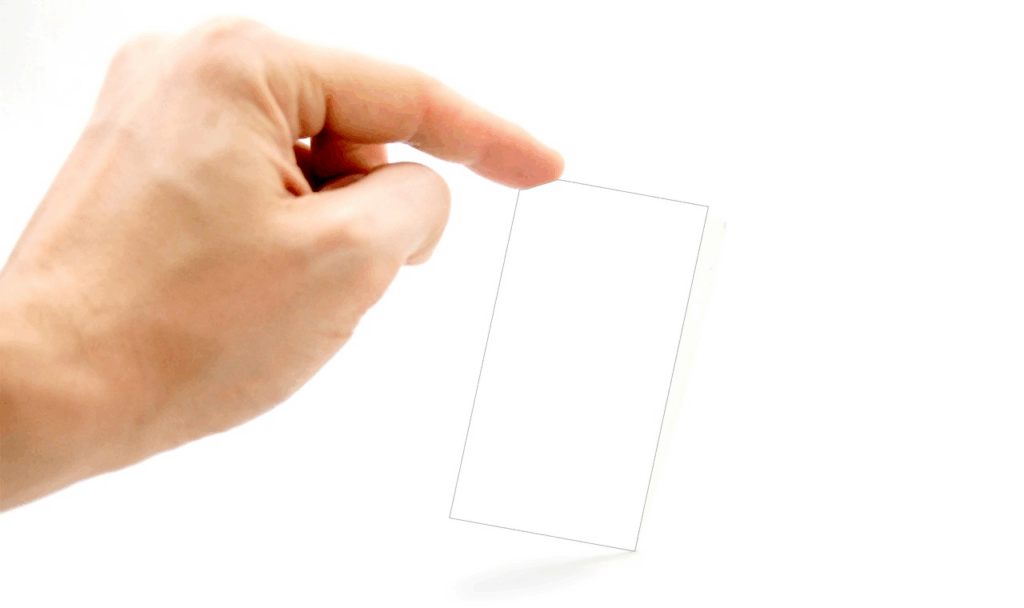
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- ある日突然、上司から「会社のIT化、よろしく!」と、壮大なプロジェクトを丸投げされてしまった、非IT部門の方
- 「プロジェクト計画書を作って、経営会議で説明して」と言われたものの、何を書けばいいのか、見当もつかずにフリーズしている方
- 中小企業で、総務や経理を担当しながら、会社のDXも進めなければならない、マルチタスクな立場の方
- これからITプロジェクトのリーダーや、プロジェクトマネージャーを目指したいと考えている、意欲あふれる若手社員の方
- 説得力のある計画書で、上司や経営層から、予算と承認をスムーズに獲得したい、すべてのビジネスパーソン
「君、パソコン詳しそうだからさ。うちの会社のIT化、ちょっと担当してくれないかな?」
ある日、上司から投げかけられた、その一言。 一見すると、期待の表れのようにも聞こえますが、その実態は、地図もコンパスも渡されずに、「宝島を探してこい」と言われるような、壮大な無茶振りです。
何から手をつけていいか分からず、ただ目の前が真っ暗になっている。そんなあなたのための「魔法の杖」、それが「プロジェクト計画書」です。
「計画書」と聞くと、何だかお役所仕事のようで、分厚くて、難解な書類を想像するかもしれません。しかし、その本質は、これから始まる、あなたのプロジェクトという名の「冒険の旅」を、成功に導くための、たった一枚の「航海図」なのです。
プロジェクトマネジメント協会(PMI)の調査によれば、プロジェクトが失敗する最大の原因は「目的の不明確さ」と「計画の不備」にあると言われています。つまり、この「航海図」を、冒険の最初に、いかに精度高く描けるかどうかが、あなたのプロジェクトの成否を、ほぼ決定づけてしまうのです。
この記事では、ITの専門知識がゼロの初心者でも、経営陣を「なるほど!」と唸らせ、周りの仲間を巻き込み、プロジェクトを成功へと導くための「最強のプロジェクト計画書」の作り方を、具体的なテンプレートに沿って、手取り足取り解説していきます。
STEP1: プロジェクトの”魂”を吹き込む。「目的」と「ゴール」の言語化
プロジェクト計画書において、最も重要で、そして、最初に書くべき項目。それが、「このプロジェクトは、一体、何のためにやるのか?」という、目的とゴールの設定です。
ここがフワッとしていると、プロジェクトは必ず、大海原で方向性を見失い、漂流します。多くの初心者が陥る罠は、「手段」と「目的」を混同してしまうことです。
- ダメな目的(手段):「勤怠管理システムを導入する」
- 最高の目的(ゴール):「手作業による勤怠データの集計と、給与計算ソフトへの入力にかかっている時間を、現状の月間80時間から30時間に削減する。これにより、経理担当者が、より付加価値の高い『予実管理分析』といった業務に集中できる体制を、6ヶ月以内に構築する」
どうでしょうか。後者の方が、圧倒的に具体的で、魅力的ですよね。この「最高のゴール」を設定するために役立つのが、「SMARTの法則」というフレームワークです。
- S (Specific): 具体的か?(勤怠管理業務の効率化)
- M (Measurable): 測定可能か?(月間50時間の工数を削減)
- A (Achievable): 達成可能か?(現実的な目標か?)
- R (Relevant): 関連性があるか?(会社の経営課題「生産性向上」と関連しているか?)
- T (Time-bound): 期限が明確か?(6ヶ月以内に)
このフレームワークに沿って考えるだけで、誰でも、具体的で、パワフルなゴールを設定することができます。これが、あなたのプロジェクトの「魂」となります。
STEP2: なぜ”今”やるのか?上司を説得する「背景」と「課題」のロジック
ゴールが決まったら、次はそのプロジェクトの「大義名分」、つまり、「なぜ、今、このプロジェクトをやる必要があるのか?」という正当性を、ロジカルに説明するパートです。これは、上司や経営層から、予算と承認を勝ち取るための、最も重要なプレゼンテーションになります。
ポイントは、現状の課題(As-Is)を、できるだけ「数値」で、具体的に示すことです。
「今の勤怠管理、大変なんです」という、感情的な訴えだけでは、人の心は動きません。
- 課題の数値化(コスト換算):
- 「現在、担当者2名による勤怠データの目視確認と、Excelへの手入力で、毎月平均80時間の工数がかかっています。これを人件費(時給2,500円と仮定)に換算すると、月々20万円、年間で240万円のコストが発生しています」
- 「さらに、手入力による転記ミスが、毎月平均で3件発生しており、その給与の再計算や修正手続きといった手戻り作業に、追加で月5時間(12,500円相当)の工数がかかっています」
- 放置した場合のリスク:
- 「このままでは、法改正(働き方改革関連法など)への対応が遅れるリスクがあります」
- 「月末の長時間残業が常態化しており、担当者の〇〇さんの心身の疲労はピークに達しています。このままでは、優秀な人材の離職に繋がりかねません」
このように、現状の課題を「お金」と「リスク」という、経営者が最も気にする言語に翻訳してあげることで、「それは、悠長なことは言っていられないな。すぐに対策を打つべきだ」という、強い当事者意識を引き出すことができるのです。
STEP3: 炎上を防ぐ最強の防波堤。「やること」と「やらないこと」の明確な線引き
おめでとうございます。あなたのプロジェクトの重要性が認められ、いよいよ具体的な計画に進むことになりました。 しかし、ここに、プロジェクトが失敗する最大の落とし穴、「スコープ・クリープ」が待ち構えています。
スコープ・クリープとは、プロジェクトが始まった後に、関係者から「あれもやってほしい」「ついでに、これもできないか?」と、次から次へと新しい要求が追加され、雪だるま式に作業範囲が膨れ上がっていく、恐ろしい現象です。
この怪物から、あなたのプロジェクトを守るための最強の防波堤が、計画書の「スコープ(範囲)」の項目で、「やること」と、それ以上に重要な「やらないこと」を、明確に線引きしておくことです。
【今回のプロジェクトのスコープ】
- スコープ内(やること):
- クラウド型勤怠管理システムの選定・導入
- 全従業員のICカードまたはスマホアプリによる打刻体制の構築
- 既存の給与計算ソフトとのデータ連携
- 全従業員への操作説明会の実施
- スコープ外(やらないこと):
- 交通費や経費の精算機能の導入(今回は見送り、フェーズ2で検討)
- プロジェクト別の工数管理機能の導入
- テレワーク時のPCログオン・ログオフ時刻との連携
「やらないこと」を決めるのは、時に勇気がいります。「それはできません」と断ることで、相手をがっかりさせてしまうかもしれないからです。しかし、ここで曖昧な返事をしてしまうと、後で「やってくれるって言ったじゃないか!」という、最悪の事態を招きます。
プロジェクトを炎上から守り、期限内にゴールへとたどり着くために、この「やらないことを決める勇気」こそが、リーダーに最も求められる資質なのです。
STEP4: 冒険の仲間と旅の工程表。「体制」と「スケジュール」の可vis化
さて、目的地の島も、そこへ至る航路も決まりました。次は、「誰と、どんな船で、いつまでに到着するのか」という、冒険の具体的な計画を立てる番です。
体制図:あなたの冒険のパーティを決めよう まず、このプロジェクトという冒険に参加する「仲間(パーティ)」を、明確にします。
- プロジェクトオーナー(王様): 会社の役員など、プロジェクトの最高責任者。最終的な意思決定を下し、予算を承認する人。
- プロジェクトリーダー(勇者): あなたです。プロジェクト全体の進捗を管理し、仲間をまとめるリーダー。
- プロジェクトメンバー(仲間たち): 実際に手を動かす、各担当者。今回は、経理部の〇〇さん、人事部の△△さん、といった具体的な名前を入れます。
- 関係者(村人たち): 直接のメンバーではないが、協力を仰ぐ必要がある他部署の人たち。
この体制図があることで、「誰に、何を確認すればいいのか」が一目瞭然になり、コミュニケーションが円滑になります。
スケジュール:冒険の工程表を作ろう 次に、ゴールまでの道のりを、具体的なタスクに分解し、時系列に並べた「工程表(ガントチャート)」を作成します。 難しく考える必要はありません。まずは、「WBS(作業分解構成図)」という手法で、やるべきことを大きな塊から小さな作業へと、箇条書きで分解してみましょう。
- 勤怠管理システムの導入
- 要件定義
- 1-1. 現場へのヒアリング
- 1-2. 要件定義書の作成
- 製品選定
- 2-1. 候補製品のリストアップ
- 2-2. 各社からの見積もり取得
- 2-3. 比較検討会の実施
- 導入・設定…
このようにタスクを洗い出したら、それをExcelやGoogleスプレッドシートの表にまとめ、各タスクの担当者と、開始日・終了日を記入していけば、立派なガントチャートの完成です。この工程表が、プロジェクトの進捗を管理する上での、強力な武器となります。
STEP5: で、結局いくらかかるの?経営者が納得する「予算」と「投資対効果」
いよいよ、計画書の最終関門です。それは、経営者が最も気にする、「で、このプロジェクトには、結局いくらかかって、会社にとって、どれだけの見返りがあるの?」という問いに、明確に答えることです。
予算:冒険に必要な、すべてのお金をリストアップする まずは、かかる費用を、正直に、そして網羅的にリストアップします。
- 初期費用:
- ソフトウェアライセンス料:〇〇円
- 導入支援コンサルティング費用:〇〇円
- 月額費用:
- システム利用料:〇〇円/月
- 人件費(忘れがち!):
- プロジェクトメンバーの工数:合計〇〇時間 × 想定時給〇〇円 = 〇〇円
「人件費」は、ついつい見落としがちですが、プロジェクトに費やす社員の時間も、会社にとっては紛れもないコストです。これをきちんと計上することで、あなたの計画書の信頼性は、格段に増します。
投資対効果(ROI):この冒険のリターンを証明する 次に、これだけの投資をすることで、会社にどれだけの「リターン」があるのかを、具体的に示します。
- 定量的な効果(金額で測れる効果):
- STEP2で算出した、残業代や手戻り工数の削減額:年間マイナス〇〇円
- 定性的な効果(金額では測りにくい効果):
- 経理担当者の業務満足度の向上、離職率の低下
- リアルタイムな勤怠状況の把握による、労務管理の健全化
- ペーパーレス化による、管理コストの削減と、環境への貢献
「このプロジェクトに〇〇円投資することで、年間で△△円のコスト削減が見込めます。さらに、従業員満足度の向上といった、プライスレスな価値も生まれます」
ここまで具体的に示せれば、経営者も、安心して「GOサイン」を出してくれるはずです。
まとめ:その一枚の紙が、あなたのプロジェクトを成功に導く
プロジェクト計画書の作り方、いかがでしたでしょうか。 それは、上司に提出するためだけの、退屈な「お役所仕事」では、決してありません。
- プロジェクトの「なぜ?」を定義し、関係者の心を一つにする「旗」であり、
- 進むべき道と、現在地を示してくれる「航海図」であり、
- 理不尽な要求や、スコープの肥大化から、あなたと仲間を守ってくれる「盾」なのです。
完璧な計画書を、最初から一人で作る必要はありません。 まずは、この記事をテンプレートにして、あなたなりの「たたき台」を作ってみてください。そして、それを持って、上司や、周りの仲間に相談してみる。
「こんなことを考えているんだけど、どう思う?」
その小さな一歩が、あなたのIT化プロジェクトという名の冒険を、成功へと導く、偉大な始まりになることを、私は信じています。

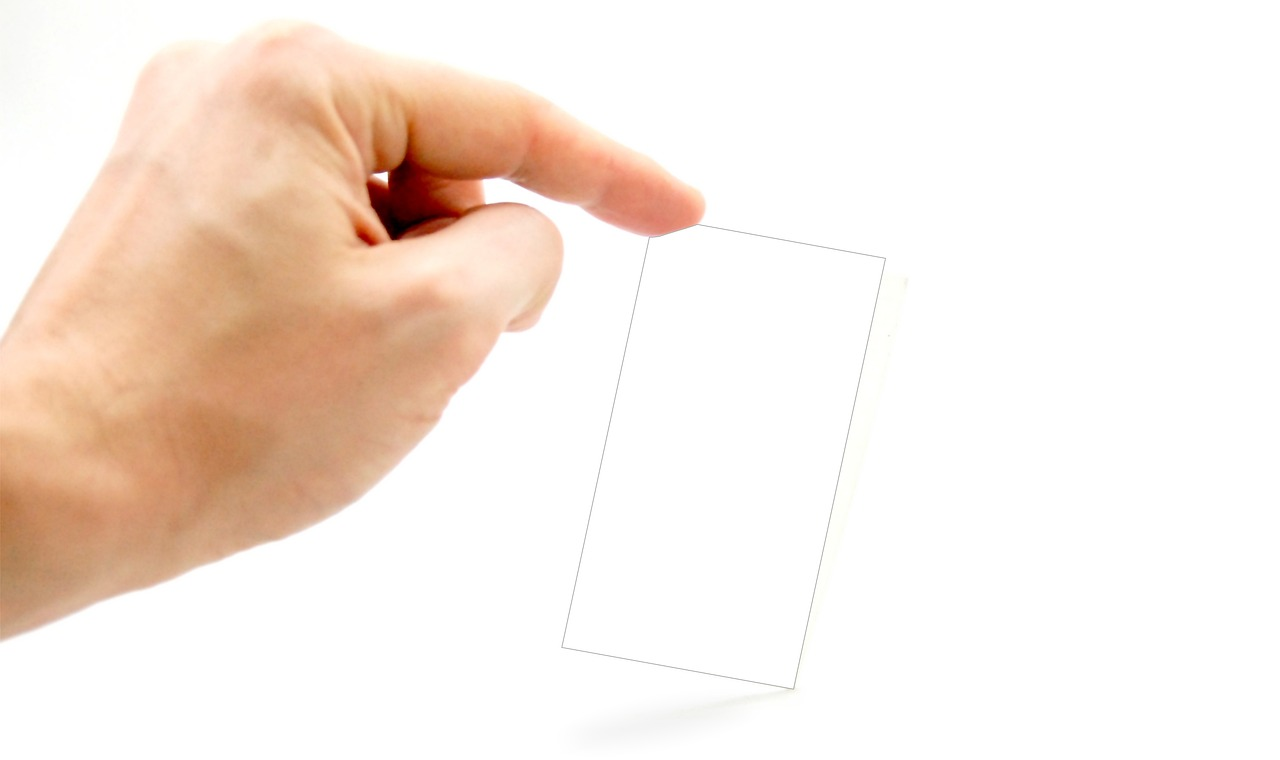
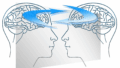

コメント