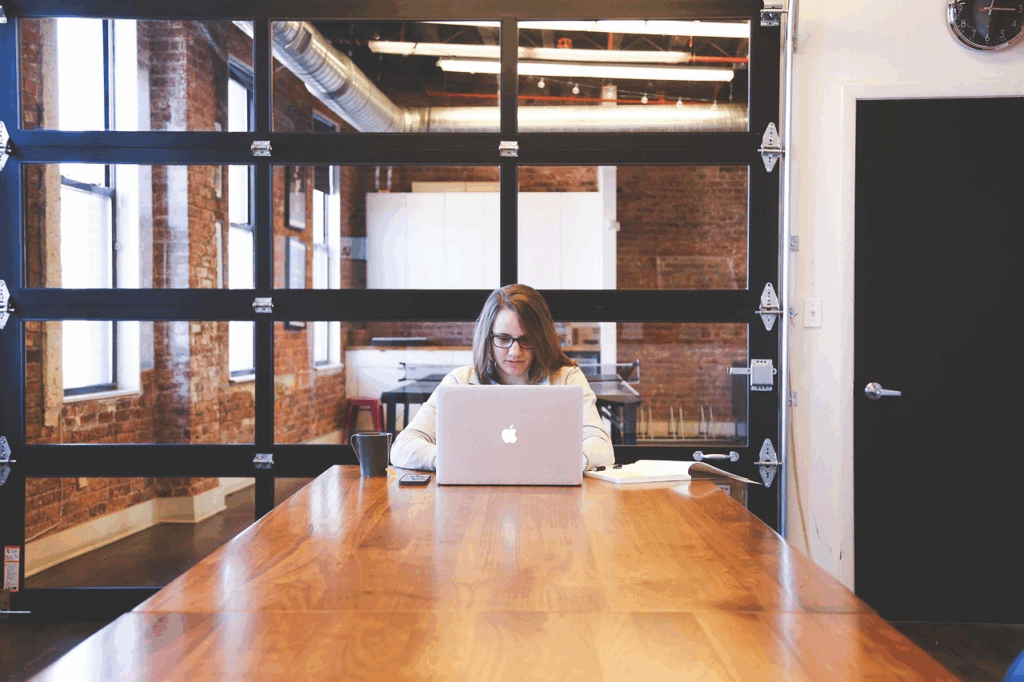
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 地方で事業を営んでいて、若手の採用に本気で悩んでいる経営者の方
- 「どうせ田舎だから」と、若手採用を諦めかけている人事担当者の方
- ハローワークや地元の求人誌に頼りきりの採用から脱却したい方
- 自社の本当の魅力を、今の若者にうまく伝えられずにもどかしい思いをしている方
- 給料や待遇面で、都市部の企業に太刀打ちできないと感じている方
「また若者の応募が一人もなかった…」「募集をかけても、集まるのはベテランばかり」。地方で会社を経営されている、あるいは人事の仕事をしているあなたなら、こんな悩みを一度ならず経験しているのではないでしょうか。人口は減り続け、若者はみんな都会に出て行ってしまう。このままでは、技術の承継も、会社の未来も危うい。そんな強い危機感を抱えているかもしれません。
「給料が安いから」「田舎で遊ぶところがないから」「仕事が地味だから」。若者が来てくれない理由を挙げれば、キリがないように思えます。そして、いつしか「地方だから仕方ない」という言葉が、諦めの呪文になっていませんか?
もし、そうだとしたら、今日はその呪いを解くための話をします。断言しますが、若手採用がうまくいかないのは、あなたの会社が「地方にあるから」ではありません。本当の魅力を、届けるべき相手に、正しい方法で「伝えられていない」だけなのです。この記事では、都市部の企業と同じ土俵で戦うことをやめ、地方企業ならではの武器を使って若者の心を掴み、採用を成功させた具体的な方法を、余すところなくお伝えします。これは机上の空論ではありません。明日から実践できる、泥臭くて、でも確かな手応えのある戦術です。
「どうせ田舎だから」は思考停止。若者が地方企業を選ばない本当の理由
まず、耳の痛い話から始めさせてください。多くの地方企業が陥っている最大の罠、それは「若者は地元志向が強いはずだ」「安定したウチの会社なら魅力的に映るはずだ」という思い込みです。残念ながら、その考えは、今の若者には通用しません。
内閣府の調査では、東京圏在住の若者(15〜29歳)の地方移住への関心は年々高まっており、約4割が関心を持っているというデータもあります。しかし、彼らが地方に求めるものは、単なる「安定」や「のんびりした暮らし」だけではありません。彼らは、その土地でしか得られない「経験」や「自己実現」の可能性を探しています。
それなのに、多くの地方企業の採用メッセージはどうでしょうか。「地域社会に貢献」「アットホームな職場です」「転勤なしで安定して働けます」。これらの言葉は、決して間違いではありません。しかし、刺激や成長を求める若者の心には、残念ながら響きにくいのが現実です。彼らから見れば、「退屈そう」「成長できなさそう」「世界が狭そう」というネガティブなイメージに繋がってしまいがちです。
問題は、あなたの会社に魅力がないことではありません。魅力の「切り口」と「伝え方」が、若者の価値観とズレてしまっているのです。「どうせ田舎だから」と嘆くのは、自分たちの可能性に蓋をしてしまう思考停止に他なりません。まず、この思い込みを捨てるところから、地方企業の採用革命は始まります。
給料で戦うな、物語で戦え。会社の「存在意義」を言語化する技術
都市部の企業と、給与や福利厚生で真っ向から勝負するのは、無謀です。では、どこで戦うのか?答えは「物語(ストーリー)」です。人は、お金のためだけに働くのではありません。特に今の若者は、「この仕事を通じて、社会にどんな影響を与えられるのか」「自分の仕事にどんな意味があるのか」という「存在意義(パーパス)」を強く求めます。あなたの会社には、まだ言語化されていない、素晴らしい物語が眠っているはずです。
あなたの仕事は、誰を、どう幸せにしていますか?
例えば、あなたが地方で金属部品を作る製造業を営んでいるとします。求人票に「金属部品の製造スタッフ募集」と書くだけでは、誰も興味を示しません。しかし、その部品が、世界中を飛ぶ航空機のエンジンに使われているとしたら?あるいは、最先端の医療機器に組み込まれ、多くの人の命を救っているとしたら?
物語はこう変わります。 「私たちの仕事は、単に金属を削ることではありません。世界中の人々の安全な空の旅を支え、医療の進化に貢献することです。小さな町工場から、世界を動かす。そんな誇りを、一緒に感じませんか?」
建設業ならどうでしょう。「道路工事の作業員募集」ではなく、 「この道は、10年後、子どもたちの通学路になる。この橋は、100年先まで、人々の暮らしを繋ぐ。私たちは、地図と記憶に残る仕事をしています。未来の故郷を、一緒に創る仲間を募集します」
このように、自社の事業が、顧客や地域社会、ひいては世界に対して、どのような価値を提供しているのかを、エモーショナルな「物語」として語るのです。これが、給料や待遇といった条件面を超えて、若者の心を直接揺さぶる、最強の武器になります。今すぐ、社員みんなで「私たちの仕事の本当の価値って何だろう?」という問いについて、話し合ってみてください。
採用の主戦場は地元じゃない。「関係人口」を狙い撃つ情報発信戦略
「物語」ができあがったら、それを発信するわけですが、ここでもう一つ、常識を捨てましょう。それは、「ターゲットは地元の若者だけ」という考え方です。もちろん、地元の若者に働いてもらうことは素晴らしいことですが、人口が減り続ける中で、パイの奪い合いをしていては限界があります。
今、注目すべきは「関係人口」というキーワードです。これは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、その地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指します。具体的には、「地域には住んでいないけれど、その地域に強い愛着や関心がある都市部の若者」です。彼らこそ、あなたの会社の未来を担う、新しい人材の宝庫です。
仕事と暮らしをセットで売るSNS戦略
では、どうやって関係人口にアプローチするのか?主戦場は、間違いなくSNSです。特に、ビジュアルで魅力を伝えやすいInstagramや、リアルタイム性の高いX(旧Twitter)は必須です。
ここで重要なのは、「仕事内容」だけを発信しないこと。彼らが知りたいのは、「その会社で働いたら、どんな毎日が待っているのか」というライフスタイル全体です。
- 社員の休日の過ごし方: 「今日は社員の〇〇さんが、近くの川でカヌーを楽しんでます!仕事も遊びも全力です!」
- 地域の魅力紹介: 「会社の近くにある、レトロな喫茶店。ここのナポリタンが絶品なんです。」
- 会社のリアルな日常: 「若手社員が、ベテランの職人から技術を教わっている一コマ。真剣な眼差しがカッコいい!」
このように、「仕事の魅力」と「その地域での暮らしの魅力」をセットで発信するのです。「この会社、なんだか面白そう」と同時に、「この町での生活、楽しそうだな」と思わせることができれば、移住への心理的なハードルは一気に下がります。飾らない、ありのままの日常を切り取って発信し続けることで、あなたの会社と地域は、都市部の若者にとって「特別な場所」になっていくのです。
「体験」こそ最強の口説き文句。オンライン時代の逆張りインターンシップ
SNSで興味を持ってくれた若者に対して、次に行うべきは、彼らを「現実世界」に呼び込むことです。どれだけオンラインで魅力を伝えても、百聞は一見に如かず。特に、移住を伴う就職では、実際にその土地の空気を感じてもらうことが、何よりも重要になります。
そこでおすすめしたいのが、交通費や宿泊費を会社が負担してでも実施する、「体験型インターンシップ」です。これは、単なる職場見学や仕事体験ではありません。あなたの会社と地域が持つ魅力を、五感で感じてもらうための「究極のおもてなし」です。
地域全体を巻き込んだ「忘れられない数日間」をプロデュースする
プログラムには、仕事体験だけでなく、その地域ならではのコンテンツを積極的に盛り込みましょう。
- 1日目: 工場見学と簡単な仕事体験。夜は、社員全員参加のBBQで本音の交流会。
- 2日目: 地元の農家さんを手伝って、採れたての野菜で昼食作り。午後は、伝統工芸の工房で職人さんの話を聞く。
- 3日目: 最終プレゼン。「自分がこの会社に入ったら、どんなことで貢献したいか」を発表してもらう。
ポイントは、学生を「お客様」として扱うのではなく、「未来の仲間」として迎え入れ、地域全体を巻き込んで、彼らの心を動かしにいくことです。都市部の企業の洗練されたインターンシップにはない、泥臭くて、人間味あふれる「忘れられない体験」。これこそが、「この人たちと一緒に働きたい」「この町で暮らしてみたい」という、強烈な志望動機を生み出すのです。費用はかかるかもしれません。しかし、ミスマッチの少ない、熱意ある若者一人を採用できると考えれば、これほど費用対効果の高い投資はありません。
「よそ者」をヒーローに。移住・Uターン社員が輝く組織文化の作り方
おめでとうございます。これらの戦略が実を結び、ついに都会から意欲ある若者が入社してくれました。しかし、本当の勝負はここからです。彼らが地域や会社に馴染めず、孤立して早期に辞めてしまっては、今までの努力が水の泡です。採用した「よそ者」を定着させ、活躍してもらうための組織文化作りが、何よりも重要になります。
ありがちなのが、昔からの慣習や人間関係を重んじるあまり、新しく入ってきた移住者やUターン社員が、窮屈な思いをしてしまうケースです。彼らを「何も知らない若者」として扱うのではなく、新しい視点や価値観を持ち込んでくれる「ヒーロー」として、最大限にリスペクトし、歓迎する雰囲気を作りましょう。
例えば、SNSでの情報発信担当を、移住してきた若手社員に任せてみる。彼らの「よそ者視点」だからこそ発見できる、地域の新たな魅力があるはずです。あるいは、社内の新しいプロジェクトのリーダーに抜擢し、裁量権を与える。彼らの成功体験が、後に続く若者たちの希望になります。
また、会社が積極的に地域コミュニティとの橋渡し役になることも大切です。地元のイベントに一緒に参加したり、同世代の若者を紹介したりと、プライベートな面でも孤立させないための配慮が、彼らの定着率を大きく左右します。移住してきた社員が、仕事でもプライベートでも輝いている。その姿こそが、次の採用における、何よりの説得力を持つ生きた広告塔になるのです。


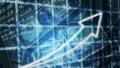
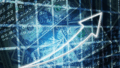
コメント