
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 「今年は良い人が採れない」と、毎年同じ悩みを天気のせいにするかのように繰り返している経営者や人事担当者の方
- 面接官によって評価がバラバラで、自社の採用基準が全く定まっていない会社の方
- 採用活動が、特定の「見る目のある」担当者の“職人芸”に依存してしまっている方
- 感覚ではなく、データと仕組みによって、採用という最も重要な経営課題を解決したい方
「どうも今年は、良い人材に巡り会えなくて…」「ウチのA部長は人を見る目があるんだけど、彼が面接しないと、どうもダメでね」。採用活動についてお話を伺うと、そんな言葉を本当によく耳にします。まるで、採用の成否が、その年の“運勢”や、特定の面接官が持つ“特殊能力”によって決まる、神秘的な儀式であるかのように。
しかし、厳しいことを言いますが、もしあなたの会社がそんな状況であるなら、それは「採用戦略」などという立派な代物ではありません。ただの「ギャンブル」です。そして、そのギャンブルに、あなたの会社の大切な未来を賭けているのです。今回は、なぜその『勘頼りの採用』が会社を滅ぼすのか、そして、運や個人のスキルに頼らず、安定して優秀な人材を獲得するための唯一の方法、『採用のパターン化』について、具体的にお話しします。
あなたの会社の採用は、なぜ「ギャンブル」なのか
なぜ、私が「ギャンブル」だと断言するのか。それは、あなたの会社の採用が、あまりに「属人的」だからです。
面接官のその日の気分や、候補者との個人的な相性で、評価がいとも簡単にブレる。ある面接官が高く評価した候補者を、別の面接官は「ピンとこない」と一蹴する。採用基準が曖昧だから、結局は「なんとなく良さそう」という印象で採用が決まる。その結果、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが多発し、多額の採用コストと教育コストをかけた人材が、あっけなく辞めていく。こんな、再現性のない行き当たりばったりの活動で、どうやって強い組織を作れるというのですか。
ステップ①:「求める人物像」を言語化し、パターン化せよ
まず、あなたがやるべきことは、採用媒体を探すことではありません。「良い人」という、呪いのように曖昧な言葉を、あなたの会社の辞書から完全に抹消することです。
そして、あなたの会社が本当に求める人物像を、具体的な「行動」のレベルまで、徹底的に言語化(パターン化)するのです。「コミュニケーション能力が高い人」などという、誰でも言える言葉ではダメです。「会議の場で、自分と異なる意見が出た際に、まず相手の意見を肯定的に受け止め、その上で、具体的なデータを用いて自身の主張を論理的に述べることができる人」。ここまで具体的に定義するのです。この、誰が読んでも同じ人物を思い描けるレベルの「求める人物像」こそが、全ての採用活動の羅針盤となります。
ステップ②:「面接」という名の“茶番”を、科学に変えよ
求める人物像が定義できたら、次は「面接」という名の茶番劇を、再現性のある「科学」へと変える作業です。その最強の武器が、「構造化面接」です。
これは、事前に「評価項目」と「それを見極めるための質問」を全て設計し、全ての候補者に対して、全ての面接官が、同じ質問を、同じ順番で行う面接手法です。そして、候補者の回答を、あらかじめ用意された「評価シート」という“共通の物差し”で点数付けしていく。これにより、面接官の「勘」や「印象」といった、曖昧で不公平な要素を徹底的に排除し、誰が面接官を務めても、評価がブレない仕組みを構築するのです。Google社をはじめ、多くの先進的な企業が、この構造化面接によって採用の精度を劇的に高めたことは、有名な事実です。
結論:採用は「アート」ではなく「サイエンス」である
もうお分かりですね。現代の採用活動は、一部のカリスマ採用担当者の「アート(芸術)」に依存するものであってはなりません。それは、データと仕組みに基づいた、誰でも(訓練すれば)再現可能な「サイエンス(科学)」であるべきなのです。
求める人物像をパターン化し、それを見極めるための質問をパターン化し、評価基準をパターン化する。この、一見すると無味乾燥で、クリエイティビティの欠片もないような地道な「パターン化」の積み重ねこそが、運や偶然といった不確定要素を排除し、継続的に会社の未来を創る優秀な人材を獲得するための、唯一にして最強の採用戦略なのです。
さあ、あなたの会社のそのギャンブル、いつまで続けますか?

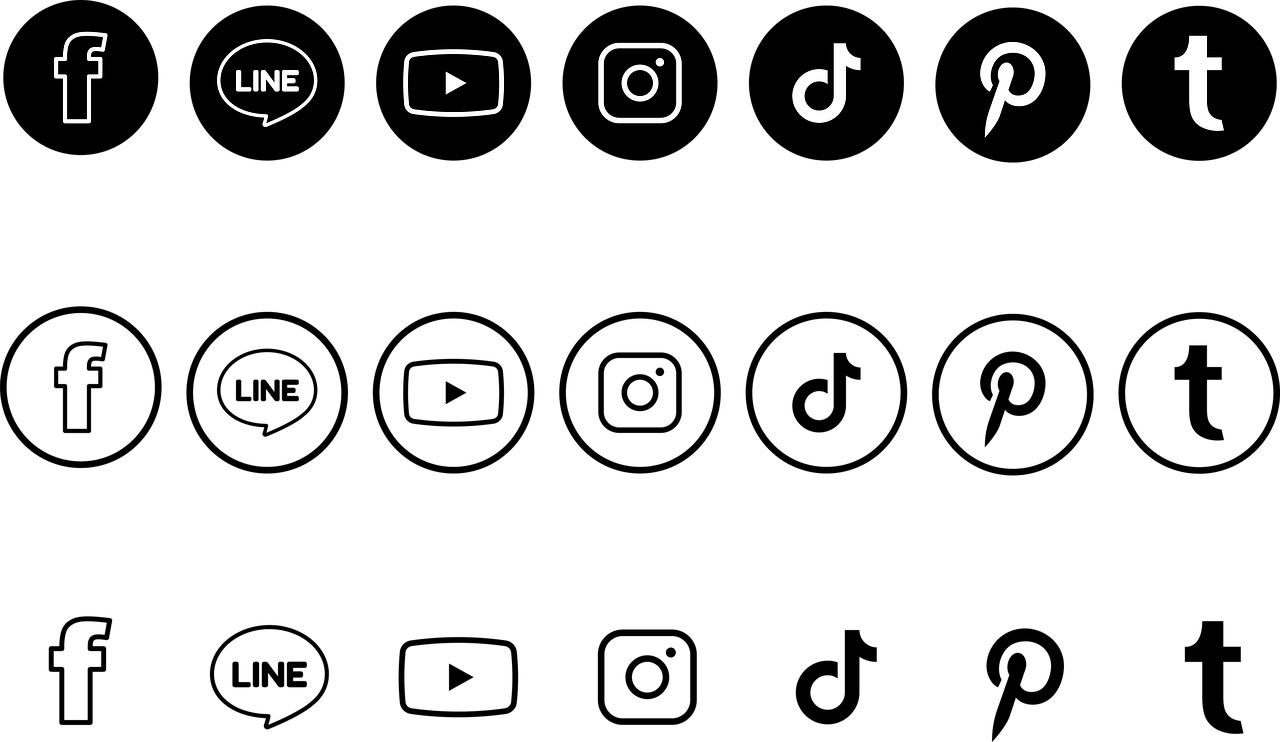
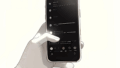

コメント