
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 会社の知名度が低くて、新卒採用に苦戦している経営者の方
- 採用にお金をかけられないけど、とにかく人が欲しい採用担当者の方
- 大手ナビサイトに掲載しても、全く応募が来なくて心が折れそうな方
- 綺麗事の採用論ではなく、具体的で泥臭い方法が知りたい方
- 来年度こそは、なんとしてでも新卒の頭数を確保したいと考えている方
会社の未来を担う、若くて優秀な人材。喉から手が出るほど欲しいですよね。でも、現実は厳しい。大手就活サイトに高いお金を払って掲載しても、エントリーは数えるほど。説明会を開いても、席はガラガラ。「うちには魅力がないのか…」なんて、落ち込んでいませんか?
わかります。その気持ち、痛いほど。中小企業にとって新卒採用は、大手企業と同じ土俵で戦う、あまりにも不利なゲームです。知名度、給与、福利厚生、どれをとっても太刀打ちできない。だから、普通にやっていては絶対に勝てません。
でも、諦めるのはまだ早い。戦い方を変えれば、やり方を変えれば、知名度ゼロ、予算ゼロの会社でも、新卒を「かき集める」ことは可能です。この記事では、綺麗事を一切抜きにして、とにかく新卒の母集団を形成し、応募数を最大化するための、少し禁断とも言える具体的な戦略を、余すところなくお伝えします。これは、理想の採用を語るものではありません。なりふり構わず、まずは「数」を確保するための、泥臭い戦術書です。覚悟はいいですか?
なぜあなたの会社に新卒が来ないのか?残酷な現実を直視しよう
まず、一番つらい話から始めましょう。なぜ、あなたの会社に学生は来てくれないのでしょうか。「ウチの会社の良さは、入社すればわかるのに…」「アットホームな社風が魅力なんだけどな」そう思っているかもしれません。でも、その想いは、残念ながら学生には1ミリも届いていません。
株式会社マイナビが2025年卒の学生を対象に行った調査によると、学生が企業選びで重視する項目は、1位「安定している」(49.7%)、2位「自分のやりたい仕事(職種)ができる」(41.9%)、3位「給料のよい」(32.8%)と続きます。悲しいですが、これが現実です。多くの中小企業がアピールしがちな「社風の良さ」や「成長できる環境」といった曖昧な言葉は、残念ながら優先順位が低いのです。
さらに言えば、学生は「知らない会社」にはエントリーすらできません。世の中には400万社以上の企業がある中で、学生が就職活動で知ることができる企業は、ほんの一握り。その中で、あなたの会社が偶然見つけてもらえる確率は、天文学的に低いと言わざるを得ません。
「大手ナビサイトに掲載すれば見てもらえる」というのも幻想です。何十万円、何百万円という広告費を払っても、あなたの会社のページは、その他大勢の企業の中に埋もれてしまいます。学生は、まず自分が知っている企業や、検索上位に出てくる人気企業からチェックしていきます。わざわざ何十ページもめくって、聞いたこともない会社を探してくれる学生は、ほぼ皆無です。
つまり、今のやり方を続けている限り、あなたの会社に学生が殺到することは絶対にない。この残酷な現実を、まずはしっかりと受け止め、直視することから始めましょう。プライドは一旦、ゴミ箱に捨ててください。ここがスタートラインです。
母集団形成の常識を疑え!「量」を確保するための逆張り思考
現実を直視できたら、次は具体的なアクションです。とにかく新卒をかき集めるためには、「母集団形成」、つまり、あなたの会社のことを知ってくれる学生の数を、圧倒的に増やす必要があります。しかし、先ほども言った通り、大手ナビサイトで正面から戦うのは愚策です。では、どうするか?答えは「逆張り」です。大手がやらない、できない戦い方で、量を確保するのです。
ダイレクトリクルーティングサイトを使い倒す
まず、絶対に活用すべきなのが、ダイレクトリクルーティングサイトです。OfferBoxやキミスカといったサービスが有名ですね。これらは、企業側から学生に直接アプローチできるのが最大のメリット。ナビサイトのように「待ち」の姿勢ではなく、「攻め」の採用が可能です。
重要なのは、ここでのターゲット設定です。「有名大学の優秀な学生」なんて高望みはしてはいけません。狙うべきは、「まだ大手企業から声がかかっていない、可能性を秘めた学生」です。プロフィールを細かく読み込み、「お、この経験は面白そうだな」「文章から誠実さが伝わってくるな」と感じた学生に、片っ端からオファーを送りましょう。
ここでケチってはいけません。月々の送信上限数があるなら、必ず使い切るくらいの気概で臨んでください。一通一通、心を込めて文章を作るのが理想ですが、まずは量を担保することが最優先。テンプレートを少しカスタマイズする形でもいいので、とにかく多くの学生に「あなたのことを見ていますよ」というシグナルを送るのです。大手企業が見向きもしないような、地方の大学や、少し変わった経験を持つ学生の中にこそ、あなたとの会社と相性の良い人材が眠っています。
大学のキャリアセンターと人間関係を築く
オンラインだけでなく、オフラインの泥臭い活動も重要です。特に、地方大学や、あなたの会社の事業内容と親和性の高い学部を持つ大学のキャリアセンターには、積極的に足を運びましょう。
一度挨拶して求人票を送るだけでは意味がありません。担当者の方と顔見知りになり、「〇〇会社の△△さんね」と覚えてもらうことがゴールです。定期的に訪問し、会社の近況を報告したり、情報交換をしたりする。そうやって人間関係を築いておけば、「面白い会社があるよ」「この学生さん、合いそうだ」と、キャリアセンターの担当者から直接、学生を紹介してもらえるケースが出てきます。
これは、お金では買えない、非常に強力なパイプになります。東京の有名大学ばかりに目を向けるのではなく、まだ見ぬ優秀な学生が眠る、地方の大学との関係構築にこそ、時間と労力を投資すべきです。
学生の心を鷲掴みにする「尖った」情報発信術
さて、学生との接点が増えてきたら、次は「いかに興味を持ってもらうか」が勝負になります。ここで、ありきたりな会社の紹介をしていては、その他大勢に埋もれてしまいます。給料や福利厚生で勝負できないなら、それ以外の部分で、強烈なインパクトを残す必要があります。キーワードは「尖る」ことです。
万人受けを捨て、「あなた」に語りかける
あなたの会社は、全ての人に好かれる必要はありません。むしろ、「こんな会社、絶対イヤだ」という人が99人いてもいいのです。残りの1人が「この会社、ヤバい!面白そう!」と熱狂してくれれば、それで採用は成功です。
そのためには、自社の「強み」と「弱み」を、包み隠さずさらけ出す勇気が必要です。例えば、
「うちは正直、給料は高くありません。でも、入社1年目からガンガン、プロジェクトを任せます。失敗を恐れず、最速で成長したい人だけ来てください」 「残業がないとは言えません。でも、BtoBのニッチな分野で、国内シェアNo.1の技術を持っています。世界を相手に自分のスキルを試したいなら、最高の環境です」
どうでしょうか。このように、弱みを正直に開示した上で、それを上回る強烈なメリットを提示するのです。こうすることで、「成長意欲の高い学生」「専門性を身につけたい学生」といった、特定の層にメッセージが深く突き刺さります。綺麗で無難な言葉を並べるよりも、よっぽど心に響くはずです。
SNS、特にTikTokを本気でやる
今の学生は、企業の公式サイトやナビサイトの情報よりも、SNS上のリアルな声を信頼します。特に、TikTokの活用は必須と言っても過言ではありません。
「うちみたいな真面目な会社がTikTokなんて…」と思うかもしれません。その考えが、時代遅れなのです。なにも、社員に無理やり踊らせる必要はありません。例えば、
- 若手社員の一日に密着したVlog
- ベテラン職人の「神ワザ」を紹介する動画
- オフィスツアーや、社員食堂の紹介
- 採用担当者が、就活生の悩みに本音で答える動画
など、切り口は無限にあります。大切なのは「リアルさ」と「人間味」です。少しダサくても、素人っぽくても構いません。加工されていない、ありのままの会社の姿を見せることで、学生は親近感を抱き、興味を持ってくれます。1本の動画がバズれば、それだけで何百、何千という学生に会社を知ってもらうことができる。これは、何百万円もする広告よりも、はるかに費用対効果の高い宣伝活動です。
説明会・選考は「劇場型」で惹きつけろ!応募数を最大化する仕掛け
情報発信で興味を引いたら、次はいよいよ説明会や選考です。ここでも、普通のことをやっていては学生の心は掴めません。参加してくれた学生を「絶対にこの会社に入りたい!」という気持ちにさせるための、「劇場型」の仕掛けを用意しましょう。
社長が魂で語る、熱狂のプレゼンテーション
学生が、中小企業の説明会で一番聞きたいのは、誰の話だと思いますか?人事担当者の当たり障りのない話ではありません。「社長」の言葉です。
会社のトップである社長が、自らの言葉で、会社のビジョンや、事業にかける想い、なぜ新卒採用にこだわるのかを、熱く、魂を込めて語る。その熱量が、学生の心を揺さぶります。「この人についていきたい」「この船に乗ってみたい」と思わせることができれば、会社の規模や知名度なんて、もはや関係ありません。社長自身が、最強の採用コンテンツなのです。プレゼン資料をただ読むのではなく、時には身振り手振りを交え、学生の目を見て、語りかける。その熱狂が、会場全体に伝播します。
「即日内定」も辞さない、スピード感のある選考
選考プロセスも、工夫次第で応募数を劇的に増やすことができます。例えば、「説明会参加者は、一次選考免除」といった特典をつけるのは、もはや当たり前。さらに踏み込むなら、「グループワークで活躍した学生は、その場で最終面接」「社長面談でOKが出たら、即日内定」といった、スピード感のある選考フローを導入してみましょう。
もちろん、これは誰にでも内定を出すということではありません。しかし、「チャンスは目の前にある」という状況は、学生のモチベーションを劇的に高めます。ダラダラと数週間もかかる選考に比べて、その場で結果がわかるスリリングな体験は、記憶に強く残ります。他社の選考が進む前に、いち早く優秀な学生を囲い込むための、非常に有効な戦略です。
内定辞退を防ぐ最終防衛ライン。なりふり構わぬ「人間的」フォロー術
苦労して内定を出しても、辞退されてしまっては元も子もありません。株式会社リクルートの「就職白書2024」によると、2024年卒の学生の就職内定辞退率は、驚くべきことに61.1%にも上ります。つまり、内定を出した学生の半分以上が、他社へ行ってしまうのです。この最終局面で負けないために、なりふり構わぬ「人間的」なフォローで、学生の心を繋ぎ止めましょう。
重要なのは、「接触回数」と「特別感」です。内定を出した後、入社まで一切連絡をしないなんていうのは論外。最低でも月に1〜2回は、電話やLINE、メールなどでコミュニケーションを取りましょう。
その際、事務的な連絡だけでは意味がありません。「最近、就活どう?」「卒業研究は順調?」といった、パーソナルな会話を心がけてください。そして、若手の先輩社員をメンターとしてつけ、気軽に相談できる関係性を築くのも非常に効果的です。学生は「この会社は、自分のことを一人の人間として大切にしてくれている」と感じ、心理的な繋がりが強まります。
さらに、オファー面談では、給与や待遇の話だけでなく、「あなたに、こんな仕事を任せたいんだ」「君のこういう経験が、うちの会社で絶対に活きると思う」と、その学生個人に向けた「期待」を具体的に伝えてください。他の誰でもない、「あなたが必要なんだ」というメッセージが、最後の最後で学生の心を動かすのです。
とにかく、内定者一人ひとりと向き合い、不安を取り除き、ファンになってもらう。その地道で人間臭い努力こそが、内定辞退を防ぐ最も強力な防衛ラインとなります。
まとめ:かき集めた後、どうするか
ここまで、とにかく新卒をかき集めるための、少し過激な方法についてお話ししてきました。
残酷な現実を直視し、常識を疑う逆張り思考で母集団を形成する。尖った情報発信で特定の学生に深く刺さり、劇場型の選考で心を鷲掴みにする。そして、人間的なフォローで内定辞退を防ぐ。
この戦略は、綺麗事ではありません。しかし、採用市場という戦場で、体力のない中小企業が生き残るためには、こうした泥臭い戦術が必要不可欠です。
最後に一つだけ。この方法で「かき集めた」大切な新入社員たちを、入社後に「使い捨てる」ようなことがあっては、絶対に長続きしません。彼らが「この会社に入ってよかった」と心から思えるような、育成の仕組みや、活躍できる環境を整えること。それこそが、次の採用活動を成功させる、最高のブランディングになるのです。
まずは、行動あるのみ。今日お話しした中の一つでもいいので、すぐに試してみてください。あなたの会社の未来は、その一歩にかかっています。


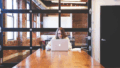

コメント