
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 優秀な人材に内定を出したのに、辞退されてしまい頭を抱えている人事・採用担当者
- 内定者とどうコミュニケーションを取ればいいか分からず、とりあえず放置してしまっている方
- 内定者懇親会などの画一的なフォローに、効果を感じられなくなっている方
- 多大な時間とコストをかけた採用活動を、最後の最後で無駄にしたくないと考えている方
- これから入社するメンバーのエンゲージメントを、入社前から高めておきたい経営者・マネージャー
何十時間にも及ぶ書類選考と、幾度となく重ねた面接。数多の候補者の中から、ようやく見つけ出した「金の卵」。
「ぜひ、うちの会社に来てほしい!」
その想いが通じ、内定を承諾してもらえた時の喜びは、何物にも代えがたいですよね。しかし、その安堵も束の間、入社を数ヶ月後に控えたある日、一本の電話が鳴ります。
「誠に申し訳ございませんが、内定を辞退させていただきたく…」
この瞬間の、天国から地獄へ突き落とされたような絶望感と徒労感。採用担当者であれば、一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
株式会社リクルートの「就職プロセス調査(2024年卒)」によると、就職内定辞退率は61.1%にものぼります。これは、内定を得た学生の6割以上が、少なくとも1社以上の内定を辞退しているという事実を意味します。
内定辞退は、「運が悪かった」のではありません。その多くは、対策をすれば防げる「人災」です。そして、その原因のほとんどは、内定を出してから入社までの「空白期間」における、コミュニケーションの失敗にあります。
この記事では、その「空白期間」を、内定者の不安を取り除くどころか、ファンにしてしまう「最高の企業体験」に変えるための、戦略的なフォローアップ術を5つの原則として徹底解説します。
原則1: 「沈黙」は禁物。接触頻度を戦略的にデザインする
内定を出して、承諾をもらった。これで一安心…と、入社式の数週間前まで何も連絡をしない。これは、内定者フォローにおいて最もやってはいけない、最悪の選択です。
考えてみてください。内定者にとって、入社までの数ヶ月間は、期待と同時に大きな不安を抱える期間です。特に複数の内定を持っている場合、「本当にこの会社で良かったのだろうか?」という迷い(いわゆる内定ブルー)が心をよぎります。
そんな最も不安定な時期に、会社から何の連絡もなければ、内定者はどう感じるでしょうか? 「自分は本当に歓迎されているのだろうか?」 「もしかして、忘れられているんじゃないか?」 「他の会社はあんなに丁寧なのに…」
この「放置」こそが、不安を増大させ、他社への心を傾かせる最大の原因なのです。
アメリカの心理学者ロバート・ザイアンスが提唱した「単純接触効果」というものがあります。これは、人は、繰り返し接触するものに対して好意を抱きやすくなる、という心理効果です。これは、恋愛やマーケティングだけでなく、採用活動にも完全に当てはまります。
コミュニケーションプランを立てる
では、具体的にどうするか。場当たり的に連絡するのではなく、「コミュニケーションプラン」を設計しましょう。
- 月1回のニュースレター配信: 会社の最新ニュース、新しいサービスの紹介、社員インタビュー、メディア掲載実績など、「会社の今」が分かる情報を届けます。内定者が「この会社、勢いがあるな」「面白そうな人がいるな」と感じるきっかけになります。
- 2週間に1回のカジュアルな連絡: 人事担当者から、「最近どうですか?」「卒論は順調ですか?」といった、ごく短いメールやチャットを送るだけでも効果は絶大です。「私たちはあなたのことを気にかけていますよ」というメッセージが伝わります。
- 2〜3ヶ月に1回のオンラインイベント: 全員参加の堅苦しいものではなく、自由参加のオンライン座談会や、若手社員との交流会などを設定します。
重要なのは、接触を「点」ではなく「線」で捉え、内定から入社まで、意識的に関係性を繋ぎ続けることです。沈黙は、内定者の心に疑念の種をまく、ということを肝に銘じてください。
原則2: “One of them”から“Only for you”へ。特別感で心を掴む
定期的な接触が重要だとお話ししましたが、その内容が全員に同じ文面の一斉送信メールだけでは、効果は半減します。人は、「その他大勢の中の一人」として扱われることよりも、「特別なあなた」として扱われることに、心を動かされる生き物だからです。
内定辞退を防ぐフォローアップの極意は、「パーソナライゼーション(個別最適化)」にあります。
あなたは、面接で内定者とたくさんの話をしたはずです。彼らがどんなことに興味を持ち、どんな価値観を大切にし、将来どんなキャリアを歩みたいと考えているのか。その貴重な情報を、内定承諾と同時に忘れてしまってはいませんか?
「あなたのこと、覚えていますよ」というメッセージ
その個人情報を、ぜひフォローアップに活用してください。
- 面接内容に触れる: 「〇〇さんが面接でお話しされていた△△のスキルですが、うちのマーケティング部でまさに必要とされている力なので、チームも期待していますよ」
- 興味に合わせた情報提供: 「そういえば、〇〇さんは現代アートがお好きだと伺いました。今度、会社の近くの美術館でこんな展示が始まるみたいですよ」
- 手書きのメッセージ: 内定承諾のお礼状に、印刷された文面だけでなく、担当者から手書きで一言添える。
これらの小さな積み重ねが、「この会社は、私のことを一人の人間として、ちゃんと見てくれている」という強烈な特別感と信頼感を生み出します。
メンター制度の導入
さらに効果的なのが、内定者一人ひとりに対して、年齢やバックグラウンドの近い若手社員を「メンター」としてアサインすることです。人事には相談しづらい、給与や残業、人間関係といったリアルな悩みを、先輩に気軽に聞ける環境を用意します。
この1対1の関係性が、内定者にとって強力な心理的セーフティネットとなり、「入社後に頼れる人がいる」という安心感は、内定辞退の強力な抑止力となります。その他大勢向けの懇親会を1回開催するよりも、一人のメンターとの30分の雑談の方が、内定者の心を掴むことがあるのです。
原則3: キラキラ情報の罠。あえて「不都合な真実」も語る勇気
内定者に対して、自社の良いところばかりをアピールしたい。その気持ちはよく分かります。しかし、キラキラした情報だけを過剰に提供するのは、逆効果になる危険性をはらんでいます。
なぜなら、賢い内定者ほど、「そんな良いことばかりのはずがない。何か隠しているのではないか?」と、かえって不信感を抱いてしまうからです。そして、内定辞退の最も大きな理由の一つが、この「入社後のギャップ」への不安です。
「聞いていた話と違う」という裏切り感をなくすためには、良い情報だけでなく、ある程度の「不都合な真実」も、誠実に伝える勇気が必要です。
誠実さが、最後の信頼を勝ち取る
もちろん、ネガティブな情報ばかりを伝える必要はありません。重要なのは、仕事の「光」と「影」の両面を、セットで伝えることです。
- 現場社員との座談会: 人事だけでなく、実際に現場で働く様々な部署の社員と話す機会を設けましょう。その際、「入社して一番大変だったことは何ですか?」「それをどうやって乗り越えましたか?」といった、リアルな質問を歓迎する雰囲気を作ることが重要です。
- 仕事のリアルを開示する: 例えば、営業職であれば、「もちろん目標達成は簡単ではないし、時には厳しいフィードバックを受けることもある。でも、それを乗り越えてお客様から『ありがとう』と言われた時の達成感は、本当に最高だよ」というように、大変さとやりがいを正直に伝えます。
- 評価制度やキャリアパスの現実: 「入社3年で全員がマネージャーになれるわけではない。でも、こういう成果を出した人が、こういうプロセスを経て昇進している」というように、理想論ではなく現実的なキャリアの歩み方を示します。
この「誠実さ」と「透明性」こそが、内定者の「この会社は信頼できる」という最終的な判断を後押しします。耳障りの良い言葉で固めたメッキは、いずれ剥がれます。飾らない等身大の姿を見せることこそが、長期的な信頼関係を築くための最短ルートなのです。
原則4: 「孤独」という最大の敵を倒す。「仲間」の絆を育む仕掛け
「入社後、周りの人と上手くやっていけるだろうか…」 「同期に優秀な人ばかりいたら、ついていけないかもしれない…」
仕事内容や待遇と同じくらい、あるいはそれ以上に、内定者が抱える大きな不安が「人間関係」です。特に、同期入社となる「仲間」の存在は、入社後の会社生活を支える上で、非常に重要な役割を果たします。
この「孤独」という感情は、入社への不安を増幅させ、内定ブルーを引き起こす大きな要因となります。だからこそ、会社側が意図的に、内定者同士の繋がりを早期に作るための「仕掛け」を用意することが効果的なのです。
共同体験で連帯感を醸成する
ただ懇親会で顔を合わせるだけでは、表面的な関係で終わってしまいます。一歩踏み込んで、内定者同士が「共同体験」を通じて、自然と仲を深められるような機会を作りましょう。
- 内定者専用オンラインコミュニティの開設: SlackやTeams、LINEのオープンチャットなどを活用し、内定者と人事担当者がいつでも気軽にコミュニケーションを取れる場を用意します。単なる情報伝達の場ではなく、自己紹介スレッドを立てたり、趣味のチャンネルを作ったりして、内定者同士の自発的な交流を促します。
- 簡単なグループワークの実施: 「私たちの会社の魅力を、学生に伝えるためのキャッチコピーを考えよう」「入社後にやってみたいことをテーマに、3分間のプレゼン資料を作ろう」といった、オンラインで完結する簡単なグループワークを課します。一つの目標に向かって協力する体験は、驚くほど早くチームの連帯感を生み出します。
- 部活動・サークル紹介: 会社に部活動やサークルがあれば、その活動を紹介し、内定者の中から同じ趣味を持つ人同士を繋げる手伝いをするのも良いでしょう。「〇〇さんと△△さんは、二人ともサッカーが好きみたいなので、今度うちのフットサル部に体験参加してみませんか?」といった形です。
入社前から「仲間がいる」という安心感は、内定者にとって何よりの心の支えになります。彼らを孤独にさせてはいけません。
原則5: 「待つ」のではなく「育てる」。入社までの成長を支援する
「入社までの間、何か勉強しておくべきことはありますか?」
意欲的な内定者から、こんな質問を受けたことはありませんか? この問いの裏には、「入社後、仕事についていけるだろうか」というスキル面での不安が隠れています。
この問いに対して、「特にありません。今は学生生活を楽しんでください」と答えるだけでは、あまりにもったいない。これは、内定者のエンゲージメントを高める絶好のチャンスなのです。
最後の原則は、内定者をただ「待つ」客体として捉えるのではなく、入社までの期間を成長のために使い、スムーズにスタートダッシュが切れるよう支援する、「育てる」視点を持つことです。
成長支援が、最高のエンゲージメントを生む
会社が自分の成長を応援してくれている、投資してくれている、という実感は、「この会社は自分を大切にしてくれている」という強力なメッセージとなり、エンゲージメントを飛躍的に高めます。
- 推奨図書の提供: 職種ごとに、入社前に読んでおくと役立つ書籍をリストアップし、数冊を会社からプレゼントします。
- e-learningコンテンツの提供: UdemyやCoursera、あるいは自社で契約している学習プラットフォームのIDを内定者に先行して付与し、自由に学習できる環境を提供します。
- 資格取得支援: 業務に関連する資格(例: ITパスポート、簿記、TOEICなど)の取得を推奨し、受験費用や教材費を会社が補助します。
- 事前課題の提供: エンジニア職であれば、簡単なコーディング課題を出すなど、実務に繋がる課題を提供し、先輩社員がフィードバックする機会を設けます。
もちろん、これらはすべて任意参加が前提です。しかし、成長意欲の高い内定者にとって、これほど魅力的なフォローはありません。「入社が楽しみだ」という気持ちを醸成すると同時に、入社後の立ち上がりをスムーズにし、結果として早期離職を防ぐ効果も期待できます。
まとめ:内定者フォローとは、未来の仲間への「最初の投資」である
内定辞退を防ぐための5つの原則、いかがでしたでしょうか。
- 接触頻度をデザインする
- 特別感を演出する
- リアルな情報を誠実に語る
- 仲間の絆を育む
- 入社までの成長を支援する
これらを見て気づくのは、もはや内定者フォローは、単なる採用活動の最終工程ではない、ということです。それは、新しく迎える仲間が、入社後にスムーズに組織に馴染み、早期に活躍してもらうための「オンボーディング(定着支援)の始まり」に他なりません。
小手先のテクニック以上に重要なのは、内定者を「管理」や「確保」の対象として見るのではなく、未来を共に創っていく「パートナー」として、一人の人間として真摯に向き合う姿勢です。
「あなたと一緒に働ける日を、心から楽しみにしています」
その想いを、行動で示し続けること。それこそが、あらゆるマニュアルに勝る、最強の内定者フォローなのかもしれません。



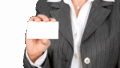
コメント