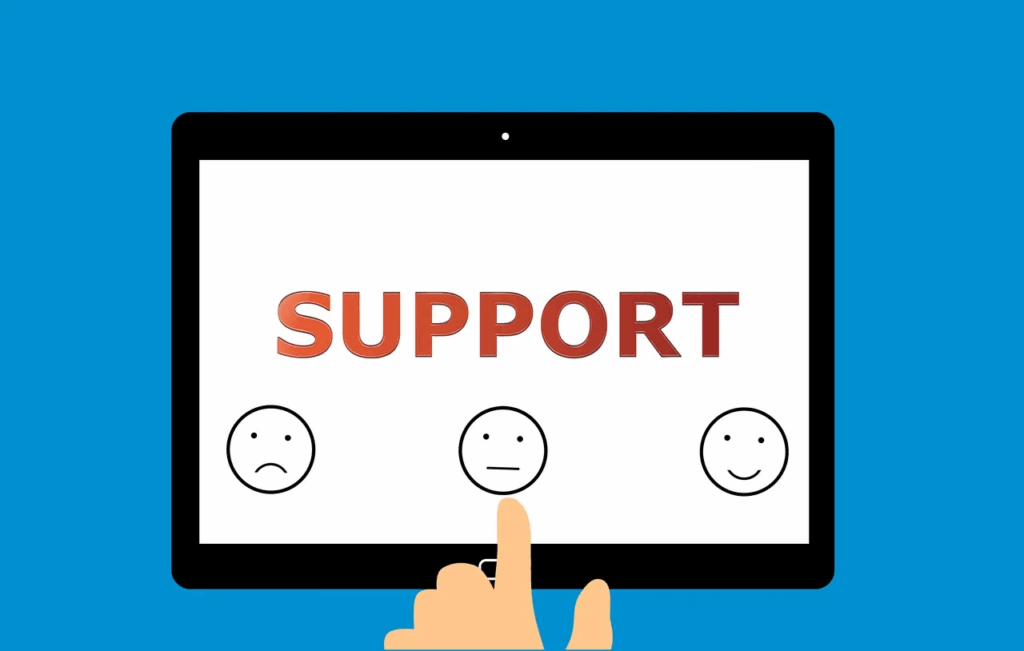
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 会社員として働きながら、副業で自営業(フリーランス)を始めようと考えている方
- 副業収入が年間20万円を超えそうで、税金や社会保険の手続きが不安な方
- 「副業すると会社の社会保険料が上がるの?」という疑問を持っている方
- 会社員と自営業のハイブリッドな働き方で、賢く手取りを最大化したい方
- 将来の独立も視野に入れつつ、まずは副業からスモールスタートしたい方
働き方が多様化する現代、会社の給料だけに頼るのではなく、自分のスキルや好きなことを活かして副業を始める人が急増しています。特に、会社員として安定した基盤を維持しながら、個人で仕事を受ける「会社員×自営業」というハイブリッドなスタイルは、非常に現実的で魅力的な選択肢ですよね。
しかし、収入の柱が増える喜びと同時に、多くの人がこんな不安にぶつかります。「副業で稼いだ分、税金や社会保険料ってどうなっちゃうの?」「頑張って稼いだのに、ごっそり引かれて手元にあまり残らないんじゃ…?」
その気持ち、とてもよく分かります。お金の仕組みは複雑で、特に会社員と自営業の2つの顔を持つ場合のルールは、誰もが一度は混乱するポイントです。この記事では、そんなあなたの不安を解消するため、会社員をしながら自営業で収入を得た場合の「税金」と「社会保険」の仕組みを徹底的に解剖します。具体的な年収モデルケースを使いながら、手取り額がどう変わるのかをリアルにシミュレーション。この記事を読めば、漠然としたお金の不安から解放され、自信を持って副業のアクセルを踏めるようになるはずです。
まずは基本!会社員と自営業で「社会保障」はこう違う
シミュレーションに入る前に、まずは基本の確認から始めましょう。会社員と自営業では、加入する社会保険や税金の納め方が根本的に異なります。この違いを理解することが、ハイブリッドワークのお金の仕組みを理解する第一歩です。
会社員の場合
会社に勤めているあなたは、給与明細を見るまでもなく、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険といった社会保険に加入しています。これらの保険料の大きな特徴は、会社が半分を負担してくれる(労使折半)ということです。そして、残りの自己負担分は毎月の給与から天引きされるため、自分で手続きをする必要はありません。税金(所得税・住民税)も、基本的には年末調整で会社が計算してくれます。まさに、手厚く守られた状態と言えるでしょう。
自営業(個人事業主)の場合
一方、フリーランスなどの自営業者は、自分で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を全額自己負担で納める必要があります。令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円、国民健康保険料は前年の所得に応じて決まりますが、収入が増えればその負担も大きくなります。税金も、年に一度、自分で売上や経費を計算して確定申告を行い、納税額を確定させて納付しなければなりません。
「会社員 × 自営業」のハイブリッドな場合は?
では、この2つを兼業する場合はどうなるのでしょうか?ルールは意外とシンプルです。
「メインの勤務先である会社の社会保険が優先される」
これが大原則です。つまり、あなたが会社員である限り、会社の健康保険と厚生年金に加入し続けます。副業である自営業の収入がいくら増えようとも、原則として、国民健康保険や国民年金に二重で加入する必要はありません。 これは、副業をする会社員にとって非常に大きなメリットと言えるでしょう。
副業収入で社会保険料は上がる?知っておきたい「標準報酬月額」の仕組み
「会社の社会保険に加入し続けるのは分かった。でも、副業で収入が増えたら、その分、会社の給料から天引きされる社会保険料も上がるんじゃないの?」
これは、誰もが抱く最大の疑問であり、最も誤解されやすいポイントです。
結論からお伝えします。あなたが会社員として働きながら、「自営業(事業所得や雑所得)」として副業収入を得ている限り、会社の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は1円も上がりません。
なぜなら、会社の社会保険料は「標準報酬月額」という基準で決まるからです。この「標準報酬月額」とは、ざっくり言うと「あなたの月給」のこと。具体的には、毎年4月〜6月の3ヶ月間に会社から支払われた給与(基本給、残業代、通勤手当などを含む)」の平均額を基に算出されます。
重要なのは、ここに含まれるのはあくまで「会社から支払われる報酬」だけだということです。あなたが個人で稼いだ自営業の収入は、この標準報酬月額の計算には一切含まれません。ですから、副業で月100万円稼いだとしても、会社からの給料が変わらなければ、天引きされる社会保険料も変わらないのです。これは、賢く手取りを増やす上で、絶対に覚えておきたいルールです。
ただし、注意点が一つ。もしあなたの副業が、フリーランスのような自営業ではなく、別の会社でのアルバイトやパートといった「雇用契約」である場合は話が別です。この場合、2つの会社から給与をもらうことになるため、両方の給与を合算した額で標準報酬月額が決定され、社会保険料が再計算されることになります。今回はあくまで「自営業」としての副業を前提に話を進めていきますね。
【年収別】手取り額はどう変わる?リアルなシミュレーション
さて、お待たせしました。ここからが本題です。実際に会社員としての給料に、自営業の収入が加わると、税金の負担はどれくらい増え、最終的な手取り額はどうなるのでしょうか。具体的なモデルケースで見ていきましょう。
【シミュレーションの前提条件】
- 働き手: 35歳、独身(扶養家族なし)
- 居住地: 東京都新宿区在住
- 会社員の給与: 年収400万円(社会保険料控除 約58万円、給与所得控除 124万円)
- 副業: 自営業(事業所得として申告)
- 経費: 副業の売上に対して30%かかると仮定
- 申告方法: 開業届と青色申告承認申請書を提出し、青色申告特別控除(65万円)を最大限活用
この前提で、副業の所得別に3つのパターンをシミュレーションします。
ケース1:副業の「所得」が年間20万円の場合
会社員の副業でよく聞く「20万円の壁」。これは所得税の話で、副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要になるというルールです。(ただし、住民税の申告は別途必要です)
- 副業売上: 28.6万円
- 経費: 8.6万円(売上の30%)
- 副業所得: 20万円
この場合、所得税の確定申告はしません。しかし、住民税は所得に対して課税されるため、市区町村へ申告が必要です。
- 増える税金(住民税): 20万円 × 10% = 2万円
- 手取りの増加額: 20万円(所得) – 2万円(住民税) = 18万円
所得が20万円なら、ざっくりその9割の18万円が手取りとして増えるイメージですね。
ケース2:副業の「所得」が年間100万円の場合
副業が軌道に乗り、年間で100万円の利益が出るようになったケースです。このレベルになると、確定申告が必須になります。青色申告のメリットを存分に活かしましょう。
- 副業売上: 143万円
- 経費: 43万円(売上の30%)
- 副業所得: 100万円
【税金の計算ステップ】
- 所得の合算:
- 給与所得:400万円 – 給与所得控除124万円 = 276万円
- 事業所得:100万円 – 青色申告特別控除65万円 = 35万円
- 総所得金額: 276万円 + 35万円 = 311万円
- 課税所得の計算:
- 総所得金額311万円 – 基礎控除48万円 – 社会保険料控除58万円 = 課税所得205万円
- (参考)副業なしの場合の課税所得:276万円 – 48万円 – 58万円 = 170万円
- 税金の増加額:
- 所得税: (課税所得205万円 × 税率10% – 控除額9.75万円) – (副業なしの場合の所得税7.25万円) = 10.75万円 – 7.25万円 = 3.5万円増
- 住民税: (事業所得35万円) × 10% = 3.5万円増
【手取りの増加額】
- 副業所得100万円 – (所得税増3.5万円 + 住民税増3.5万円) = 93万円
所得100万円に対して、税金の負担は約7万円。手取りで93万円もプラスになる計算です。青色申告の65万円控除がいかに強力かが分かりますね。
ケース3:副業の「所得」が年間300万円の場合
さらに事業が拡大し、会社員の給料に迫る勢いで稼げるようになった場合です。税金のステージも変わってきます。
- 副業売上: 428万円
- 経費: 128万円(売上の30%)
- 副業所得: 300万円
【税金の計算ステップ】
- 所得の合算:
- 給与所得:276万円
- 事業所得:300万円 – 青色申告特別控除65万円 = 235万円
- 総所得金額: 276万円 + 235万円 = 511万円
- 課税所得の計算:
- 総所得金額511万円 – 基礎控除48万円 – 社会保険料控除58万円 = 課税所得405万円
- 税金の増加額:
- 所得税: この所得レベルになると税率が20%に上がります。 (課税所得405万円 × 税率20% – 控除額42.75万円) – (副業なしの場合の所得税7.25万円) = 38.25万円 – 7.25万円 = 31万円増
- 住民税: (事業所得235万円) × 10% = 23.5万円増
- 個人事業税: 副業所得が290万円を超えると、個人事業税もかかります。 (所得300万円 – 事業主控除290万円) × 税率5% = 0.5万円増
【手取りの増加額】
- 副業所得300万円 – (所得税増31万円 + 住民税増23.5万円 + 事業税0.5万円) = 245万円
所得300万円に対して、税金合計は約55万円。税率が上がったことで負担感は増しますが、それでも手取りで245万円という大きな金額が残ります。
シミュレーションまとめ
| 副業所得 | 増える税金(合計) | 手取り増加額 |
| 20万円 | 約2万円 | 約18万円 |
| 100万円 | 約7万円 | 約93万円 |
| 300万円 | 約55万円 | 約245万円 |
このシミュレーションから分かるのは、「副業収入が増えれば税金も増えるが、それ以上に手取りは確実に増える」という事実です。そして、その手取り額を最大化する鍵が「節税」にあることも見えてきます。
副業するなら絶対使うべき!手取りを最大化する節税テクニック
シミュレーションで見たように、同じ所得でも、知識があるかないかで手元に残るお金は大きく変わります。ここでは、会社員×自営業のあなたが絶対に活用すべき節税テクニックを紹介します。
1. 「青色申告」はマストアイテム
今回のシミュレーションでも大活躍した「最大65万円の青色申告特別控除」。これは、事業所得から無条件で65万円を差し引けるという、まさに最強の節税策です。これをやらない手はありません。税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出するだけで、この恩恵を受けられます。e-Taxで電子申告するなどの要件はありますが、その手間を補って余りあるメリットです。
2. 経費を漏れなく計上する
自営業の所得は「売上 – 経費」で計算されます。つまり、経費を漏れなく計上することが、そのまま節税に直結します。副業のために購入したパソコンや書籍、打ち合わせの飲食代はもちろん、自宅で仕事をしているなら、家賃や光熱費、通信費の一部を「家事按分」して経費に計上できます。例えば、「家賃10万円の家の20%を仕事で使っている」と合理的に説明できるなら、月2万円(年間24万円)を経費にできるのです。日頃から事業に関連する支払いの領収書は必ず保管し、会計ソフトなどを活用してきっちり管理しましょう。
3. 所得控除をフル活用する(iDeCo・小規模企業共済)
税金は「所得」そのものではなく、所得から様々な「控除」を差し引いた「課税所得」に対してかかります。この所得控除を増やすことも有効な節税策です。 特に強力なのが「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「小規模企業共済」です。これらは、掛け金が全額所得控除の対象になるため、将来のための資産形成をしながら、目先の所得税・住民税を安くできるという一石二鳥の制度。会社員も加入できますが、自営業者として小規模企業共待に加入できるのはハイブリッドワーカーの特権とも言えます。
まとめ
会社員として安定した基盤を持ちながら、自営業で新たな収入の柱を築く。このハイブリッドな働き方は、リスクを抑えつつ収入アップを目指せる、非常に賢い生き方です。
今回の記事でお伝えしたかった重要なポイントをまとめます。
- 会社の社会保険は維持され、副業(自営業)収入で保険料は上がらない。
- 税金は増えるが、シミュレーションで分かる通り、手取りは確実にプラスになる。
- 手取りを最大化する鍵は「青色申告」「経費」「所得控除」という節税知識にある。
副業を始めたばかりの頃は、慣れない確定申告などに戸惑うこともあるかもしれません。しかし、お金の知識は、あなた自身とあなたの未来を守るための強力な武器になります。まずは年間所得20万円を一つの目安にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。実際に自分で稼ぎ、自分で税金を納めるという経験は、会社員として働いているだけでは得られない、貴重な学びを与えてくれるはずです。


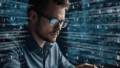

コメント