
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- SAPを導入しているけど、在庫がなかなか減らないと悩んでいる在庫管理担当者の方
- 「在庫はコストだ!」と分かっていながら、具体的な削減方法が見つからない経営者や部門長の方
- 過剰在庫と欠品の間で、いつも頭を悩ませている購買・生産管理担当者の方
- 勘と経験に頼った発注業務から脱却し、データに基づいたスマートな管理を実現したい方
- 会社のキャッシュフローを改善し、経営体質を強化したいと考えているすべての方
「うちの会社、倉庫に在庫が溢れているのに、なぜか肝心な時に必要なモノが足りなくなる…」
企業の在庫管理に携わっていると、こんなジレンマに陥ることはありませんか? 在庫は会社の資産であると同時に、管理コストや陳腐化リスクを抱える厄介な存在でもあります。特に、先行きが不透明な現代のビジネス環境において、過剰在庫はキャッシュフローを圧迫し、経営の足かせになりかねません。かといって、在庫を減らしすぎれば、急な需要増に対応できず、販売機会の損失や顧客からの信頼失墜に繋がってしまいます。
この永遠の課題ともいえる在庫管理の問題を解決する強力なツールが、実は多くの企業ですでに導入されているSAP、特にその中の資材管理(MM)モジュールなんです。SAP MMを単なる「購買・入出庫の記録ツール」だと思っているとしたら、それは非常にもったいない話。この記事では、SAP MMに秘められたポテンシャルを最大限に引き出し、無駄な在庫を削減しながら欠品を防ぐ、「攻めの在庫最適化」を実現するための具体的な方法を、データと実践的なステップに基づいて徹底的に解説していきます。
なぜ今、在庫最適化が重要なのか?見過ごせないコストとリスク
そもそも、なぜこれほどまでに「在庫を最適化しよう」と言われるのでしょうか。それは、在庫が目に見える「モノ」以上に、多くのコストとリスクを内包しているからです。
まず分かりやすいのが、在庫維持コストです。一般的に、在庫を維持するためには、年間で在庫金額の15%〜25%ものコストがかかると言われています。例えば、1億円の在庫を抱えている企業なら、年間1,500万円から2,500万円が、何も生み出さない在庫のために消えている計算になります。
このコストの内訳は、倉庫の賃料や光熱費といった保管費用だけではありません。在庫に掛ける火災保険などの保険料、在庫を管理・棚卸しするための人件費、そして最も恐ろしいのが、製品のモデルチェンジや劣化による陳腐化・品質劣化損です。特に技術革新の速い業界では、昨日まで価値のあった製品が、今日には価値を失ってしまうことも珍しくありません。
もう一方の側面が、機会損失リスクです。在庫を恐れるあまり、必要最低限しか持たないでいると、急な大口受注やメディアでの紹介による需要の急増に対応できなくなります。これが「欠品」です。欠品は、単にその時の売上を逃すだけではありません。「あの会社はいつも品切れだ」という評判が立てば、顧客は競合他社に流れてしまい、長期的な信頼関係まで失いかねません。
例えば、単価1万円、粗利率30%の商品が100個欠品したとしましょう。この時の直接的な機会損失額は、「100個 × 1万円 × 30% = 30万円」にもなります。これが頻繁に起これば、年間の利益に与えるインパクトは計り知れません。
このように、在庫は「多すぎればキャッシュフローを悪化させ、少なすぎればビジネスチャンスを逃す」という、非常に厄介な性質を持っています。だからこそ、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいて論理的に「最適な量」を導き出し、維持していくアプローチが不可欠なのです。
SAP MMが在庫最適化の鍵を握る理由
「在庫管理の重要性は分かった。でも、なぜその解決策がSAP MMなの?」と思われるかもしれません。その答えは、SAP MMが持つ「データの一元管理」と「豊富な標準機能」にあります。
多くの企業では、販売計画は営業部門、発注は購買部門、在庫管理は倉庫部門、生産計画は製造部門…というように、情報が各部門に分断されがちです。これでは、会社全体として最適な在庫量を把握することは困難です。
しかし、SAP MMは、購買依頼から見積、発注、入庫、請求書照合に至るまでの一連の購買プロセスが一つのシステム上で完結しています。さらに、販売管理(SD)モジュールと連携すれば「いつ、何が、どれだけ売れたか」、生産管理(PP)モジュールと連携すれば「いつ、何を、どれだけ作るか」といった情報もリアルタイムで繋がります。
つまり、SAPの中には、在庫を最適化するために必要なあらゆるデータが、正確かつリアルタイムに蓄積されているのです。この「信頼できる唯一の情報源(Single Source of Truth)」があることこそ、SAP MMが在庫最適化の強力な基盤となる最大の理由です。
さらに、SAP MMには、この蓄積されたデータを活用して在庫最適化を自動化・効率化するための便利な機能が標準で備わっています。後ほど詳しく解説するMRP(資材所要量計画)や消費主導型計画、安全在庫の自動計算といった機能は、まさにその代表例です。これらの機能を使いこなすことで、担当者の経験や勘に依存した属人的な管理から脱却し、誰がやっても一定の精度を保てる、データドリブンな在庫管理体制を構築できるのです。
【実践編】SAP MMで在庫を最適化する5つの具体的ステップ
それでは、いよいよ本題です。SAP MMを使って在庫を最適化するための、具体的で実践的な5つのステップを見ていきましょう。
ステップ1: ABC分析で在庫の「見える化」と優先順位付け
最初に取り組むべきは、現状把握です。数千、数万点にも及ぶ在庫品目をすべて同じように管理しようとすると、手間がかかるばかりで効果は上がりません。そこで有効なのがABC分析です。
ABC分析は、「売上や消費金額の大部分は、ごく一部の品目によって生み出されている」というパレートの法則に基づいた分析手法。在庫品目を重要度に応じてA・B・Cの3つのランクに分類し、管理にメリハリをつけるのが目的です。
- Aランク品目: 全在庫品目のうち上位10〜20%の品目で、売上・消費金額の約70〜80%を占める最重要グループ。
- Bランク品目: 中間の20〜30%の品目で、売上・消費金額の約15〜20%を占める。
- Cランク品目: 残りの大多数(50〜70%)の品目で、売上・消費金額に占める割合はわずか5〜10%程度。
SAPでは、トランザクションコード MC40(消費金額)や MC41(在庫金額)などを実行するだけで、簡単にABC分析ができます。
この分析結果をどう活かすかが重要です。
- Aランク品目に対しては、「絶対に欠品させないが、過剰にも持たない」という方針で、厳密な管理を行います。需要予測の精度を高め、安全在庫レベルを慎重に設定し、発注状況を日々モニタリングするといった重点的なケアが必要です。
- Cランク品目は、管理工数をかけるのがもったいないグループです。多少多めに在庫を持っても金額的なインパクトは小さいため、発注業務の効率化を優先します。例えば、2ビン方式や定期発注方式といった簡易的な管理手法を採用し、発注の手間を極力減らすのが得策です。
- Bランク品目は、AとCの中間の管理を行います。
まずはこのABC分析で自社の在庫の「顔ぶれ」を把握し、どこに注力すべきかを見極めることが、最適化への第一歩となります。
ステップ2: 正確な需要予測に基づいた発注計画
ABC分析で重点管理品目(Aランク品目)が特定できたら、次はその品目が「将来どれくらい必要になるか」を予測します。これが需要予測です。
多くの現場では、担当者の「これくらいだろう」という感覚や、前年同月の実績をそのまま使うといった方法で発注量を決めているケースが見られます。しかし、その方法では市場の急な変化に対応できません。
SAP MMには、過去の消費実績データに基づいて、将来の需要を統計的に予測する「消費主導型MRP」という機能があります。品目マスタのMRPビューで、予測モデル(例えば、移動平均法、加重移動平均法、指数平滑法など)を選択し、過去のどの期間のデータを参照するかを設定するだけで、システムが自動で将来の需要量を計算してくれるのです。
重要なのは、品目の特性に合わせて適切な予測モデルを選択することです。例えば、安定的に消費される品目なら単純な「移動平均法」で十分かもしれませんが、季節性のある商品(夏に売れる清涼飲料水など)であれば「季節モデル」、トレンドに乗って売上が伸びている商品であれば「トレンドモデル」といったように、最適なモデルを選ぶことで予測精度は格段に向上します。
この予測結果を基に購買依頼や購買発注を自動生成することも可能です。これにより、発注漏れや担当者の勘違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した調達を実現できます。
ステップ3: 最適な「安全在庫」の設定と自動計算
需要予測をしても、予測が100%当たることはありませんし、サプライヤーの納期が遅れることもあります。こうした不確実性に対応するために必要なのが「安全在庫」です。
しかし、この安全在庫が曲者で、担当者が「念のため」と多めに設定しがちなため、過剰在庫の温床になることがよくあります。では、最適な安全在庫はどう決めればよいのでしょうか?
これもSAPが解決してくれます。品目マスタのMRP2ビューには、安全在庫を統計的に自動計算する機能があります。ここで重要になるのが「サービスレベル」という考え方です。サービスレベルとは、「顧客からの要求に対して、何%欠品なく対応したいか」という目標値です。例えば、サービスレベルを95%に設定するということは、100回の注文のうち95回は在庫で対応し、5回は欠品を許容するという意味になります。
このサービスレベルと、過去の需要のばらつき(標準偏差)、そして調達にかかるリードタイムのばらつきをSAPに設定すると、システムは統計学的な計算式(例: 安全在庫 = 安全係数 × 需要の標準偏差 × √リードタイム)を用いて、目標のサービスレベルを達成するために必要な、理論的な安全在庫レベルを算出してくれます。
ある電子部品メーカーの事例では、従来は担当者の経験則で「2ヶ月分」と設定していた安全在庫を、この機能を使ってサービスレベル98%を目標に再計算したところ、品目によっては在庫が30%削減され、一方で欠品が頻発していた品目では在庫が増加したそうです。結果として、会社全体の在庫金額を15%削減しながら、欠品率は5%から1%未満に改善し、機会損失の削減によって利益率が向上したといいます。
このように、感情論ではなくデータに基づいて安全在庫を決めることが、在庫最適化の核心部分なのです。
ステップ4: リードタイムの短縮とばらつきの抑制
在庫量に大きな影響を与えるもう一つの要素が、発注してから商品が納入されるまでの期間、すなわち調達リードタイムです。リードタイムが長ければ長いほど、その間の不確実性に備えるための在庫(特に安全在庫)がより多く必要になります。
SAPの品目マスタでは、「購買処理時間(社内処理)」「計画配送時間(サプライヤーの準備・輸送期間)」「入庫処理時間(荷受・検収期間)」といった形で、リードタイムを細かく設定できます。これらの項目に、サプライヤーから提示された標準的な納期をただ入力するだけでは不十分です。
重要なのは、実績データを分析することです。SAPには購買発注日と実際の納入日のデータがすべて蓄積されています。このデータを分析すれば、「サプライヤーAの平均リードタイムは15日だが、実際には10日〜25日とばらつきが大きい」「サプライヤーBは平均18日と少し長いが、必ず17日〜19日の間に納品してくれている」といった実態が見えてきます。
リードタイムのばらつきが大きいサプライヤーは、安全在庫を多く持たなければならず、管理上のリスクとなります。こうしたデータは、サプライヤーとの納期改善交渉を行う際の強力な客観的証拠になります。また、社内の購買処理や入庫処理に時間がかかっていることが分かれば、業務プロセスの見直しにも繋がります。リードタイムを1日でも短縮し、そのばらつきを抑える努力が、着実に在庫削減へと結びついていくのです。
ステップ5: MRP(資材所要量計画)の徹底活用
最後に、これまでのステップの集大成ともいえるのが、MRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画)の活用です。
MRPは、販売計画や独立需要(予測)に基づいて、「いつ、どの品目が、どれだけ必要になるか」を算出し、現在の在庫や発注残を考慮した上で、不足分を「いつ、どれだけ発注・製造すべきか」という調達提案(計画手配や購買依頼)を自動で作成してくれる機能です。
MRPを効果的に動かすためには、品目マータの「MRPタイプ」と「ロットサイズ」の設定が肝になります。
MRPタイプは、その品目をどのように計画するかを決定する重要な区分です。例えば、高価なAランク品目であれば、販売計画に直結させて無駄なく手配する「PD(計画主導型MRP)」を。安価なCランク品目であれば、一定の在庫レベル(発注点)を下回ったら自動で発注する「VB(消費主導型手動発注点方式)」を選ぶ、といった使い分けが考えられます。
ロットサイズは、1回にどれだけの量を発注するかを決めるルールです。例えば、「EX(ロットフォーロット)」にすれば必要な分だけを都度発注するため在庫は最小化できますが、発注頻度が増えて発注コストがかさみます。逆に「FX(固定ロットサイズ)」にすれば発注頻度は減らせますが、必要量以上の手配となり在庫が増える可能性があります。
このように、品目の特性やコスト構造(発注コスト vs 在庫維持コスト)を考慮して、MRPのパラメータを適切に設定し、定期的に実行することで、在庫の自動補充の仕組みが完成します。これにより、担当者は日々の発注業務から解放され、より付加価値の高い業務(サプライヤー交渉や需要予測の精度向上など)に集中できるようになるのです。
在庫最適化を成功させるための組織的なポイント
ここまでSAP MMの機能面を中心に解説してきましたが、ツールを導入するだけでは在庫最適化は成功しません。最後に、組織として取り組むべき重要なポイントを2つお伝えします。
一つ目は、KPI(重要業績評価指標)の設定とモニタリングです。在庫最適化の取り組みがうまくいっているかどうかを客観的に判断するために、「在庫回転日数」「欠品率」「滞留在庫金額」「在庫維持コスト」といった指標をKPIとして設定しましょう。そして、これらのKPIをSAPの標準レポートやBIツールなどでダッシュボード化し、関係者がいつでも進捗を確認できる状態にしておくことが重要です。数値で成果を共有することで、活動のモチベーション維持にも繋がります。
二つ目は、部門間の連携です。在庫は、営業、購買、製造、倉庫、経理といった様々な部門が関わる、まさに「部門の壁」の象徴です。営業部門が持つ最新の需要情報、購買部門が持つサプライヤーの納期情報、製造部門が持つ生産計画の変更情報などがスムーズに共有されなければ、最適な在庫管理は実現できません。定期的に関連部門が集まり、需要と供給の計画をすり合わせるS&OP(Sales and Operations Planning)のような会議体を設けるなど、組織横断で取り組む意識が不可欠です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。SAP MMは、単なる業務トランザクションを記録するだけのシステムではありません。その中に蓄積された膨大なデータを正しく活用することで、企業の長年の課題である在庫問題を解決に導く、非常に強力な武器となり得ます。
今回ご紹介した5つのステップ、
- ABC分析による現状把握と優先順位付け
- 需要予測に基づく計画的な手配
- データに基づいた最適な安全在庫の設定
- リードタイムの分析と改善
- MRPの活用による自動化
これらを一つずつ実践していくことで、あなたの会社の在庫は必ず「最適化」され、キャッシュフローは改善し、より強固な経営体質へと変わっていくはずです。
もちろん、一朝一夕にすべてを実現するのは難しいかもしれません。まずは自社の在庫データをSAPから抽出し、ABC分析を行って、どこに問題が潜んでいるのかを「見える化」することから始めてみませんか? きっと、そこから在庫最適化への確かな道筋が見えてくるはずです。


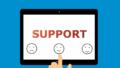

コメント