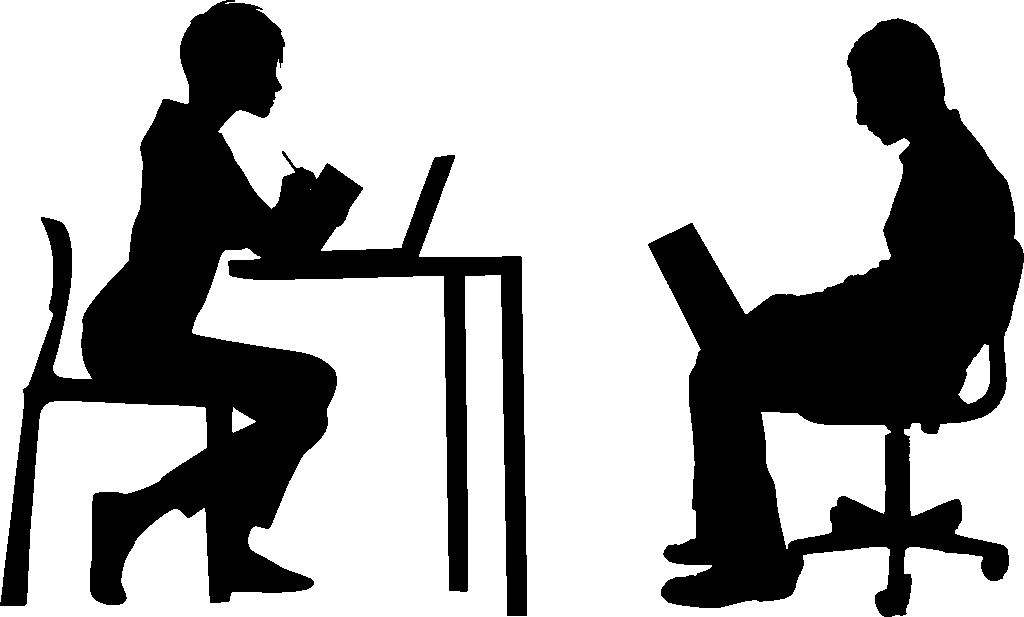
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 毎日、夜遅くまで残業しているのに、なぜか仕事が終わらないと悩んでいる方
- 上司から「もっと本質を考えろ」「なんで?」と繰り返しフィードバックされてしまう若手社員の方
- 目の前の作業に没頭してしまい、気づくと本来の目的を見失ってしまっていることが多い方
- 複雑な問題を前に、どこから手をつければ良いか分からず、思考がフリーズしてしまう方
- コンサルタントのように、シャープで生産性の高い仕事の進め方を学び、自分の市場価値を高めたいと考えている方
あなたの隣の席にいる、いつも定時で颯爽と帰るのに、なぜか常に高い成果を出し、上司からの評価も高いAさん。一方、毎日パソコンの前で必死に手を動かし、夜遅くまで頑張っている自分。アウトプットの質もスピードも、なぜかAさんには及ばない…。この差は、一体どこから来るのでしょうか?
才能や経験の差でしょうか?それも、あるかもしれません。しかし、もっと根本的な違いは、仕事への「向き合い方」、もっと言えば「思考法のOS」そのものにあるのかもしれません。
実は、多くのビジネスパーソンが、一日の大半を「考える仕事」ではなく、指示されたことをこなすだけの「単純作業」に費やしてしまっています。日本の労働生産性がG7(先進7カ国)の中で、長年最下位に甘んじているというデータは、この「考えない働き方」がもたらす、根深い問題を示唆しているのかもしれません。
この記事では、問題解決のプロフェッショナルである「コンサルタント」が、複雑な課題の本質を瞬時に見抜き、最短距離で成果を出すために必ず実践している、ある「魔法の質問」を軸にした思考法を、誰にでも分かりやすく、そして今日から実践できる形で徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの仕事の進め方は劇的に変わり、「作業」から解放され、本質的な「仕事」に集中できるようになるはずです。
あなたは「作業」をしていませんか?仕事の9割を占める”思考の罠”
本題に入る前に、あなたに一つ、問いかけをさせてください。 あなたは今日、本当の意味で「仕事」をしましたか?それとも、ただ「作業」に追われていただけでしょうか?
この二つは、似ているようで全く異なります。
- 作業とは: 指示されたこと、決められた手順を、頭を使わずにこなすこと。(例:データをExcelに転記する、言われた通りに資料を修正する)
- 仕事とは: 「目的」を達成するために、頭を使い、付加価値を生み出すこと。(例:データから傾向を読み取り、改善策を提案する。資料の目的を考え、より伝わる構成を再設計する)
驚くほど多くの人が、この「作業」に忙殺され、一日が終わった時に「今日も頑張った」という疲労感だけで、本質的な価値を生み出せていないという”思考の罠”に陥っています。上司に「このデータ、グラフにしといて」と言われ、ただ言われた通りのグラフを作るのは「作業」です。一方で、「このデータを伝える目的は何か?円グラフより棒グラフの方が、変化率をより効果的に示せるのではないか?」と考えるのが「仕事」です。
この「考える」という一手間を惜しむことで、手戻りが発生したり、的外れなアウトプットになったりして、結果的に何倍もの時間を無駄にしてしまうのです。では、どうすればこの罠から抜け出し、本質的な「仕事」ができるようになるのでしょうか。その答えが、コンサルタントの思考法に隠されています。
コンサルタントが最初に問う「魔法の質問」
コンサルタントは、どんなに複雑で巨大な問題に直面しても、決して思考停止しません。彼らは、カオスのような情報の中から、問題の「本質」をえぐり出すための、強力な思考ツールを持っています。
その核心となるのが、たった2つの「魔法の質問」です。
1. So What?(だから、何?)
2. Why So?(それは、なぜ?)
この2つを、頭の中で絶えず往復させること。これが、コンサルタントの思考法のOSそのものです。
So What?(だから、何?)― 事実から本質的な意味を掘り出す
目の前にある情報やデータ、起きた事象に対して、「だから、何が言えるの?」「このことから導き出せる、本質的な示唆は?」と問いかけるのが「So What?」です。
例えば、上司から「今月のA商品の売上が、前月比で20%ダウンした」という事実を伝えられたとします。 ここで思考が止まってしまうのが「作業者」です。 「そうですか、20%ダウンですね」と事実をオウム返しするだけ。
一方、「仕事人」は考えます。 「(So What?)だから、何?…20%のダウンは、単月のブレなのか、それとも下降トレンドの始まりなのか?」 「(So What?)…競合のB商品が先月リニューアルしたが、その影響か?」 「(So What?)…このままでは、四半期の売上目標達成が危うい、ということを意味するのではないか?」
このように、「So What?」を繰り返すことで、単なる事実の羅列から、行動に繋がる「意味合い」や「課題」を抽出することができるのです。
Why So?(それは、なぜ?)― 表面から根本原因を突き詰める
「So What?」で見えてきた課題や事象に対して、「なぜ、そうなっているの?」「その根本的な原因はどこにあるの?」と、原因を深く、深く掘り下げていくのが「Why So?」です。
有名なのが、トヨタ生産方式で用いられる「なぜなぜ5回分析」です。 先ほどの例で、「競合B商品の影響で、A商品の売上が落ちたのではないか」という仮説が立ったとします。
- なぜ①: なぜ、A商品はB商品に負けたのか? → B商品の新しい広告キャンペーンが、若者層に刺さったから。
- なぜ②: なぜ、B商品の広告は若者に刺さったのか? → 人気のインフルエンサーを起用し、SNSで拡散されたから。
- なぜ③: なぜ、A商品は同様の施策をしなかったのか? → A商品のターゲットは40代以上であり、若者向けSNSは重視していなかったから。
- なぜ④: なぜ、ターゲットを40代以上に設定していたのか? → 長年の顧客データから、それが最も購買力のある層だと判断していたから。
- なぜ⑤: なぜ、その判断を今も見直さないのか? → 市場の変化や若者層の台頭という、新しい現実を直視できていなかったから。
どうでしょうか。「売上が20%落ちた」という表面的な問題が、「自社のマーケティング戦略が、市場の変化に対応できていない」という、より本質的で根深い原因にまで辿り着きました。ここまで掘り下げて初めて、打つべき対策(ターゲットの見直し、新しいプロモーション戦略の立案など)が明確になるのです。
実践!「本質思考」を鍛える3つのトレーニング
「So What? / Why So?」の重要性は分かった。でも、これを日常的に使いこなすのは、なかなか難しいものです。そこで、この「本質思考」の筋力を鍛えるための、具体的な3つのトレーニングをご紹介します。
トレーニング1:ゼロ秒思考 ― 思考の瞬発力を鍛える
コンサルタント出身の赤羽雄二氏のベストセラー『ゼロ秒思考』で紹介されている、非常にシンプルかつ強力なトレーニングです。
やり方は簡単。A4のコピー用紙を横向きに置き、左上にテーマ、右上に日付を書きます。そして、そのテーマについて、1分間で思いつくことを4〜6行、箇条書きで書き出すだけ。これを毎日10枚(10分間)続けます。
テーマは何でも構いません。「なぜ、今日の会議は長引いたのか?」「どうすれば、もっと資料作成が早くなるか?」など、身の回りの疑問や課題でOKです。このトレーニングは、頭の中にあるモヤモヤとした思考を、瞬時に言語化し、整理する「思考の瞬発力」を劇的に高めてくれます。
トレーニング2:ロジックツリー ― 思考を構造化する
複雑な問題を前にした時、どこから手をつければいいか分からなくなるのは、問題の全体像が見えていないからです。ロジックツリーは、大きな問題を小さな要素に分解し、その構造を「見える化」するための思考ツールです。
例えば、「売上を上げるには?」というテーマで考えてみましょう。 売上は「顧客数 × 顧客単価」に分解できます。さらに顧客数は「新規顧客+既存顧客」に、顧客単価は「購買点数 × 商品単価」に分解できます。 このように、問題を樹形図(ツリー)のように分解していくことで、「どの要素に、どんな課題があり、どこから手をつけるべきか」が網羅的に、そして論理的に整理できるのです。
トレーニング3:仮説思考 ― 最短距離でゴールを目指す
これは、コンサルタントの生産性の高さを支える、最も重要な思考法の一つです。 多くの人は、問題に直面すると、まず闇雲に情報収集を始めがちです。しかし、それでは時間がいくらあっても足りません。
仮説思考では、情報収集を始める前に、「現時点での、最も確からしい仮の答え(仮説)」を先に立ててしまいます。例えば、「売上が落ちた原因は、競合のSNSキャンペーンの影響だろう」という仮説を立てるのです。
そして、その仮説が「正しいか、間違っているか」を検証するために、必要な情報だけを集めに行きます。もし仮説が正しければ、そのまま解決策の立案に進めます。もし間違っていたら、すぐに新しい仮説を立て直せばいいのです。この「仮説→検証→修正」のサイクルを高速で回すことで、無駄な調査や分析を一切行わず、最短距離で本質的な答えに辿り着くことができます。
本質を見抜く人は、仕事のすべてが一味違う
こうした「本質思考」が身につくと、会議での振る舞いや、資料の作り方といった、日々の具体的なアウトプットの質も劇的に変わってきます。
- 会議では: 議論が脇道に逸れそうになった時、「そもそも、この会議の目的って何でしたっけ?」と、常に本質的な「目的」に立ち返らせることができるようになります。
- 資料作りでは: いきなりPowerPointを開くことはありません。まず手書きで、「この資料で、誰に、何を伝えて、どう動いてほしいのか」という目的を明確にし、結論から逆算して、相手が最も理解しやすいストーリーを設計します。
「考える」ことをサボらず、常に仕事の「本質」を問い続けること。それは、短期的には少し面倒に感じるかもしれません。しかし、長期的に見れば、無駄な手戻りや的外れな努力からあなたを解放し、何倍もの時間と、そして評価をもたらしてくれる、最強の武器となるのです。
さあ、今日からあなたの口癖を「So What? / Why So?」に変えてみませんか?

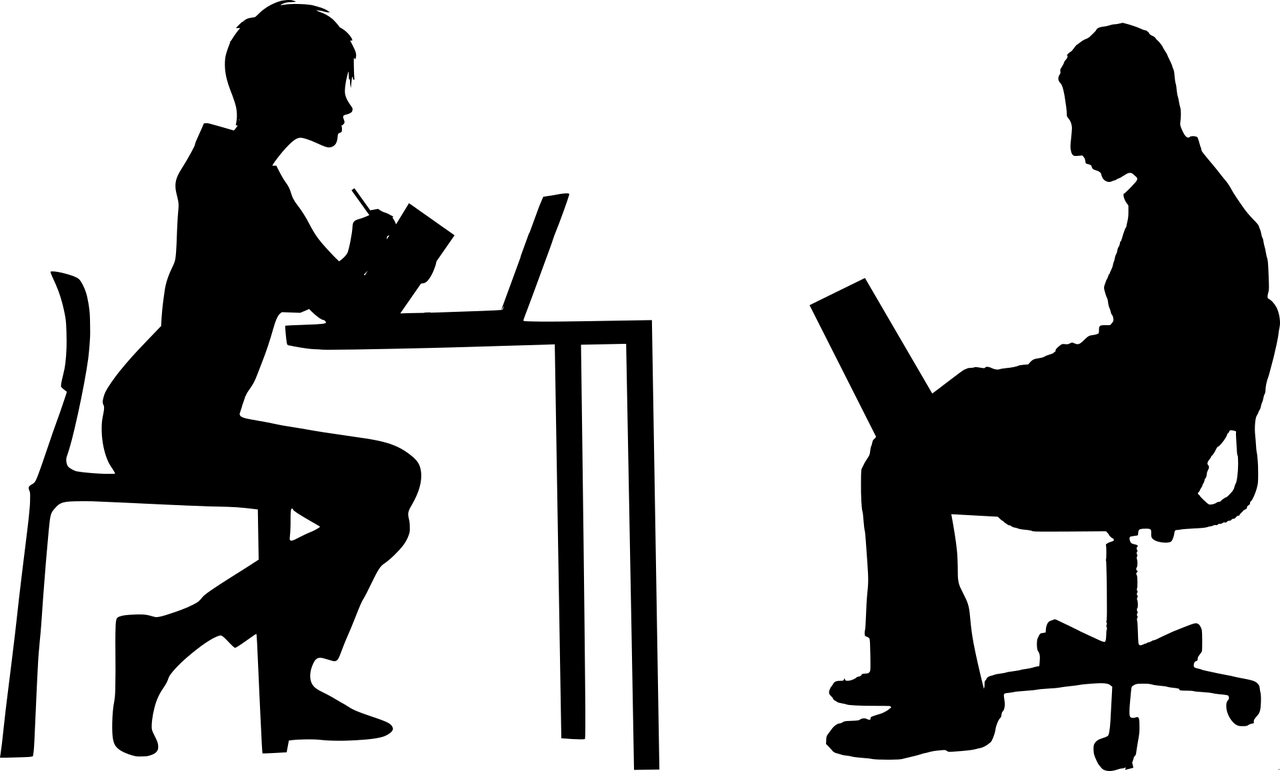
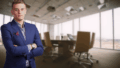

コメント