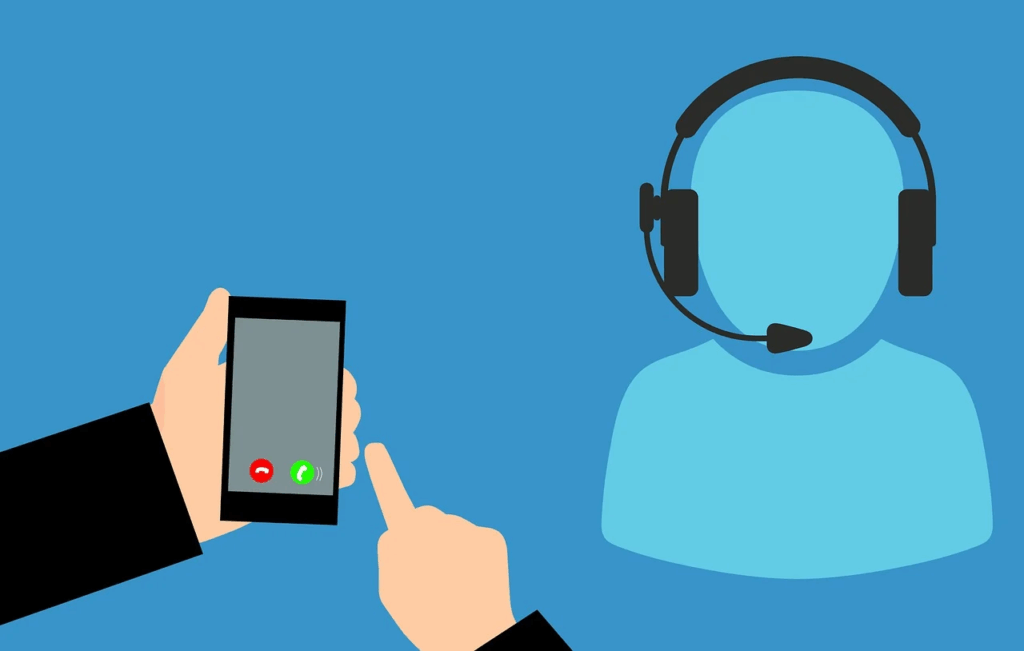
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 何時間もかけて作った資料を、会議で「で、結局何が言いたいの?」と一蹴されてしまった経験がある方
- 自分の資料が、ただ情報を詰め込んだだけの「退屈なデータ集」になっていると感じる方
- 伝えたいことはあるのに、それをどう構成し、どう表現すれば良いか分からず、いつも途中で手が止まってしまう方
- 会議の議事録が、ただの「発言録」になってしまい、ネクストアクションに繋がらないと悩んでいる方
- コンサルタントのように、明快で説得力のある資料をサッと作り上げ、周囲を動かせるようになりたいと考えている方
昨日の夜、何時間もかけて作り上げた渾身の提案資料。しかし、今日の会議で、上司や役員は数ページめくっただけで、退屈そうな顔でこう言いました。「うーん、データは分かったけど、それで、我々は何をすればいいんだっけ?」
この一言で、あなたの努力は水の泡。そんな、悔しくてやるせない経験はありませんか?
ある調査によると、ビジネスパーソンは、勤務時間の約20%を「資料作成」に費やしているというデータがあります。週5日勤務なら、実に丸一日を資料作りに充てている計算です。しかし、その多くの資料が、誰の心にも響かず、誰の行動も変えられずに、静かにファイルサーバーの肥やしになっているとしたら、これは由々しき事態です。
一方で、コンサルタントが作る資料は、なぜか一見シンプルなのに、読み手の心を掴み、議論を活性化させ、スムーズな意思決定を促します。
その違いは、PowerPointのデザインセンスや、グラフの見せ方が美しいから、ではありません。その裏側には、資料を作る「前」の、圧倒的に深い「思考のプロセス」が隠されているのです。
この記事では、見た目だけのテクニックではない、コンサルタントが実践する「人を動かす」ためのドキュメンテーションの本質、その極意を、誰にでも実践できる形で徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたの資料作りは、単なる「作業」から、相手を動かす「戦略的コミュニケーション」へと変わるはずです。
その資料、「キレイなゴミ」になっていませんか?
ドキュメンテーションの議論になると、多くの人が「どうすれば、もっと見栄えの良い資料が作れるか?」という、デザインの話に終始しがちです。確かに、デザインは重要です。しかし、それは本質ではありません。
コンサルタントの世界では、どんなに美しいグラフや洗練されたテンプレートを使っても、中身のない資料は「Beautiful Garbage(キレイなゴミ)」と呼ばれ、全く評価されません。
なぜなら、コンサルタントにとってのドキュメントとは、単なる「報告書」や「情報のまとめ」ではないからです。それは、「読み手の意思決定を促し、具体的な行動を引き出すための、戦略的なツール」なのです。
この目的意識の違いこそが、凡庸な資料と、人を動かす資料とを分ける、最初の、そして最大の分岐点です。
ペンを持つな、まず紙に書け。コンサルが「書く」より「考える」に8割の時間を費やす理由
人を動かす資料を作るための、最も重要な極意。それは、「いきなりPowerPointやWordを開かない」ということです。
コンサルタントは、資料作成に10時間かかるとしたら、そのうちの8時間を、パソコンに触らない「考える時間」に費やします。そして、残りの2時間で、一気に書き上げるのです。多くの人が、いきなり書き始めてしまい、途中で構成に悩み、何度も手戻りを繰り返すのとは、全く逆のアプローチです。
では、その「8割の時間」で、彼らは何を考えているのでしょうか。 それは、たった3つの問いに、完璧に答えるための思考プロセスです。
- この資料の「読み手」は、誰か? (社長向けなのか?現場の担当者向けなのか?それによって、使う言葉も、情報の詳しさも、すべてが変わる)
- 読み手に「何を理解してほしい」のか? (この資料を通じて、相手の頭の中に残したい、たった一つの核心的なメッセージは何か?)
- そして、読み終わった後、「どう動いてほしい」のか? (承認してほしいのか?予算を確保してほしいのか?次のアクションに進んでほしいのか?具体的なゴールは何か?)
この3つの問い、いわば「ドキュメントの設計図」を、A4の紙一枚に書き出すことから、すべてのドキュメンテーションは始まります。この設計図なしに資料を作り始めるのは、地図もコンパスも持たずに、航海に出るようなもの。遭難するのは、目に見えています。
なぜ、あなたの話は最後まで聞いてもらえないのか?「ピラミッド原則」という最強の武器
設計図が完成したら、次はいよいよ「構成」を考えます。ここで、コンサルタントが必ず使う、最強の思考ツールが登場します。それが「ピラミッド原則」です。
これは、コンサルティングファームのマッキンゼーで開発された、世界中のビジネスパーソンの標準スキルとも言える考え方で、一言でいえば「結論から話せ(書け)」ということです。
多くの人が、自分が考えたプロセスを時系列に沿って、一生懸命に説明しようとします。 「まず、現状調査としてAを行い、次にBという分析をしました。その結果、Cという事実が判明し、Dという課題が見えてきました。そこで、解決策としてEを提案します…」 これでは、毎日何十もの意思決定に追われる多忙な役員は、途中で「で、結論は何なんだ?」とイライラし始めるでしょう。
ピラミッド原則では、構成を完全に逆転させます。
- 頂点(Main Message): まず、資料全体で伝えたい「最も重要な結論・提案」を、最初にズバリと提示する。
- 中段(Key Line): 次に、その結論を支える「主要な根拠や理由」を、3つ程度のグループに分けて簡潔に述べる。
- 土台(Support): 最後に、それぞれの根拠を裏付ける「具体的なデータや事実」を提示する。
【ピラミッド構造のイメージ】
結論: 来期、A事業に1億円の追加投資をすべきです。
根拠①: 市場が年率20%で急成長しているため。
根拠②: 競合他社が、まだ本格参入していないため。
根拠③: 当社の技術的優位性が、最も活かせるため。
データ/事実: (市場調査レポートのデータ)
データ/事実: (競合各社の動向分析)
データ/事実: (自社の特許や技術評価)
この構造であれば、読み手は、最初の数秒で話の全体像と最も重要なポイントを理解できます。そして、興味を持った部分や、疑問に感じた部分だけを、深く掘り下げて読んでいけば良いのです。これは、読み手の貴重な時間を奪わないという、最高の「配慮」でもあります。
神は細部に宿る。資料の解像度を劇的に上げる「1スライド・1メッセージ」の鉄則
全体の構成がピラミッド構造で固まったら、いよいよ個別のスライド作成に入ります。ここでも、コンサルタントが徹底する、シンプルな鉄則があります。 それが「1スライド・1メッセージ」の原則です。
これは、「一つのスライドで伝えたいことは、必ず一つに絞る」というルールです。
よくある失敗例: 一枚のスライドに、売上推移の棒グラフ、顧客満足度の円グラフ、地域別の売上シェアの表を詰め込み、スライドのタイトルは「各種データまとめ」となっている。 これでは、読み手は何を見ればいいのか、そして、このスライドから何を受け取ればいいのか、全く分かりません。
コンサル流の改善例: 上記の失敗例は、3枚のスライドに分割します。
- スライド1枚目:
- タイトル(メッセージ): A事業の売上は、過去3年間で年率15%の安定成長を遂げている
- ボディ(根拠): 売上推移の棒グラフ
- スライド2枚目:
- タイトル(メッセージ): 高い顧客満足度が、安定したリピート購入を支えている
- ボディ(根拠): 顧客満足度調査の円グラフ
- スライド3枚目:
- タイトル(メッセージ): 特に、首都圏エリアでの売上構成比が、全体の7割を占めている
- ボディ(根拠): 地域別の売上シェアの表
このように、各スライドの「タイトル」部分に、そのスライドで言いたい「結論(メッセージ)」を、必ず文章で書きます。そして、スライドの中身(グラフや表)は、そのメッセージを裏付けるための「証拠」という位置づけになります。
このルールを徹底するだけで、あなたの資料は、一つひとつの主張が明確で、論理の流れが非常に分かりやすい、プロフェッショナルなものへと生まれ変わります。
資料作りは、「思考のトレーニング」である
ここまで、コンサル流のドキュメンテーションの極意をお話ししてきました。
- 書く前に、目的(誰に、何を、どうしてほしいか)を考え抜く
- 構成は、結論から話す「ピラミッド原則」で
- 各スライドは、「1スライド・1メッセージ」を徹底する
これらの根底に流れているのは、「徹底した読み手視点」です。
資料作りは、自分が言いたいことを書き連ねる「自己満足の作業」ではありません。それは、読み手という「他者」の頭の中を想像し、どうすれば最も効率的に、そして最も効果的にメッセージを届けられるかを設計する、「思考のトレーニング」であり、「コミュニケーションのデザイン」なのです。
この思考法が身につけば、あなたの作る資料は、もはや「キレイなゴミ」ではなく、人を動かし、ビジネスを前に進めるための、強力な「武器」となります。そして、そのスキルは、どんな職種、どんな業界でも通用する、あなたの市場価値を大きく高める、一生モノの財産となるでしょう。
さあ、今日から、あなたのドキュメンテーションに「人を動かす魔法」をかけてみませんか。




コメント