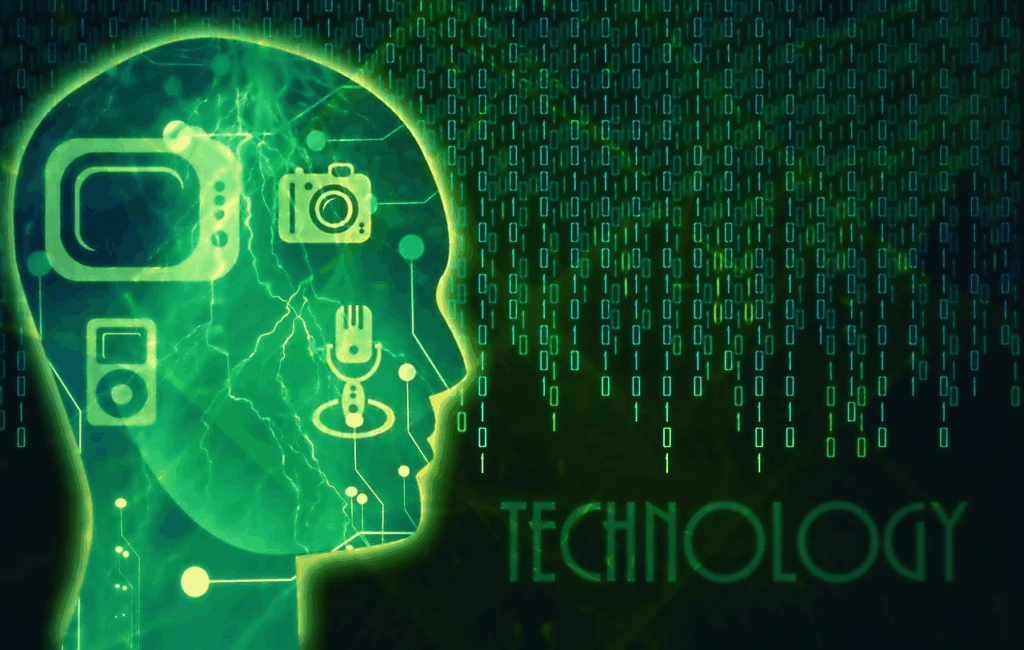
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 「フェルミ推定」という言葉を聞いたことがあるが、何のことかよく分かっていない方
- コンサルティング業界の思考法に興味があり、自分の仕事にも活かしたい方
- 論理的思考力や問題解決能力を、座学だけでなく実践的に鍛えたい方
- 情報が少ない状況でも、的確な判断ができるようになりたい方
- いわゆる「地頭が良い人」になりたいと本気で思っている方
「日本全国にある電柱の数は?」 「世界中で1日に消費されるピザの枚数は?」
こんな、一見すると答えようのない質問をされたら、あなたはどうしますか? 「分かるわけないよ…」と、すぐに諦めてしまうかもしれません。
しかし、コンサルティングファームの面接や研修では、このような「正解がすぐには分からない問題」を使って、候補者の思考力を測ることがあります。この思考トレーニングこそが、今回ご紹介する「フェルミ推定」です。
フェルミ推定は、単なる知識を問うクイズではありません。それは、手元にある情報と論理的な推論を武器に、未知の数値を「だいたいこれくらいだろう」と概算する、最強の思考ツールなのです。
この記事では、「フェルミ推定って何?」という基本から、コンサルタントが実践する具体的な解き方の4ステップ、そして、このトレーニングで得られる思考力が、いかにあなたの日常業務やキャリアを豊かにするかまでを、どこよりも分かりやすく徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたはどんな難問にも怯むことなく、自分の頭で考え抜く楽しさと、そのための強力な「思考の武器」を手に入れているはずです。
そもそも「フェルミ推定」って、一体なに?
まずは、フェルミ推定の正体から探っていきましょう。 フェルミ推定とは、一言で言うと、「実際に調査するのが難しい、あるいは不可能な数値を、自分が持っている知識や常識を元に、論理的な仮説を積み重ねて、短時間で概算する方法」のことです。
この名前は、ノーベル物理学賞を受賞した物理学者エンリコ・フェルミに由来します。彼は、世界初の原子爆弾実験の際に、爆風で紙片がどのくらい動いたかを見ただけで、爆発のエネルギー量を驚くほど正確に算出した、という逸話を持っています。まさに、限られた情報から答えを導き出す達人でした。
ここで絶対に押さえておきたい、最も重要なポイントがあります。 それは、フェルミ推定の目的は「正解の数値をピッタリ当てること」ではない、ということです。
面接官や上司が見ているのは、その数値そのものではなく、「その数値を導き出すまでの思考プロセス」です。
- 未知の問題を、どのように分解(構造化)しているか?
- それぞれの要素に、どんな根拠を持って仮説(数値)を置いているか?
- その思考プロセスを、相手に分かりやすく説明できるか?
これらの点を通して、あなたの論理的思考力、仮説構築力、そしてコミュニケーション能力を総合的に評価しているのです。だから、完璧な答えが出なくても、全く気にする必要はありません。大切なのは、粘り強く考え抜く姿勢と、その過程の美しさなのです。
なぜ今、ビジネスでフェルミ推定が重要なのか?
「就活のテクニックでしょ?」と思うかもしれませんが、それは大きな誤解です。フェルミ推定で鍛えられる思考力は、現代のビジネスパーソンにとって必須のサバイバルスキルと言っても過言ではありません。
理由1:情報が不完全な状況での「意思決定力」が求められるから
現代は、先行きが不透明で変化の激しい「VUCAの時代」です。ビジネスの現場では、「全てのデータが揃うのを待っていたら、競合に先を越されてしまう」という場面が日常茶飯事。
例えば、あなたが新規事業の担当者になったとしましょう。「この新しいサービスの市場規模は、一体どれくらいだろう?」という問いに対して、完璧な市場調査データはどこにも存在しません。 こんな時こそ、フェルミ推定の出番です。 限られた情報から、「ターゲット層は〇〇万人で、そのうち△△%が利用する可能性があるから、市場規模はおそらく□□億円くらいだろう」と「当たりをつける(仮説を立てる)」ことができれば、GOかNOか、次のアクションを迅速に判断できます。
この「仮説構築力」こそが、ビジネスのスピードと成功確率を大きく左右するのです。
理由2:複雑な問題を「構造化」する力が身につくから
「売上を10%アップさせろ」 もし、上司からこんな指示を受けたら、あなたは何から始めますか?
思考が整理できていないと、「とにかく頑張ります!」と精神論に走ってしまいがちです。 しかし、フェルミ推定のトレーニングを積んでいると、この漠然とした課題を自然と分解(構造化)できるようになります。
「売上」=「客数」×「客単価」 ↓ 「客数」=「新規顧客」+「既存顧客」 「客単価」=「商品単価」×「買い上げ点数」
このように問題を分解すれば、「まず新規顧客を増やすために、Web広告を強化しよう」「既存顧客の買い上げ点数を増やすために、セット割引を提案しよう」といった、具体的で実行可能なアクションプランが見えてきます。
フェルミ推定は、この問題解決の根幹となる「構造化思考」を、実践形式で鍛える最高のドリルなのです。
【完全ガイド】フェルミ推定の解き方4ステップ
お待たせしました。ここからは、具体的な例題を使って、フェルミ推定の解き方をステップバイステップで見ていきましょう。一緒に考えながら読み進めてみてください。
【例題】日本全国にある美容室の店舗数は?
ステップ1:前提確認・アプローチ設定
まず、いきなり計算を始めるのではなく、問題の定義を明確にします。 「『美容室』の定義は何ですか?理容室(床屋さん)は含みますか?」「個人経営の小さな店舗も、大手チェーンも全て含みますか?」といった質問を、心の中(あるいは実際に)投げかけます。この「前提を疑い、定義を確認する姿勢」が非常に重要です。
今回は、「理容室は含まず、美容師が施術を行う店舗すべて」と定義しましょう。
次に、どういう切り口で答えを導き出すか、アプローチを決めます。
- 需要側アプローチ:国民がどれくらい美容室を必要としているか(需要)から考える。
- 供給側アプローチ:美容師の数や、1店舗あたりのスタッフ数(供給)から考える。
- インフラアプローチ:面積あたりに何軒あるか、などから考える。
どの方法でも構いませんが、今回は最も考えやすい「需要側アプローチ」で進めてみましょう。
ステップ2:式の構造化(分解)
次に、ゴールとなる「美容室の店舗数」を、計算可能な要素へと分解していきます。
美容室の店舗数 = (日本全体の年間美容室市場規模) ÷ (美容室1店舗あたりの年間売上)
この式だけでは、まだ計算できませんね。さらに分解します。
A. 日本全体の年間美容室市場規模 = (日本の人口) × (美容室に行く人の割合) × (一人当たりの年間利用回数) × (一回当たりの利用金額)
B. 美容室1店舗あたりの年間売上 = (1店舗あたりのスタッフ数) × (スタッフ1人あたりの年間売上)
ここまで分解できれば、あとは各要素に具体的な数値を当てはめていくだけです。
ステップ3:数値の代入(仮説の設定)
ここがフェルミ推定の腕の見せ所。自分の知識や肌感覚を総動員して、仮説の数値を置いていきます。
【A. 市場規模の計算】
- 日本の人口:約1億2,500万人(総務省統計局の公表データ。これは知っていると便利)
- 美容室に行く人の割合:乳幼児や一部の高齢者などを除き、ざっくり80%と仮定。
- 年間利用回数:女性は2ヶ月に1回(年6回)、男性は3ヶ月に1回(年4回)と仮定。男女比は約1:1なので、平均して年5回と置く。
- 一回当たり利用金額:カット、カラー、トリートメントなど含め、平均6,000円と仮定。
→ A = 1億2,500万人 × 0.8 × 5回 × 6,000円 = 3兆円
【B. 1店舗あたり売上の計算】
- 1店舗あたりのスタッフ数:平均3人と仮定。
- スタッフ1人あたりの年間売上:月50万円くらい?少し多めに見積もって、年間700万円と仮定。
→ B = 3人 × 700万円 = 2,100万円
重要なのは、なぜその数字にしたのか、必ず自分なりの根拠を持つことです。「女性の方が利用回数が多いので…」「駅前の店舗はもっと売上が高いだろうけど、平均すると…」といった思考のプロセスが評価されます。
ステップ4:計算・結論
最後に、ステップ2で立てた式に、ステップ3で置いた数値を代入して計算します。
美容室の店舗数 = 3兆円 ÷ 2,100万円 ≒ 約14万3,000店
「日本の美容室は、およそ14万店くらいではないか」という結論が出ました。
ちなみに、厚生労働省の「令和4年度衛生行政報告例」によると、実際の美容所の施設数は約27万施設です。私たちの推定値とは差がありますが、桁数が大きく外れているわけではありません。この差異について「1店舗あたりの売上をもっと低く見積もるべきだったかもしれない」「個人経営の小規模店舗が想定より多いのかもしれない」などと考察できれば、さらに評価は高まります。
仕事で使える!フェルミ推定で鍛えられる3つの思考力
この思考トレーニングを続けると、日常の仕事で驚くほど役立つ3つの力が身につきます。
1. 仮説思考力
情報が不完全な中でも「たぶんこうだろう」と仮説を立て、仕事の当たりをつけられるようになります。これにより、無駄な調査や手戻りが減り、仕事のスピードが劇的に向上します。
2. 構造化思考力
複雑で漠然とした課題を、具体的な要素に分解して考える癖がつきます。「どうすればいいか分からない…」と悩む時間が減り、常に具体的な打ち手を考えられるようになります。
3. 数値化力
「すごく良いです」「たくさん売れてます」といった曖昧な表現ではなく、「〇〇という理由で、約△△%の改善が見込めます」のように、物事を定量的に語れるようになります。あなたの報告や提案は、圧倒的な説得力を持つことになるでしょう。
まとめ:正解のない時代の「思考のコンパス」を手に入れよう
今回は、コンサル流の思考法「フェルミ推定」について、その本質から具体的な実践方法までを解説してきました。
- フェルミ推定は、答えを当てるクイズではなく、論理的な思考プロセスを鍛えるトレーニングである。
- 「前提確認 → 構造化 → 仮説設定 → 計算」という4ステップは、あらゆる問題解決に応用できる。
- このトレーニングを通じて、仮説思考力、構造化思考力、数値化力という、現代ビジネスに不可欠な力が身につく。
最初は難しく感じるかもしれませんが、心配はいりません。大切なのは、日頃から「これはフェルミ推定で考えたらどうなるだろう?」と、知的なゲームとして楽しむ姿勢です。 街を歩きながら「このカフェの1日の売上は?」「日本にいるカラスの数は?」と考えてみる。その小さな思考の筋トレが、あなたの地頭を確実に鍛え上げます。
正解が一つではないこの時代に、自分の頭で考え抜き、納得のいく答えを導き出す力は、あなたにとって最も信頼できる「思考のコンパス」になるはずです。


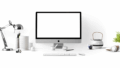
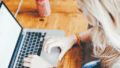
コメント