
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 「ロジカルシンキング」と「論理的思考力」、二つの言葉の違いが気になっている方
- ビジネス書や研修でこれらの言葉を聞くが、どう使い分ければいいか分からない方
- 言葉の定義に惑わされず、思考法の「本質」をしっかりと理解したい方
- 仕事で使う思考法について、他の人より一歩進んだ知識を身につけたい方
- 「結局、どっちを鍛えればいいの?」という疑問に、スッキリした答えが欲しい方
「ロジカルシンキングを身につけよう!」「君には論理的思考力が足りない」。 ビジネスシーンで当たり前のように使われる、この2つの言葉。 なんだか似ているけれど、一体何が違うんだろう?もしかして、全くの別物…? そんな風に、頭の中に「?」が浮かんだことはありませんか。
結論から先にお伝えします。 「ロジカルシンキング」と「論理的思考力」は、ほぼ同じ意味で使われている言葉です。
「え、じゃあこの記事はここで終わり?」 いえいえ、話はここからが本番です。 ほぼ同じ意味なのに、なぜ2つの言葉が存在するのでしょうか。実は、その背景や使われ方には、知っておくと非常に面白い、微妙なニュアンスの違いが隠されています。
この記事では、「ロジカルシンキング」と「論理的思考力」の言葉の迷路からあなたを救い出します。二つの言葉の根本的な関係性から、言葉の背景、そして「結局、私たちは何を意識すればいいのか?」という実践的なゴールまで、どこよりも分かりやすく、そして深く掘り下げて解説していきます。
この記事を読み終える頃には、言葉の表面的な違いに惑わされることなく、思考法そのものの「本質」を掴み、明日からの仕事に活かせる本物の理解を手に入れているはずです。
【大結論】ロジカルシンキングと論理的思考力は「ほぼ同じ意味」
改めて、この記事の最も重要な結論から始めましょう。 ロジカルシンキング(Logical Thinking)は英語、論理的思考力はその日本語訳であり、指し示している概念は基本的に同じです。
どちらも、中核となる意味は「物事を体系的に整理し、矛盾なく筋道を立てて考える力(または、その考え方)」を指します。 ですから、日常会話やビジネスシーンにおいて、「彼のロジカルシンキングは素晴らしい」と言っても、「彼の論理的思考力は素晴らしい」と言っても、意味は全く問題なく通じますし、どちらを使っても間違いではありません。
実際に、多くのビジネス書やオンライン記事でも、この2つの言葉はほぼ同義として扱われています。 検索エンジンで「ロジカルシンキングとは」と調べても、「論理的思考力とは」と調べても、出てくる解説のほとんどが同じ内容(例えば、演繹法や帰納法、MECE、ロジックツリーなど)であることからも、両者が同じものを指していることが分かります。
では、なぜわざわざ別の言葉のように扱われることがあるのでしょうか。 その答えは、言葉が日本で広まっていった「背景」と、言葉が持つ「ニュアンス」に隠されています。この違いを知ることで、思考法への理解がぐっと深まります。
なぜ2つの言葉が存在する?知っておきたい言葉の背景
同じ意味なのに、なぜ2つの言葉が使われるのか。それは、それぞれの言葉が日本で注目を浴びた「ルーツ」が異なるからです。
背景1:コンサル発祥の「スキル」としてのロジカルシンキング
「ロジカルシンキング」という言葉がビジネスシーンで広く使われるようになったのは、1990年代後半から2000年代にかけて。その火付け役となったのが、マッキンゼー・アンド・カンパニーをはじめとする外資系のコンサルティングファームでした。
彼らは、複雑な経営課題を解決するための「思考の技術(スキル)」として、ロジカルシンキングを体系化し、社内のトレーニングに取り入れました。 その際に、課題を分解して整理するための「ロジックツリー」や、漏れなくダブりなく物事を捉える「MECE(ミーシー)」といった、具体的な「フレームワーク(思考の型)」とセットで広まったのが大きな特徴です。
そのため、「ロジカルシンキング」という言葉には、
- 後天的に習得できる「技術」「スキル」
- 問題解決のための具体的な「方法論」「ツール」 といったニュアンスが色濃く含まれています。いわば、ビジネスの現場で即戦力となる「実践的な思考術」というイメージです。
背景2:学問の世界における「能力」としての論理的思考力
一方で、「論理的思考力」という日本語は、もっと古くから存在し、哲学や心理学、教育学といった学問の世界で使われてきた言葉です。
こちらは、アリストテレスの時代から続く「論理学」の流れを汲み、人間が物事を正しく考えるための、より根源的で普遍的な「知的能力(アビリティ)」として捉えられています。 特定のフレームワークというよりは、「演繹法」や「帰納法」といった、思考の根本的な原理原則に焦点が当てられることが多いです。
そのため、「論理的思考力」という言葉には、
- 人間が元来持っている、または育むべき「能力」「地力」
- 物事の道理を考える、より普遍的な「知性」 といった、少しお固い学術的なニュアンスが含まれています。いわば、「人間としての考える力そのもの」というイメージです。
この違いを料理に例えるなら、ロジカルシンキングが「美味しいカルボナーラを作るための具体的なレシピや調理テクニック」だとすれば、論理的思考力は「火加減の調整や味覚といった、料理全般に必要な基礎的な腕前」と表現できるかもしれません。美味しいカルボナーラを作るには、両方が必要ですよね。
結局、私たちはどちらを意識すればいいのか?
言葉の背景やニュアンスの違いは分かった。では、これから思考法を学んだり、実践したりする上で、私たちはどちらの言葉を意識すれば良いのでしょうか。
ここでの結論は、非常にシンプルです。 言葉の違いにこだわる必要は一切ありません。本当に重要なのは「思考の本質」を理解し、実践することです。
言葉の定義で議論したり、どちらが正しいかで悩んだりするのは、いわば「どのメーカーの包丁が優れているか」で延々と悩んで、肝心の料理を始めないようなもの。時間の無駄ですし、本来の目的を見失ってしまいます。
私たちが目指すべきゴールは、言葉を覚えることではなく、その思考法を使って、
- 目の前の問題を解決する
- 自分の考えを分かりやすく相手に伝える
- より良い意思決定をする ことのはずです。
そのために必要な「思考の本質」は、次の3つの要素に集約できます。
- 分解する:複雑で大きな問題を、シンプルで扱いやすい小さなパーツに分ける力。(MECEやロジックツリーが役立つ)
- 筋道を立てる:分けたパーツ間の関係性(特に原因と結果)を明らかにし、矛盾のないストーリーを組み立てる力。(演繹法や帰納法が役立つ)
- 伝える:組み立てたストーリーを、相手が理解しやすいように、結論から分かりやすく表現する力。(PREP法などが役立つ)
この3つの本質を実践する上で、「ロジカルシンキング」という言葉が持つ「スキル」や「フレームワーク」の側面は、非常に強力な武器になります。 そして、その武器を使いこなすための土台となるのが、「論理的思考力」という言葉が持つ「基礎能力」としての側面です。
つまり、両者は対立するものではなく、「論理的思考力という土台の上に、ロジカルシンキングという技術を習得する」という補完関係にあると捉えるのが、最も実践的で分かりやすい理解と言えるでしょう。
「論理」だけでは不十分?これからの時代に求められる思考法
さて、ロジカルシンキング(論理的思考力)の重要性について話してきましたが、最後に少しだけ視座を上げて、これからの時代に本当に活躍するための「思考法の全体像」について触れておきます。
実は、ロジカルシンキングだけでは、現代の複雑なビジネス課題には対応しきれない、と言われています。なぜなら、ロジカルシンキングはあくまで「既にある情報を整理し、深掘りする」のは得意ですが、「新しいアイデアを生み出す」ことや、「そもそもその前提は正しいのかと疑う」ことは苦手だからです。
そこで、ロジカルシンキングと合わせて身につけたいのが、以下の2つの思考法です。
1. クリティカルシンキング(批判的思考)
これは、「本当にそうなの?」「なぜそう言えるの?」と、物事の前提を健全に疑う思考法です。ロジカルに組み立てられた話でも、「そもそも、そのデータは信頼できる?」「その論理の出発点、間違ってない?」と、思考の「質」を検証する役割を果たします。フェイクニュースや偏った情報に惑わされないためにも必須のスキルです。
2. ラテラルシンキング(水平思考)
これは、既存の枠組みや常識にとらわれず、物事を全く違う角度から見て、新しいアイデアを生み出す思考法です。「なぜ?なぜ?」と深掘りするロジカルシンキング(垂直思考)に対し、ラテラルシンキングは「他に方法はないか?」と自由に発想を広げていきます。イノベーションの源泉となる思考法です。
世界経済フォーラムが発表した「仕事の未来レポート2023」では、今後重要性が増すスキルとして、「分析的思考(Analytical thinking)」が1位、「創造的思考(Creative thinking)」が2位にランクインしています。
これはまさに、ロジカルシンキング(分析的思考)を土台としながらも、ラテラルシンキング(創造的思考)やクリティカルシンキングを組み合わせて使う能力が、これからの時代に不可欠であることを示しています。
- ラテラルシンキングでアイデアを広げ、
- ロジカルシンキングでアイデアを整理・構築し、
- クリティカルシンキングでその質を検証する。
この3つを使いこなせてこそ、真の「思考の達人」と言えるでしょう。
まとめ:言葉の迷いを乗り越え、思考の達人へ
今回は、「ロジカルシンキングと論理的思考力の違い」という、多くの人が一度は疑問に思うテーマを深掘りしてきました。
- 結論として、両者は「ほぼ同じ意味」である。
- ただし、ロジカルシンキングは「コンサル発祥の実践スキル」、論理的思考力は「学問的な基礎能力」という背景とニュアンスの違いがある。
- 言葉の違いにこだわるより、「分解・筋道・伝達」という思考の本質を実践することが何よりも重要。
- さらに、ロジカルシンキングを土台に、クリティカルシンキングやラテラルシンキングを組み合わせることで、思考力は次のステージへ進化する。
もう、あなたは2つの言葉の違いに悩む必要はありません。この二つは、あなたの思考を助けてくれる強力なパートナーです。 まずは言葉の迷いから解放され、思考法を「使う」という本来の目的に意識を向けてみてください。その先に、仕事や人生における、よりクリアでパワフルな未来が待っているはずです。


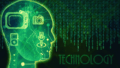

コメント