
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- エンジニアとの打ち合わせで、専門用語が飛び交い、話についていけず愛想笑いをしてしまう方
- 営業や企画の仕事で、IT部門に何かを依頼する際に、うまく要望を伝えられずにもどかしい思いをしている方
- ある日突然「DX推進担当」に任命されたけど、そもそもITの基本が分からなくて途方に暮れている方
- ニュースで見る「クラウド」や「API」といった言葉の意味が、なんとなくしか分からずモヤモヤしている方
- これから社会に出る上で、職種に関係なく役立つ「ITの教養」を身につけておきたい学生の方
「サーバーサイドでAPIを叩いて、DBからJSON形式でデータを取得し、フロントに渡しますね」
エンジニアとの会議中、こんな言葉が飛び交い、頭が真っ白に…。話の内容が理解できないまま、ただただ時間が過ぎていくのを待った経験はありませんか?
営業、企画、マーケティング、人事、経理…どんな職種であれ、ITと全く無関係でいられるビジネスパーソンは、もはや存在しない時代になりました。
ITの基礎知識がないと、エンジニアとの意思疎通がうまくいかず、仕事が非効率になる。そればかりか、あなたの素晴らしいアイデアが形にならなかったり、大きなビジネスチャンスを逃してしまったりすることさえあります。
かといって、分厚い専門書を片っ端から読んだり、プログラミングスクールに通ったりする時間も気力もない…。
そんなあなたのための「IT入門の決定版」が、この記事です。
今回は、非エンジニアがこれだけは絶対に押さえておくべきITの基礎知識を10個に厳選。専門用語を、誰もが知っている「身近なもの」に例えながら、世界一分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、エンジニアとの会話が驚くほどスムーズになり、仕事の解像度が格段に上がることをお約束します。
なぜ、すべてのビジネスパーソンにIT知識が必要なのか?
「ITのことは、専門家であるエンジニアに任せておけばいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、その考え方は、もはや通用しない時代になっています。
その最大の理由が、国を挙げて推進されている「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。 DXとは、単にITツールを導入することではありません。デジタル技術を使って、ビジネスのやり方そのものを根本から変革していく取り組みです。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書2023」によると、日本企業の約7割がDXに取り組んでいますが、その成果が出ている企業はまだ半数程度。そして、DX推進の課題として多くの企業が挙げているのが、「IT人材の不足」と並んで、「社員のITリテラシー不足」なのです。
これは何を意味するのでしょうか? それは、DXの本当の主役は、エンジニアだけではないということです。現場の課題を一番よく知っている営業担当者や、顧客のニーズを深く理解しているマーケターといった、非エンジニアの皆さんこそが、「この業務を効率化するために、どんなITツールが使えるだろう?」「このIT技術を使えば、新しいサービスが作れるかもしれない」と考える、重要な役割を担っているのです。
そのためには、ITを「よく分からない魔法」として恐れるのではなく、「便利な道具」として正しく理解し、エンジニアと「共通言語」で話せるようになることが、今、すべてのビジネスパーソンに求められています。
これだけは押さえよう!IT基礎知識10選【超・たとえ話つき】
それでは早速、本題に入りましょう。ここでは、ITの世界の全体像を掴むために不可欠な10個のキーワードを、分かりやすいたとえ話と共に解説していきます。
1. ハードウェア/ソフトウェア
- ひと言でいうと:パソコンの「体」と「脳みそ」。
- たとえるなら: ハードウェアは、スマートフォン本体や、パソコンのディスプレイ、キーボード、マウスといった、目に見えて、手で触れる「物理的なモノ」のことです。まさに人間でいう「体」や「骨格」にあたります。 一方、ソフトウェアは、そのハードウェアの上で動く、LINEやInstagramといったアプリやプログラムのこと。目には見えません。人間でいう「知識」や「思考」といった「脳みそ」の働きです。どんなに高性能な体(ハードウェア)も、賢い脳みそ(ソフトウェア)がなければ、ただの箱になってしまいます。
2. OS (オペレーティングシステム)
- ひと言でいうと:ハードとソフトを操る、偉大な「指揮者」。
- たとえるなら: 皆さんが普段使っている、Windows、macOS、あるいはスマホのiOS、Android。これがOSです。OSは、ハードウェアとソフトウェアの間に立って、両者がうまく連携できるように交通整理をしてくれる、オーケストラの「指揮者」のような存在です。私たちがマウスを動かすと(ハードウェアの操作)、画面上のカーソルが動く(ソフトウェアの反応)。この当たり前を、裏で支えているのがOSなのです。
3. IPアドレス/ドメイン
- ひと言でいうと:インターネット上の「住所」と「表札」。
- たとえるなら: インターネットに繋がっている全ての機器には、「192.168.1.1」のような数字の羅列でできた、重複しない住所が割り振られています。これがIPアドレスです。まさに「東京都〇区△△町1-2-3」といった現実世界の「住所」です。 しかし、数字の住所は覚えにくいですよね。そこで、「https://www.google.com/search?q=google.com」や「yahoo.co.jp」といった、人間が覚えやすい文字列の「名前」を付けます。これがドメインで、いわば「〇〇商事ビル」という「表札」にあたるのです。
4. サーバー/クライアント
- ひと言でいうと:サービスを提供する「お店」と、利用する「お客様」。
- たとえるなら: この関係は、レストランに例えると非常に分かりやすいです。 私たちがスマホ(クライアント)でYouTubeを見るとき、それはレストランの客席に座った「お客様」のようなものです。「この動画が見たい」と注文すると、厨房にいるシェフが料理を作って提供してくれますよね。この、注文に応じてサービス(データや機能)を提供してくれる巨大なコンピューターのことをサーバーと呼びます。
5. クラウド (IaaS/PaaS/SaaS)
- ひと言でいうと:ITシステムを「所有」から「レンタル」へ。
- たとえるなら: 昔は、自社でサーバー(お店の厨房)を持つのが当たり前でした。しかし、今はそれをインターネット経由で「レンタル」できる時代です。これがクラウドです。クラウドには、主に3段階のレンタル形態があります。
- SaaS(サース):家具・家電付きの賃貸マンション。GmailやSlackなど、契約すればすぐに使える完成品のソフトウェア。
- PaaS(パース):注文住宅用の土地と基礎工事。アプリを開発するための土台(OSやデータベース)だけが用意されている。どんな家を建てるかは自由。
- IaaS(イアース):更地の土地。サーバーやネットワークといったインフラだけを借りる。最も自由度が高い。
6. データベース (DB)
- ひと言でいうと:整理整頓された巨大な「デジタル図書館」。
- たとえるなら: AmazonのようなECサイトには、膨大な顧客情報、商品情報、購入履歴などが保管されています。これらのデータを、後から簡単に見つけたり、使ったりできるように、きちんと整理整頓して保管しておく場所がデータベースです。まるで、ジャンルごと、著者ごとに本が綺麗に並べられた「図書館」の書庫のようなイメージです。
7. API (Application Programming Interface)
- ひと言でいうと:サービス同士を便利につなぐ「連携の窓口」。
- たとえるなら: APIは、現代のWebサービスを支える超重要人物です。 例えば、あなたが使っている家計簿アプリが、銀行のサイトにログインしなくても自動で入出金データを取得してくれるとします。これは、家計簿アプリが、銀行が用意したAPIという「専用の連携窓口」を通して、「〇〇さんの最新の取引データをください」とお願いしているからです。APIがあるおかげで、異なるサービス同士が、安全かつ便利に機能を連携させることができるのです。まさに、サービスとサービスをつなぐ「コンセント」のようなものです。
8. フロントエンド/バックエンド
- ひと言でいうと:レストランの「客席」と「厨房」。
- たとえるなら: Webサイトやアプリは、大きく2つの部分に分かれています。 フロントエンドは、ユーザーの目に直接触れる部分。つまり、サイトのデザイン、文字のレイアウト、ボタンの配置など、レストランの「客席」の内装やメニュー表にあたります。 一方、バックエンドは、ユーザーの目には見えない裏側の仕組み。注文データをデータベースに保存したり、在庫を確認したり、クレジットカード決済を処理したりといった、レストランの「厨房」の仕事です。
9. セキュリティ (SSL/TLS)
- ひと言でいうと:通信内容を暗号化する「鍵付きの封筒」。
- たとえるなら: Webサイトで個人情報やクレジットカード番号を入力するとき、その情報が誰かに盗み見られたら大変ですよね。そこで、通信データを暗号化して、第三者には読み取れないようにする技術がSSL/TLSです。 見分け方は簡単。URLが「http://」ではなく「https://」で始まり、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されていれば、この技術で保護されています。それはまるで、大切な手紙を「鍵付きの封筒」に入れて送るようなもので、安心して情報をやり取りできる証なのです。
10. プログラミング言語
- ひと言でいうと:コンピューターに指示を出すための「外国語」。
- たとえるなら: コンピューターは、私たちが話す日本語を直接理解できません。そこで、コンピューターが理解できる専用の「言葉」を使って、やってほしいことを命令する必要があります。これがプログラミング言語です。 人間が話す言葉に英語やフランス語があるように、プログラミング言語にも、作りたいものによって様々な種類があります。Webサイトの見た目を作るならHTML/CSS/JavaScript、AIやデータ分析が得意なのはPython、スマホアプリならSwift(iPhone)やKotlin(Android)といった具合です。非エンジニアは、これらの言語を話せる必要はありません。ただ、「作りたいものによって、話すべき言語が違うんだな」と知っておくだけで、エンジニアとの会話の解像度がぐっと上がります。
知識を武器に変える!明日からできる2つのアクション
これらの知識を、ただの豆知識で終わらせてはもったいないです。明日から、ぜひこの2つのアクションを試してみてください。
アクション1:エンジニアとの会話で、こっそり「翻訳」してみる
次回のエンジニアとの打ち合わせで、「この機能を追加したいんです」とだけ伝えるのではなく、覚えたての言葉を使ってみましょう。 「この画面(フロントエンド)にボタンを追加して、それを押したら、〇〇のデータベースから商品情報を取ってきて表示する、みたいなイメージですか?」 このように、自分の要望をIT用語に「翻訳」して伝えるだけで、エンジニアは「お、この人は分かっているな」と感じ、より具体的で建設的な議論ができるようになります。
アクション2:ITニュースを「自分ごと」として読んでみる
これまで読み飛ばしていたかもしれない、IT系のニュース記事に目を通してみましょう。「〇〇社が新しいSaaSをリリース」というニュースを見たら、「うちの会社のあの業務課題を解決できるかも?」と考えてみる。「大規模なAPI連携を発表」というニュースなら、「どんなサービス同士が繋がって、私たちの生活が便利になるんだろう?」と想像してみる。この「自分ごと化」の積み重ねが、知識を血肉に変え、あなたのビジネスの視野を大きく広げてくれます。
まとめ:ITは「魔法」じゃない。最高の「ビジネスツール」だ
今回ご紹介した10個のIT基礎知識は、広大で深遠なITの世界の、ほんの入り口に過ぎません。しかし、この入り口を知っているかどうかで、見える景色は全く違ってきます。
ITの基礎知識は、エンジニアと対等に話すためだけの処世術ではありません。それは、自分自身の仕事の可能性を広げ、新しいアイデアを生み出し、これからの時代を生き抜くための、必須の「教養」です。
ITを、一部の専門家だけが操るブラックボックスな「魔法」として恐れるのではなく、誰もが使える最高の「ビジネスツール」として使いこなす側に回りましょう。
その第一歩として、この記事が、あなたの知的好奇心を刺激し、新しい世界への扉を開くきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。


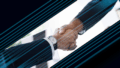

コメント