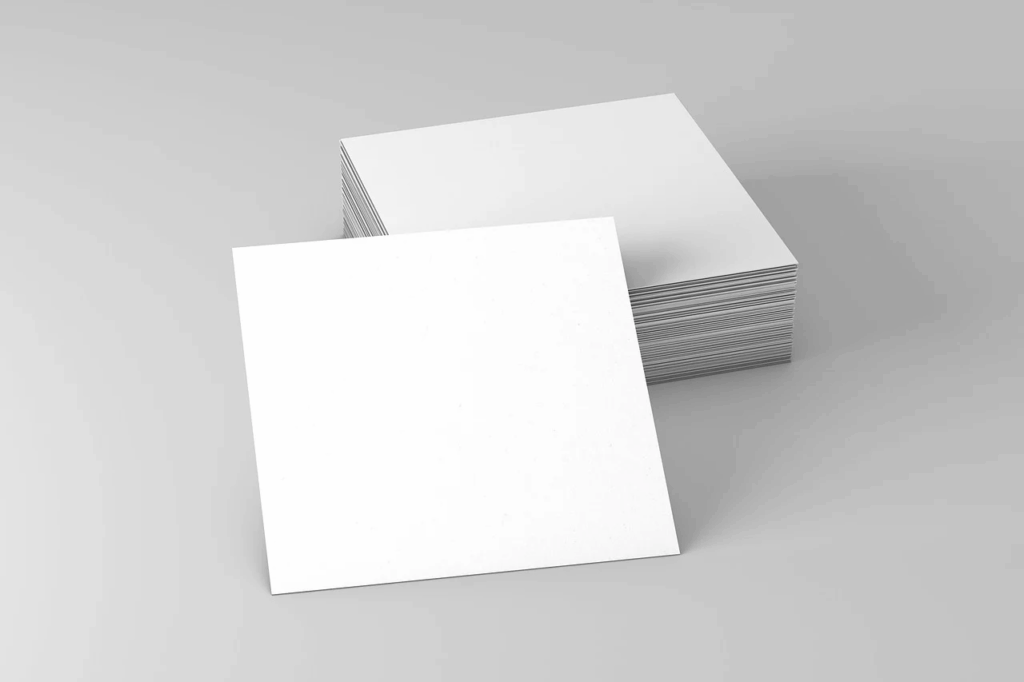
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 高い求人広告費を払い続けているのに、一向に応募が増えなくて悩んでいる方
- 会社の知名度が低く、採用市場で大手企業に相手にされないと感じている方
- SNS採用に挑戦したいけど、「うちにはアピールできるようなキラキラしたネタがない…」と諦めている方
- 給与や待遇だけでなく、会社の「価値観」や「社風」に共感してくれる人材だけを集めたい方
- 採用担当が自分一人だけ、あるいは兼任で、とにかく時間がない中小企業の経営者・担当者の方
「多額の広告費を投じて、やっと採用できたのに、数ヶ月で辞めてしまった…」 「うちみたいな知名度のない会社には、どうせ優秀な人材は来てくれない…」
そんな風に、採用活動に疲れ果て、諦めの気持ちを抱いてはいないでしょうか。高い広告費、鳴らない電話、そしてミスマッチによる早期離職という負のスパイラル。
しかし、もし、そのすべてを解決する方法があるとしたら?
実は今、求人広告に1円も払わず、SNSという無料のツールだけを使って、自社の「ファン」を増やし、優秀な人材から「ぜひ、あなたの会社で働きたい」と次々に応募を集めている企業が、業種や規模を問わず増えています。
その秘密兵器こそが「SNS採用ブランディング」。これは、スペックを並べて「広告」するのではなく、会社の「物語」を語って「共感」で人を集める、まったく新しい時代の採用戦略です。
この記事では、ホームセンター、ビールメーカー、福祉ベンチャーという、一見すると採用とは無縁そうな3社が、いかにしてSNSでファンを作り、採用コストを劇的に削減したのか。その魔法のような、しかし誰にでも真似できるリアルな成功の軌跡を徹底解剖します。
「広告」はもう見られない。求職者が本当に見たいのは“会社の体温”
そもそも、なぜ従来の求人広告は効かなくなってきているのでしょうか。 それは、今の求職者、特にZ世代と呼ばれる若者たちが、企業からの一方的な「広告」を信用しなくなっているからです。
ある調査では、Z世代の約半数が「企業の広告よりも、インフルエンサーや一般の人のレビューを参考にする」と回答しています。彼らは、綺麗に整えられた公式ホームページの言葉よりも、SNS上にある、ちょっと不格好でも、リアルで正直な「生の声」に価値を感じるのです。
これは採用活動においても全く同じ。給与や福利厚生といった「スペック情報」も大事ですが、それ以上に彼らが知りたいのは、「どんな人たちが、どんな想いで、どんな表情で働いているのか」という、目には見えない“会社の体温”です。
そして、この「会社の体温」を、最もリアルに、かつコストをかけずに伝えられるツールこそが、SNSに他なりません。SNSは、会社の規模や知名度に関係なく、その「人柄」や「魅力」で勝負できる、中小企業にとって最高のステージなのです。
あなたの会社はどのタイプ?SNS採用ブランadinaディング3つの型
「そうは言っても、うちにはどんな発信ができるんだろう…」。そう悩む方のために、SNS採用ブランディングの成功パターンを、大きく3つの「型」に分類しました。自社がどの型を目指せそうか、考えながら読み進めてみてください。
- キャラクター型 社長や人事担当者など、「中の人」のユニークな個性や人間味を前面に出してファンを作るスタイル。親近感や「この人と働きたい」という気持ちを醸成します。
- ファン化型 自社の商品やサービスのファンを、会社のファン、そして「未来の仲間」へと昇華させるスタイル。BtoC企業や、熱狂的な顧客を持つ企業に特に有効です。
- ミッション共感型 会社のビジョンや社会的な存在意義(ミッション)を熱く語り、その「志」に共感する人を集めるスタイル。社会貢献性の高い事業や、強い哲学を持つ企業に向いています。
それでは、この3つの型それぞれで、見事な成功を収めた企業の事例を見ていきましょう。
【型別】SNS採用ブランディング・衝撃の成功事例3選
【キャラクター型】株式会社カインズ:ゆるい「中の人」が、会社の“スキ”を作る
- どんな会社?:全国に展開する、言わずと知れた大手ホームセンター。
- どんな発信?:カインズの公式X(旧Twitter)アカウント(@cainz_official)は、大企業らしからぬ、非常に「ゆるい」投稿で有名です。新商品の宣伝もしますが、それ以上に多いのが、広報担当者である「中の人」の個人的なつぶやきや、フォロワーとの気さくなやりとり。「#企業公式が毎朝地元の天気を言い合う」といったユニークなハッシュタグにも積極的に参加し、他の企業アカウントとも親しく交流しています。
- なぜ成功した?:巨大企業であるカインズが、あえて完璧ではない「人間らしさ」や「親近感」を前面に出したこと。これにより、顧客や求職者との心理的な距離が一気に縮まり、「カインズさん、面白いな」「中の人、頑張れ!」といった応援の声が集まるようになりました。これは、単なる広報活動を超え、会社の「愛されるキャラクター」を作り上げることに成功した好例です。
- 驚きの成果:採用面接で「いつもTwitter見てます!中の人のファンです」と語る学生が急増。採用目的のガチガチな発信をしなくても、自然と会社のファンになった候補者が集まるという理想的な状態を生み出しています。企業としての好感度が上がることで、採用だけでなく、売上にも良い影響を与えていることは言うまでもありません。
【ファン化型】株式会社ヤッホーブルーイング:「好き」を仕事に。熱狂的ファンを採用する仕組み
- どんな会社?:「よなよなエール」などのクラフトビールで、熱狂的なファンを持つビールメーカー。
- どんな発信?:彼らの手法は、単なるSNS投稿に留まりません。「よなよなエールの宴」という大規模なファンイベントをリアルで開催し、ファンとスタッフが一緒になって楽しむ場を創出。Facebookや公式Webメディア「よなよなの里」では、ビールの開発秘話だけでなく、スタッフ一人ひとりのビールへの想いや、ユニークな働き方、会社の哲学などを、物語として深く発信しています。
- なぜ成功した?:単に「美味しいビール」を売るだけでなく、その裏側にある「作り手の物語」や「会社のカルチャー」を共有することで、商品のファンを、会社のファン、そして「作り手側に回りたい」と願う未来の仲間へと巧みに育て上げているのです。好きという気持ちが、共感、そして仲間意識へと昇華していく見事な設計です。
- 驚きの成果:採用応募者の大半が、もともと自社製品の熱狂的なファン。そのため、企業の価値観や文化への理解が非常に深く、カルチャーフィットは抜群。入社後のエンゲージメントや定着率が極めて高いことは、想像に難くありません。まさに、採用コストをかけることなく、最高のマッチングを実現しているのです。
【ミッション共感型】株式会社ヘラルボニー:「志」で、異才を惹きつける
- どんな会社?:「異彩を、放て。」をミッションに、知的障害のあるアーティストと契約し、その作品を様々なプロダクトやサービスに展開する福祉実験ユニット。
- どんな発信?:SNSやメディアを通じて、所属アーティストの才能や作品の圧倒的な魅力を発信するのはもちろんのこと、代表の松田兄弟が、なぜこの事業を始めたのか、どんな社会を実現したいのかという「会社の存在意義(ミッション)」を、自らの言葉で、熱く、繰り返し語り続けています。
- なぜ成功した?:自社の利益を語るのではなく、「社会をどう変えたいか」という大きなビジョンを掲げることで、その志に強く共感する人々を惹きつけています。「お金のため」ではなく「社会のため」に働きたい、という価値観を持つ優秀な人材が、業界や職種の垣根を越えて、ヘラルボニーの扉を叩くのです。
- 驚きの成果:広告費ゼロにもかかわらず、大手広告代理店や外資系コンサルティングファーム、有名IT企業など、第一線で活躍していた優秀な人材が「この船に乗りたい」と次々に転職。従来の採用手法では決して出会えなかったであろう「異才」たちが、会社のミッションの下に集結しています。
9割の企業が失敗する「SNS採用」の落とし穴と、成功への5つのステップ
成功事例を見ると、「よし、うちもやろう!」と意気込みたくなりますが、見切り発車は禁物。実は、多くの企業が陥りがちな「失敗の落とし穴」があります。そうならないための「成功への5つのステップ」と合わせて見ていきましょう。
よくある落とし穴
- 落とし穴1:目的なく始めてしまう「とりあえず投稿」病 「流行っているから」という理由だけで始め、何を伝えたいのかが不明確。結果、誰にも響かない自己満足な投稿を続けてしまう。
- 落とし穴2:宣伝ばかりの「売り込み」アカウント 「新商品!」「募集中!」といった宣伝ばかりで、見ている側がうんざり。すぐにフォローを外されてしまう。
- 落とし穴3:担当者任せの「孤独な戦い」と「三日坊主」 担当者一人に丸投げし、社内は無関心。ネタも尽き、プレッシャーに耐えきれず、いつの間にか更新が止まってしまう。
成功への5つのステップ
- Step1:発信の「軸」を決める 始める前に、「うちの会社は、誰に、どんな価値を届けたいのか?」という発信の軸を決めましょう。先ほどの3つの型(キャラクター、ファン化、ミッション)を参考に、「うちは社長の面白さを軸にしよう」「商品のこだわりを語ろう」と決めるだけで、投稿内容に一貫性が出ます。
- Step2:担当者に「自由」と「裁量」を与える SNSの投稿は、会社の「人柄」そのもの。「この言葉遣いはダメ」「投稿前に必ず上長の承認を」といった細かいルールで縛ると、面白い投稿は生まれません。担当者を信じ、ある程度の自由と裁量を与えることが、活きた発信の秘訣です。
- Step3:小さく、低コストで始める 立派なカメラも、動画編集ソフトも、最初は必要ありません。今の時代、スマートフォン一つあれば、十分に質の高いコンテンツが作れます。大切なのは、お金をかけることではなく、知恵と情熱を注ぐことです。
- Step4:社内を全力で巻き込む SNS担当者は、孤独です。だからこそ、経営陣や他の社員が積極的に協力しましょう。「今日のランチ、写真撮っていい?」「面白いネタない?」と声をかけたり、担当者の投稿に「いいね!」やコメントをしたりする。この小さな協力が、担当者のモチベーションを支え、発信の幅を広げます。
- Step5:反応してくれたすべての人に「ありがとう」を伝える コメントやDMをくれた人は、あなたに関心を持ってくれた「未来のファン候補」。一つひとつの反応に、できる限り丁寧に対応しましょう。この地道な「対話」の積み重ねこそが、SNS時代の信頼関係を築く王道です。
まとめ:採用活動を、「コスト」から「最高の資産形成」へ
SNS採用ブランディングは、単なるコスト削減のためのテクニックではありません。
自社の価値観や魅力を発信するプロセスは、未来の仲間だけでなく、未来の顧客をも惹きつけます。そして何より、自分たちの仕事の意義を再確認し、社内に誇りを醸成する、最高の「組織開発」の機会にもなるのです。
それは、お金を払って人を集める「コスト」としての採用活動ではなく、会社の魅力を高め、ファンを増やしていく「資産形成」としての活動と言えるでしょう。
広告費を払って「人」というリソースを買う時代は、終わりを告げました。これからは、自社の「物語」を語り、その物語に共感する「人」を惹きつける時代です。
あなたの会社には、どんな物語がありますか? その物語を、今日から世界に発信してみませんか?

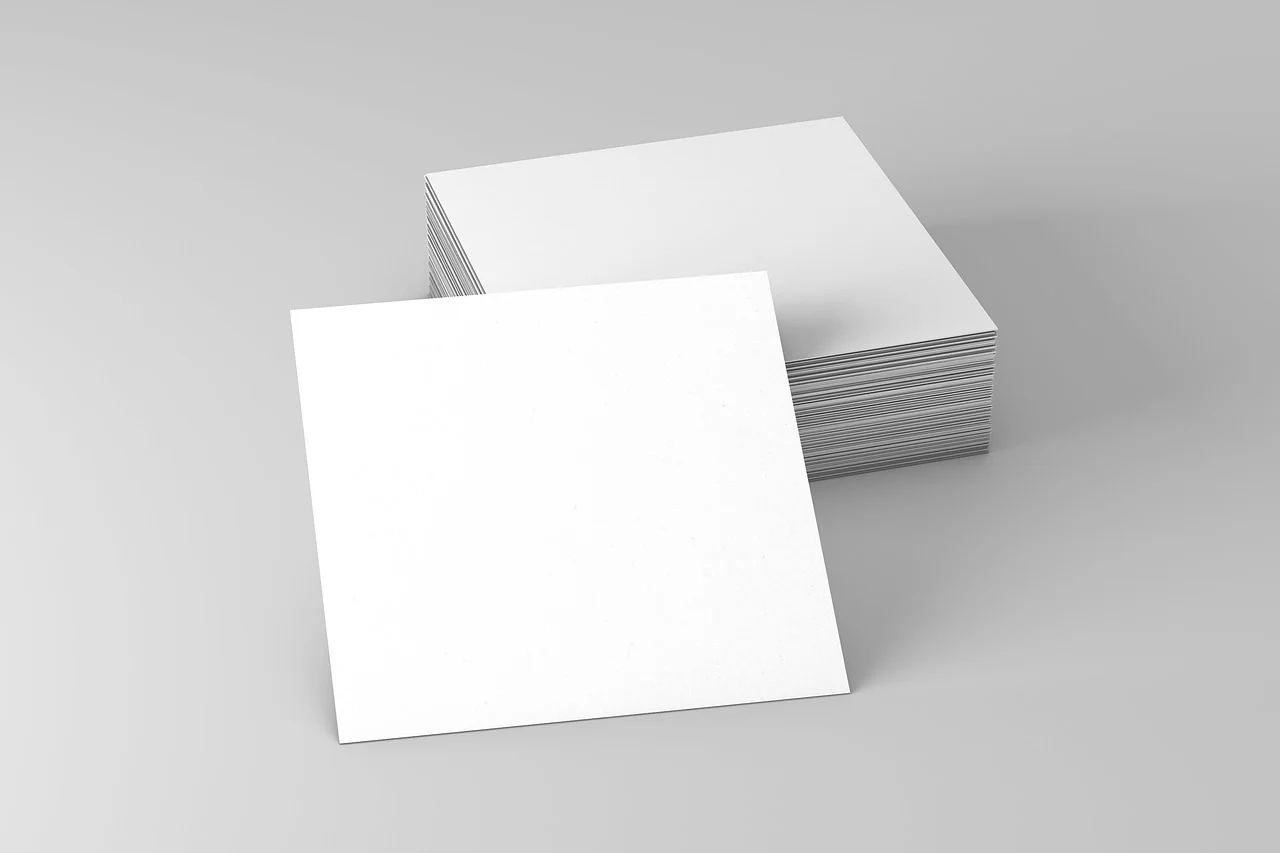
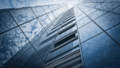

コメント