
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- ロジカルシンキングと論理的思考力の違いが、いまいちピンときていない方
- 仕事で「もっと論理的に考えて」と言われ、どうすればいいか悩んでいる方
- 思考力を鍛えて、仕事の成果や生産性を上げたいと思っている方
- 複雑な問題をスッキリ解決できる、クリアな頭脳を手に入れたい方
- 自分の考えを分かりやすく伝えられるようになりたい方
「ロジカルシンキングを学びましょう」「これからは論理的思考力が不可欠だ」。ビジネスシーンで、こんな言葉を耳にしない日はないですよね。でも、この二つの言葉、正直なところ「何がどう違うの?」と思っていませんか。似ているようで、実は全くの別物。この違いを理解しないままでは、せっかく思考法を学んでも、宝の持ち腐れになってしまうかもしれません。
この記事では、「ロジカルシンキング」と「論理的思考力」の決定的な違いから、それぞれの役割、そして本当に使える思考力を手に入れるための具体的なトレーニング方法まで、思考の専門家が誰にでも分かるように、かみ砕いて解説していきます。
この記事を読み終える頃には、頭の中のモヤモヤが晴れ、明日から何をすべきかが明確になっているはず。あなたの仕事のパフォーマンスを劇的に変える「思考の地図」を手に入れましょう。
結論:ロジカルシンキングは「技術」、論理的思考力は「土台となる能力」
いきなり結論からお伝えしますね。
ロジカルシンキングは、物事を整理整頓するための「技術」や「フレームワーク(型)」のことです。 一方で、論理的思考力は、その技術を使いこなすための「土台となる総合的な能力」、いわば「思考の地力」です。
料理に例えると、とても分かりやすいですよ。
ロジカルシンキングが「美味しいチャーハンの作り方」というレシピや、「包丁の正しい使い方」という技術だとします。レシピ通りにやれば、誰でもある程度のチャーハンは作れますよね。
それに対して論理的思考力は、冷蔵庫にある余り物を見て「これで美味しい料理を作ろう」とひらめいたり、火加減や味付けを絶妙に調整したりする「料理人としての腕前」そのものです。
どんなに素晴らしいレシピ(ロジカルシンキング)を持っていても、料理の腕前(論理的思考力)がなければ、最高の味を引き出すことはできません。逆に、料理の腕前があれば、レシピがなくても美味しい料理を生み出せます。
つまり、論理的思考力という土台があってこそ、ロジカルシンキングという技術が最大限に活かされる、という関係性なんです。この二つは、車の両輪のようなものなんですね。
そもそも「ロジカルシンキング」って何?具体的な手法をサクッと解説
では、まず「技術」であるロジカルシンキングについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
ロジカルシンキングとは、「物事を体系的に整理し、筋道を立てて矛盾なく考えるための思考のフレームワーク(型)」のこと。ごちゃごちゃになった頭の中を、スッキリ整理整頓するための「道具箱」のようなイメージです。
この道具箱には、便利なツールがたくさん入っています。特に有名なものをいくつかご紹介しますね。
MECE(ミーシー):漏れなく、ダブりなく
MECEは “Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive” の略で、「互いに重複せず、全体として漏れがない」状態を指します。物事を分解して考えるときの、基本中の基本となる考え方です。
例えば、顧客層を分析するときに「男性、女性、子供」と分けると、「子供」は性別ではないので分類の軸がずれていますし、「大人」が漏れていますよね。
MECEを使って「20代未満、20代、30代、40代以上」と年齢で区切ったり、「男性、女性」と性別で区切ったりすれば、漏れもダブりもなく全体を把握できます。これにより、問題の所在を正確に突き止められるようになるんです。
ロジックツリー:問題を分解して原因を探る
ロジックツリーは、一つの大きな問題を木の枝のように分解していくことで、原因や解決策を見つけ出すフレームワークです。
例えば、「売上が下がっている」という大きな問題を、
- 「客数」と「客単価」に分解
- さらに「客数」を「新規顧客」と「リピート顧客」に分解
- 「客単価」を「商品単価」と「買い上げ点数」に分解
このように細かくしていくと、「リピート顧客の買い上げ点数が減っているのが、一番の原因かもしれない」といった具体的な課題が見えてきます。漠然とした悩みを、具体的なアクションプランに落とし込むための強力なツールです。
So What? / Why So?:だから何?それはなぜ?
これは、思考を深掘りするための問いかけです。
- So What?(だから何?):目の前の事実から、どんな結論が言えるのか、どんな意味があるのかを考える問い。
- Why So?(それはなぜ?):その結論に至った根拠は何か、なぜそう言えるのかを考える問い。
この二つを繰り返すことで、表面的な事象に惑わされず、物事の本質に迫ることができます。「なんとなく」で話を進めるのではなく、一つひとつに根拠を持たせ、説得力のある主張を組み立てられるようになります。
このように、ロジカルシンキングは「考え方の手順や型を学ぶことで、誰でも一定レベルの結論を導き出せるようにする」ための、非常に実践的な技術なんです。
じゃあ「論理的思考力」ってどんな力?
ロジカルシンキングが後天的に学ぶ「技術」だとしたら、論理的思考力とは何なのでしょうか。
論理的思考力とは、「物事の因果関係を正しく理解し、筋道立てて考え、最適な結論を導き出すための『総合的な思考能力』」です。ロジカルシンキングのフレームワークを使う、もっと手前の段階にある、根源的な力と言えます。
いわゆる「地頭がいい」と言われる人が持っている力に近いかもしれません。この力は、いくつかの要素から成り立っています。
- 分析力:複雑な物事を、その構成要素に分解して理解する力。何と何が、どう関係しているのかを見抜きます。
- 洞察力:物事の表面的な部分だけでなく、その裏にある本質や隠れた前提を見抜く力。「そもそも、この問題設定は正しいのか?」と考える力も含まれます。
- 統合力:分解して得た情報や、一見バラバラに見える複数の情報を、意味のある形に繋ぎ合わせ、新しい結論や仮説を生み出す力。
- 言語化能力:頭の中で考えた筋道を、誰もが理解できるように言葉にして説明する力。
ロジカルシンキングのフレームワークは、これらの能力を補助してくれるツールではありますが、最終的に質の高い結論を導けるかどうかは、この「論理的思考力」の高さにかかっているんです。
例えば、同じロジックツリーを使っても、論理的思考力が高い人は、問題の分解の仕方が的確だったり、見つけ出した原因の本質を見抜いたりすることができます。結果として、より効果的な解決策にたどり着くことができるのです。
【データで見る】なぜ今、論理的思考力が必要とされるのか?
「思考力が大事なのは分かったけど、本当にそんなに重要なの?」と思うかもしれません。ですが、データを見るとその重要性は明らかです。
経済産業省が2018年に発表した「社会人基礎力」の中では、「考え抜く力(シンキング)」が3つの能力の柱の一つとして挙げられています。この中には、課題発見力や計画力といった、まさに論理的思考力が問われるスキルが含まれています。
また、リクルートマネジメントソリューションズの調査(2023年)によると、企業が若手社員に「今後強化したい能力」として挙げた項目の中で、「論理的思考力」は常にトップクラスに位置しています。
なぜ、これほどまでに論理的思考力が求められるのでしょうか?
その最大の理由は、ビジネス環境の変化にあります。現代は、VUCA(ブーカ)の時代、つまり、先行きが不透明で、複雑で、曖昧な時代です。過去の成功体験やマニュアルが通用しない場面が格段に増えました。
このような時代には、前例のない問題に対して、自分自身の頭で本質を見抜き、筋道を立てて解決策を考え、周囲を説得しながら実行していく力が不可欠です。
さらに、AI(人工知能)の台頭も大きな要因です。単純な情報収集やデータ整理は、AIが得意とするところ。これからの人間に求められるのは、AIが弾き出したデータを元に「だから何が言えるのか?」「次に何をすべきか?」を考え、新たな価値を創造していくことです。これこそ、論理的思考力の真骨頂と言えるでしょう。
実際に、世界経済フォーラムの「仕事の未来レポート2023」では、今後重要性が増すスキルとして、「分析的思考」「創造的思考」が1位と2位を独占しています。論理的思考力は、もはや一部のコンサルタントや企画職だけのものではなく、すべてのビジネスパーソンにとって必須のサバイバルスキルとなっているのです。
あなたはどっち?ロジカルシンキングと論理的思考力の違いが一目でわかる比較表
ここまで解説してきた内容を、一度すっきり整理してみましょう。この表を見れば、二つの違いが一目瞭然です。
| 項目 | ロジカルシンキング | 論理的思考力 |
| 位置づけ | 思考の「技術」「フレームワーク」 | 思考の「土台」「総合的な能力」 |
| 習得方法 | 本や研修で学び、後天的に習得できる | 日常の経験や意識的な訓練で鍛えるもの |
| 具体例 | MECE、ロジックツリー、ピラミッド構造 | 因果関係の把握、本質の見抜き、前提を疑う |
| 目指す姿 | 誰がやっても同じ結論にたどり着ける再現性 | 独自の視点で新たな結論や価値を導き出す |
| 例えるなら | 料理のレシピ、包丁の使い方 | 料理人のセンス、調理の腕前 |
Google スプレッドシートにエクスポート
どうでしょうか。こうして見ると、両者の役割の違いがクリアになりますよね。ロジカルシンキングはあくまで「手段」であり、それを使いこなす「論理的思考力」こそが、本当の意味での思考力の源泉なのです。
【明日からできる】論理的思考力を爆上げする5つの習慣
「じゃあ、土台となる論理的思考力はどうやって鍛えればいいの?」 ご安心ください。論理的思考力は、才能ではなく、日々のちょっとした意識と習慣で、誰でも鍛えることができます。ここでは、明日からすぐに始められる5つのトレーニング習慣をご紹介します。
1. 「So What?(だから何?)」「Why So?(それはなぜ?)」を口癖にする
これは、ロジカルシンキングの技術でもありますが、思考の「地力」を鍛える最高の筋トレです。ニュースを見たり、上司から指示を受けたりしたときに、頭の中で「で、結局何が言いたいの?(So What?)」「なんでそうなるの?(Why So?)」と自問自答する癖をつけましょう。物事を鵜呑みにせず、深く考える姿勢が自然と身につきます。
2. 前提を疑う癖をつける(クリティカルシンキング)
私たちは無意識のうちに「これはこういうものだ」という思い込み(前提)にとらわれています。「この会議は本当に必要?」「このやり方がベストなの?」と、当たり前を疑ってみましょう。常識を疑うことで、思考停止を防ぎ、誰も気づかなかった新しい視点やアイデアが生まれるきっかけになります。
3. 物事を構造化・図解してみる
考えがまとまらないとき、それは頭の中で情報がごちゃごちゃになっている証拠です。そんなときは、ノートやホワイトボードに、話の登場人物や要素を書き出し、線で結んで関係性を整理してみましょう。頭の中を「見える化」するだけで、問題の構造が驚くほどスッキリと理解でき、論理の矛盾点にも気づきやすくなります。
4. 他人に説明してみる
自分が理解しているかどうかを確かめる一番の方法は、その事柄について全く知らない人に説明してみることです。「あれ、うまく伝わらないな」「ここ、なんて言えばいいんだろう」と感じた部分こそ、あなた自身が論理的に理解できていない部分。説明というアウトプットを通して、思考の穴を見つけ、埋めていくことができます。
5. 異なる分野の本や情報に触れる
いつも同じ分野の情報ばかりに触れていると、思考のパターンも凝り固まってしまいます。意識的に自分の専門外の本を読んだり、普段は見ないジャンルのドキュメンタリーを見たりしてみましょう。異なる分野の知識や考え方が結びつくことで、物事を多角的に捉える力が養われ、思考の引き出しが一気に増えます。
これらの習慣は、一つひとつは小さなことですが、毎日続けることで、あなたの思考のOSは確実にアップデートされていきます。
まとめ:思考の「型」を学び、「地力」を鍛えよう
今回は、「ロジカルシンキング」と「論理的思考力」の違いについて、深掘りしてきました。
- ロジカルシンキングは、思考を整理するための便利な「技術(フレームワーク)。
- 論理的思考力は、その技術を使いこなすための「土台となる総合的な能力」。
大切なのは、どちらか一方ではなく、両方をバランス良く高めていくことです。
まずは、MECEやロジックツリーといったロジカルシンキングの「型」を学ぶことで、考えを整理する武器を手に入れましょう。そして同時に、日々の習慣を通して、物事の本質を見抜く論理的思考力という「地力」を鍛え続けるのです。
思考の技術と地力が組み合わさったとき、あなたの説得力、問題解決能力、そして仕事の成果は、間違いなく飛躍的に向上するはずです。
今日から、身の回りの出来事に対して「だから何?」「なぜ?」と問いかけることから始めてみませんか?その小さな一歩が、あなたの未来を大きく変える思考革命の始まりです。



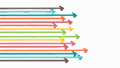
コメント