
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 「人的資本経営って、結局のところ本当に儲かるの?」と半信半疑な経営者・人事の方
- 理屈は理解したけど、他社がどうやって成功しているのか、リアルな事例を知りたい方
- 自社で人的資本経営を導入するための、具体的なヒントやパクれるアイデアが欲しい方
- 社員のやる気を引き出し、会社の業績も右肩上がりにしたい、すべてのリーダーの方
- これから入る会社が、本当に自分を大切にしてくれるか見極めたいと考えている方
「人を大切にすれば、会社は儲かる」。 言葉にすれば聞こえはいいですが、どこか綺麗事のように感じてしまう人も多いのではないでしょうか。「そんな理想論で、厳しいビジネスの世界を勝ち抜けるのか?」と。
しかし、この「綺麗事」を本気で実践し、見事に証明してみせた企業が、日本には確かに存在します。
赤字事業からの劇的なV字回復。右肩上がりの売上成長。そして、優秀な人材が「辞めない」どころか、どんどん集まってくる組織文化。これらはすべて、「人的資本経営」への舵切りがもたらした、紛れもないリアルな成果なのです。
この記事では、絵に描いた餅で終わらせない、本物の人的資本経営を実践する企業の「生々しい」取り組みを、具体的な数字と共に徹底解剖していきます。丸井グループ、KDDI、サイボウズは一体何をしたのか?その成功の裏側にある、業種や規模を超えた共通の「鉄則」とは何なのか?
この記事を読み終える頃には、あなたの会社の「人」という最も身近な資産を、「莫大な利益」に変えるための、具体的なアクションプランが見えてくるはずです。
「人への投資」は本当に儲かるのか?データが示す驚きの事実
個別の事例を見る前に、まず大前提として「人的資本への投資は、本当に企業業績に繋がるのか?」という疑問に、客観的なデータでお答えしましょう。
結論から言うと、答えは明確に「YES」です。
経済産業省がまとめた資料によると、従業員エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)のスコアが高い企業グループは、低い企業グループに比べて、営業利益率が平均で約2倍も高いという相関関係が示されています。
さらに、世界最大級の意識調査機関であるGreat Place to Work® Institute Japanの調査では、「働きがいのある会社」として選出された企業の株価の伸びが、日本の代表的な株価指数であるTOPIXを大きく上回り続けるという結果も出ています。
つまり、社員がいきいきと働いている会社ほど、収益性が高く、市場からも将来性を高く評価されているのです。
これからご紹介する事例は、決して奇跡的な成功譚ではありません。この「人を大切にすることが、企業の成長に繋がる」という原理原則を、愚直に、そして戦略的に実践した結果なのです。
事例1:【丸井グループ】「手挙げ文化」で赤字からV字回復、売上2.4倍へ
今でこそ、先進的な企業として知られる丸井グループですが、2000年代後半、彼らは大きな岐路に立たされていました。主力だった「モノを売る」小売事業が時代の変化とともに苦戦し、業績は低迷。このままではジリ貧だという強い危機感がありました。
転換点:モノ売りから「信用」を売るビジネスへ
彼らが下した決断は、クレジットカード事業を核としたフィンテック企業への大胆なビジネスモデル転換でした。しかし、この壮大な変革を実現するには、マニュアル通りに動く人材ではなく、社員一人ひとりが自ら考え、挑戦する「自律したプロ」になる必要がありました。経営陣は、会社の未来を社員の成長に賭けたのです。
具体的な取り組み
丸井グループの変革を象徴するのが、「手挙げの文化」です。
- 自らキャリアを創る:社員が「この仕事がやりたい」「この部署に行きたい」と自ら手を挙げて異動希望を出せる制度を導入。驚くべきことに、現在では年間3,000件以上の手が挙がり、組織の新陳代謝と活性化を促しています。
- 年齢ではなく「専門性」で評価:多くの日本企業に残る「役職定年」を廃止。年齢に関係なく、社員がプロフェッショナルとして専門性を磨き、長く活躍できる環境を整えました。
- 「人の成長」を本気で評価:従来の売上目標だけでなく、「社員のしあわせ」や「お客さまのしあわせ」といった非財務的な指標を重要な経営目標(インパクト目標)に設定。全社員が「人の成長こそが会社の成長」だと信じられる仕組みを構築しました。
驚きの成果
この「人」を中心とした経営への転換は、目覚ましい成果となって表れます。
かつて低迷していた営業利益は、2014年3月期の216億円から、2023年3月期には526億円へと約2.4倍にまでV字回復を遂げました。
社員が自律的に動く「手挙げの文化」から、アニメ事業やD2C支援事業など、これまでの丸井にはなかった新しいビジネスが次々と生まれ、新たな収益の柱へと育っています。まさに、社員の成長が、企業の成長そのものに直結したのです。
事例2:【KDDI】「全社員DX人財化」を掲げた大企業の覚悟
通信インフラという巨大で安定した事業基盤を持つKDDI。しかし、その安定性は裏を返せば、組織の硬直化や年功序列といった大企業ならではの課題も生み出していました。5Gの普及や異業種からの参入など、激変する事業環境の中で、このままではいけないという危機感が彼らを動かしました。
転換点:「プロ人財」への変革宣言
2020年、KDDIは「KDDI版ジョブ型人事制度」の導入を柱とする、新人事制度を発表。これは単なる制度変更ではありませんでした。「全社員が会社の看板に頼らずとも通用するプロフェッショナルになろう」という、会社と社員の双方に向けた、覚悟のメッセージだったのです。
具体的な取り組み
その覚悟は、具体的な施策に表れています。
- 「KDDI DX University」の設立:なんと全社員約45,000人を対象に、DX(デジタルトランスフォーメーション)スキルを学ぶための専門組織を設立。入門レベルから高度な専門スキルまで、誰もが学びたいときに学べる環境を整備しました。
- 役割と成果に基づく評価:年齢や勤続年数ではなく、社員が担う「仕事(ジョブ)」の価値と、そこで出した「成果」によって評価される仕組みに転換。これにより、若手でも大きな役割に挑戦し、正当に評価される道が開かれました。
- 挑戦を促す「社内副業制度」:現在の部署に所属しながら、業務時間の20%を使って別のプロジェクトに参加できる制度を導入。社員はリスクを取らずに新しいスキルや経験を積むことができ、組織の壁を越えたイノベーションが生まれやすくなっています。
驚きの成果
こうした取り組みの結果、KDDIの従業員エンゲージメントスコアは、国内企業の中でもトップクラスの水準まで向上しました。社員一人ひとりの専門性と挑戦意欲が高まったことは、金融、エネルギー、エンターテインメントといった、通信以外の事業領域の成長を力強く後押ししています。大企業が本気で「人」に投資することで、巨大な船のエンジンを新しいものに載せ替えようとしているのです。
事例3:【サイボウズ】離職率28%が4%に!「100人100通りの働き方」
グループウェアで知られるサイボウズ。今でこそ「働きがいのある会社」の代名詞的存在ですが、2005年頃、会社は崩壊の危機にありました。急成長の歪みで長時間労働が常態化し、離職率はなんと28%にまで達していたのです。
転換点:「個人のわがまま」を許容する逆転の発想
この危機を救ったのは、創業者の青野社長自身の経験でした。育児のために働き方を変えざるを得なくなったとき、「個人の事情を優先すると、チームの生産性は下がる」という常識に疑問を抱きます。そして、「チームの生産性を最大化するには、むしろ個人のわがまま(多様な働き方)を徹底的に受け入れるしかない」という、180度違う結論にたどり着いたのです。
具体的な取り組み
サイボウズの施策は、徹底して「個人」に寄り添っています。
- 究極に柔軟な働き方:働く場所や時間を社員が自由に決められる「ウルトラワーク」や、週休3日を選べる制度など、文字通り「100人いれば100通りの働き方」を許容。
- 「働き方宣言」でオープンに:全社員が、自分が希望する働き方(勤務時間、場所、残業の可否など)を社内のグループウェアで公言。これにより、周囲もその人の働き方を尊重し、チームとしてどう補い合うかを考える文化が生まれました。
- 徹底した情報公開:驚くことに、経営会議の議事録を含む、ほぼ全ての社内情報が全社員にオープンにされています。「知る、考える、議論する」というプロセスを全員で共有することで、社員一人ひとりが会社の当事者として自律的に判断できる土壌を育んでいます。
驚きの成果
結果は劇的でした。28%に達した離職率は、現在ではわずか4%前後という驚異的な低水準で安定。社員の働きがいと創造性が解放された結果、会社の業績も右肩上がりで、売上高は10年以上連続で増収を続けています。社員の「辞めたい」を「ここで働き続けたい」に変えたことが、最高の経営戦略となったのです。
成功企業に共通する「3つの鉄則」とは?
丸井グループ、KDDI、サイボウズ。業種も規模も文化も異なりますが、その成功の裏側には、驚くほど共通した「3つの鉄則」が存在します。
鉄則1:経営トップが「本気」でコミットし、語り続けている
どの事例も、変革は人事部に丸投げではありません。丸井の青井社長、KDDIの高橋社長、サイボウズの青野社長といった経営トップ自らが、変革の必要性を自らの言葉で、情熱を持って、繰り返し社員に語りかけています。トップの揺るぎない覚悟と本気度こそが、巨大な組織を動かす最大のエンジンなのです。
鉄則2:「性善説」に基づき、社員の可能性を心から信じている
3社に共通するのは、「社員はサボるものだ」という性悪説的な管理思想ではなく、「社員は誰もが成長したい、貢献したいと願っている」という性善説に基づいている点です。だからこそ、社員を信頼して権限を委譲し、情報をオープンにし、自律的な挑戦を促すことができる。この信頼が、社員の当事者意識に火をつけます。
鉄則3:「対話」と「透明性」を何よりも大切にしている
手挙げ文化、1on1ミーティング、オープンな情報共有。形は様々ですが、いずれの企業も社員と経営、社員同士の「対話」の機会と、意思決定プロセスの「透明性」を徹底的に重視しています。社員が「自分は大切にされている」「会社の状況がよく分かる」と感じられること。この安心感が、エンゲージメントの土台となっています。
まとめ:あなたの会社も「人」が最強の資産になる
今回ご紹介した事例は、私たちに非常に重要なことを教えてくれます。 それは、人的資本経営とは、企業の規模や業種に関係なく実践できる、普遍的で強力な成長戦略であるということです。
もちろん、他社の成功事例をそのまま真似するだけではうまくいきません。大切なのは、これらの事例の裏にある「鉄則」を学び、自社の現状と真摯に向き合うことです。
「私たちの会社にとって、社員の成長とは何か?」 「社員の可能性を信じ、解き放つために、何ができるか?」
まずは、経営陣が、リーダーが、この問いについて本気で対話を始めること。その小さな一歩が、社員一人ひとりの心に火をつけ、やがては会社全体を未来へと動かす、最もパワフルな力になるはずです。あなたの会社にとって、最も価値のある資産は、すでに足元にいる「人」なのですから。


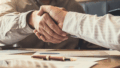

コメント