
【この記事はこんな方に向けて書いています】
✅ IT業界に興味があるけど、働き方がよくわからない…
✅ 「SES」って言葉は聞くけど、派遣と何が違うの?
✅ エンジニアとして働く上で、自分に合った契約形態を知りたい!
✅ これからエンジニアを採用したいけど、どの契約がいいか迷っている…
IT業界で働いていると、必ずと言っていいほど耳にする「SES(エスイーエス)」という言葉。でも、「それって結局、派遣みたいなものでしょ?」なんて、ちょっと曖昧な理解のままにしていませんか?
実は、SESは派遣や請負とは全く異なる、IT業界特有の契約形態なんです。この違いを知らないままだと、エンジニアとして働く上でのキャリアプランを見誤ってしまったり、企業側としては人材をうまく活用できなかったりする可能性も…。
この記事では、そんな「今さら聞けない!」と感じているあなたのために、SESの基本から、派遣・請負との明確な違い、そしてエンジニアと企業双方にとってのメリット・デメリットまで、どこよりも分かりやすく解説します!
結論から言うと、SESとは「準委任契約」という契約に基づき、エンジニアの技術力を時間単位で提供するサービスのこと。この記事を読み終える頃には、それぞれの契約形態の違いがスッキリ整理され、自分や自社にとって最適な選択肢が見えてくるはずです。
まずは結論!SESの正体は「準委任契約」です
「SESって何?」と聞かれたら、まずはこう答えましょう。 「エンジニアの技術力を、時間単位で提供するサービスだよ」と。
SESは「System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)」の略称です。 多くの場合は、クライアント企業のオフィスに常駐して、システム開発やインフラ運用などの業務をサポートします。
ここでの最大のポイントは、契約形態が「準委任契約」であるという点です。 法律の話が出てくると少し難しく感じてしまうかもしれませんが、大丈夫です。 簡単に言うと、「特定の業務を、善良な管理者の注意をもって行うこと」を約束する契約です。
ポイントは「成果物の完成」を義務としていないこと。 あくまでエンジニアがスキルを提供し、決められた時間きちんと働くことに対して報酬が支払われます。 この「時間に対して対価が支払われる」という点が、SESを理解する上で非常に重要になります。
【徹底比較】SES・派遣・請負、何がどう違うの?
SESを正しく理解するために、よく混同されがちな「派遣」「請負」との違いをハッキリさせておきましょう。 この3つの最も大きな違いは、「指揮命令権がどこにあるか」という点です。 指揮命令権とは、カンタンに言うと「誰がエンジニアに仕事の指示を出すか」という権利のことです。
この違いを表にまとめると、一目瞭然です。
| 契約形態 | SES(準委任契約) | 派遣(労働者派遣契約) | 請負(請負契約) |
| 契約の目的 | 業務の遂行(労働力の提供) | 労働力の提供 | 仕事の完成(成果物の納品) |
| 指揮命令権 | 自社(SES企業) | 派遣先企業 | 自社(受託開発企業) |
| 成果物責任 | 負わない | 負わない | 負う |
| 報酬の対象 | 労働時間 | 労働時間 | 成果物 |
Google スプレッドシートにエクスポート
いかがでしょうか? それぞれの特徴を、もう少し詳しく見ていきましょう。
SES(準委任契約)の仕組み
指揮命令権は、エンジニアが所属している「SES企業」にあります。 そのため、常駐先であるクライアント企業の担当者が、SESエンジニアに対して直接「この作業を明日の10時までにやっておいて」といった具体的な指示(命令)を出すことは、原則としてできません。
実務上は、クライアントとコミュニケーションを取りながら作業を進めますが、あくまで契約上の指揮命令権は所属会社にある、と覚えておきましょう。 報酬はエンジニアが働いた時間に対して支払われます。
派遣(労働者派遣契約)の仕組み
派遣は、皆さんが最もイメージしやすい働き方かもしれませんね。 派遣会社に登録し、そこから紹介された「派遣先企業」で働きます。 この場合、給与は派遣会社から支払われますが、仕事の指示は「派遣先企業」の担当者から直接受けます。 指揮命令権が派遣先にある、というのがSESとの決定的な違いです。 報酬はSESと同じく、働いた時間に対して支払われます。
請負(請負契約)の仕組み
請負契約は、他の2つとは大きく性質が異なります。 目的は、労働力を提供することではなく、「成果物を完成させて納品すること」です。 例えば、「このECサイトを3ヶ月で構築してください」といった依頼がこれにあたります。
指揮命令権は、開発を担当する「自社(受託開発企業)」にあります。 クライアントは開発の進め方について細かく指示することはできず、全て自社の責任でプロジェクトを進め、期日までに約束したものを納品する義務を負います。 そのため、報酬は「成果物」に対して支払われます。
エンジニア視点!SESで働くメリット・デメリット
では、実際にエンジニアとしてSESで働くことには、どのような良い点と、注意すべき点があるのでしょうか。
SESで働くメリット
- 未経験からでもIT業界に挑戦しやすい SES企業は未経験者向けの研修制度を整えていることが多く、IT業界への入り口として非常に門戸が広いです。まずは実務経験を積みたい、という方にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
- 様々な現場や技術に触れられる 通常、数ヶ月から数年単位で常駐先が変わることが多いです。そのため、大企業の開発現場から最新技術を扱うスタートアップまで、様々な環境を経験できます。いろいろな企業の文化や開発スタイルに触れることで、自身のスキルセットを多様化させることが可能です。
- 人間関係をリセットしやすい もし常駐先の人間関係で悩んだとしても、契約期間が満了すれば別の現場に移ることができます。環境を変えやすい点は、精神的なセーフティーネットになるかもしれません。
SESで働くデメリット
- 給与が上がりにくい構造 SESのビジネスモデルは、クライアントから受け取る単価と、エンジニアに支払う給与の差額が企業の利益となります。そのため、エンジニアの単価が上がっても、それが直接給与に反映されにくいという構造的な課題があります。
- キャリアプランを描きにくい 参画するプロジェクトは、基本的に会社の営業力やタイミングに依存します。そのため、「次はAIのプロジェクトに挑戦したい」と思っても、希望通りの案件にアサインされるとは限りません。一貫したキャリアを築きにくい、いわゆる「案件ガチャ」の状態に陥る可能性もあります。
- 会社への帰属意識が薄れやすい ほとんどの時間を常駐先で過ごすため、自社の社員との交流が希薄になりがちです。「自分はどこの会社の人間なんだろう…」と感じてしまうことも少なくありません。
企業視点!SESを活用するメリット・デメリット
次に、エンジニアを発注する企業側から見たSES活用のメリットとデメリットを見ていきましょう。
SESを活用するメリット
- 必要なスキルを迅速に確保できる 「急遽、Javaに詳しいエンジニアが3名必要になった!」といった状況でも、SESを活用すれば自社で採用活動を行うよりもスピーディーに必要な人材を確保できます。プロジェクトの立ち上げ期などに非常に有効です。
- 採用・教育コストを削減できる 正社員を一人採用するには、多大な採用コストと、入社後の教育コストがかかります。SESであれば、既にスキルを持ったエンジニアを即戦力として迎え入れることができるため、これらのコストを大幅に削減可能です。
- 人員調整の柔軟性が高い プロジェクトの繁閑に合わせて、必要な人数を柔軟に調整できます。繁忙期だけ増員し、プロジェクトが落ち着いたら契約を終了するといった柔軟な対応が可能なため、無駄な人件費を抑えることができます。
SESを活用するデメリット
- ノウハウが社内に蓄積されにくい SESエンジニアに開発のコアな部分を任せすぎると、契約終了と同時にそのノウハウも失われてしまいます。長期的な視点で見ると、自社の技術力が育たないというリスクがあります。
- 直接的な指揮命令ができない 前述の通り、SESエンジニアへの指揮命令権は所属企業にあります。そのため、業務の進め方について細かい指示を出しにくく、コミュニケーションに工夫が必要になる場合があります。これを無視して直接命令してしまうと「偽装請負」という法律違反になる可能性があり、注意が必要です。
- 帰属意識の醸成が難しい SESエンジニアはあくまで他社の社員です。自社のビジョンや文化を深く共有し、同じ目標に向かって進む仲間としての一体感を醸成するのは、正社員に比べて難しい側面があります。
SES業界の今とこれから【データで見る未来】
SESという働き方は、日本のIT業界を支える上でなくてはならない存在になっています。 その背景には、深刻なIT人材不足があります。
経済産業省が2019年に発表した「IT人材需給に関する調査」によると、日本のIT人材は2030年には最大で約79万人も不足すると予測されています。
(出典:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)
この圧倒的な人材不足を補うため、企業が必要な時に必要なスキルを確保できるSESの需要は、今後もますます高まっていくと考えられます。 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や、AI、IoTといった新しい技術の台頭により、求められるスキルは多様化・高度化しており、すべてのスキルを自社で抱えるのが難しくなっていることも、SESの需要を後押ししています。
後悔しないために!優良なSES企業の見分け方
もしあなたがエンジニアとしてSES企業で働くことを考えているなら、企業選びは非常に重要です。 ここでは、優良な企業を見分けるための5つのチェックポイントをご紹介します。
- 還元率を公開しているか 還元率とは、クライアントから支払われる単価のうち、どのくらいの割合がエンジニアの給与になるかを示す数値です。この数値を公開している企業は、透明性が高く、エンジニアへの誠実な姿勢がうかがえます。一般的に70%以上が一つの目安とされています。
- 案件の選択肢が豊富か 保有している案件数が多ければ多いほど、自分の希望やキャリアプランに合ったプロジェクトを選べる可能性が高まります。面接の際に、どのような業界や技術の案件が多いのかを具体的に質問してみましょう。
- キャリア相談の体制が整っているか 営業担当者や専門のキャリアアドバイザーが、定期的に面談の機会を設け、エンジニア一人ひとりのキャリアプランについて親身に相談に乗ってくれるかどうかも重要なポイントです。
- エンジニアの教育・学習支援に積極的か 資格取得支援制度や、技術研修、勉強会の開催など、エンジニアのスキルアップをサポートする制度が充実している企業は、社員の成長を大切にしている証拠です。
- 自社サービスや受託開発も行っているか SES事業だけでなく、自社でサービス開発や受託開発も行っている企業は、経営が安定している傾向にあります。また、将来的にはSESから自社開発部門へキャリアチェンジできる可能性もあり、キャリアの選択肢が広がります。
まとめ:自分に合った働き方を見つけるために
今回は、今さら聞けない「SES」について、派遣や請負との違いを中心に、メリット・デメリットまで詳しく解説してきました。
もう一度ポイントをおさらいしましょう。 ・SESは「準委任契約」で、エンジニアの労働時間を対価とする ・派遣との違いは「指揮命令権」がクライアントではなく自社にあること ・請負との違いは「成果物」ではなく「労働力」を提供すること
SESは、IT業界の深刻な人材不足を背景に、多くのエンジニアと企業を繋ぐ重要な役割を担っています。 メリット・デメリットの両側面を正しく理解することで、エンジニアにとっては自分らしいキャリアを築くための選択肢となり、企業にとっては事業を成長させるための強力なパートナーとなり得ます。
この記事が、あなたのSESに対する理解を深め、より良いキャリアやビジネスの選択に繋がれば幸いです。


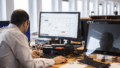
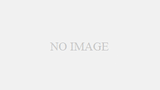
コメント