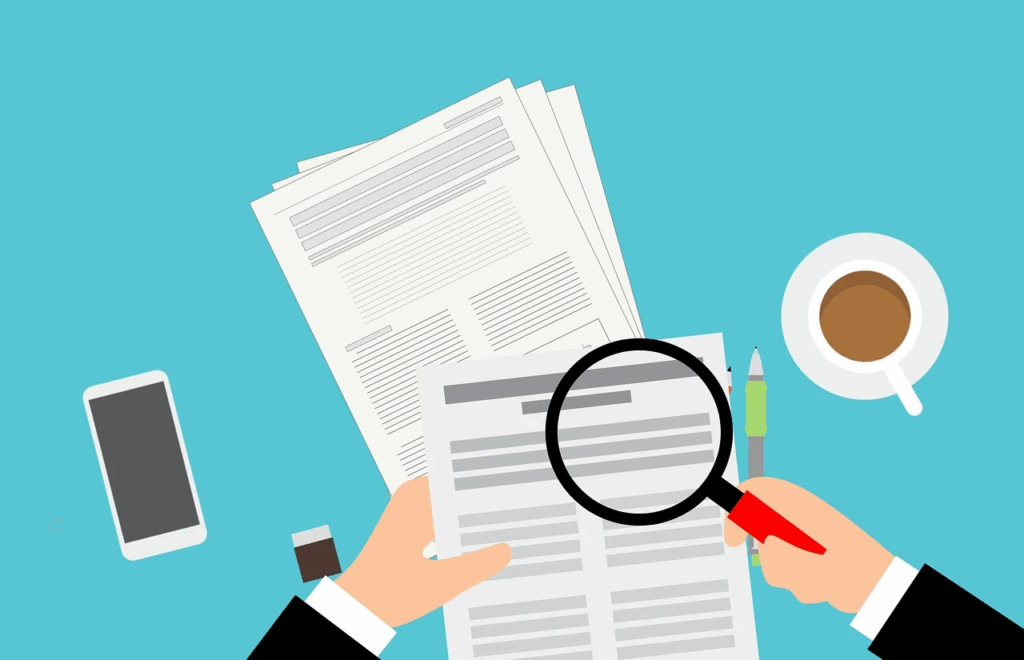
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 「フェルミ推定」という言葉は聞いたことがあるが、正直よくわからないし、必要性も感じていない。
- ITコンサルタントの面接を控えており、「ケース面接」の対策をしたい。
- 仕事で「で、ざっくりどれくらい?」と聞かれた時に、うまく答えられず固まってしまう。
- 正解のない問題に対して、自分なりの答えを導き出す「地頭力」を鍛えたい。
- 今の自分の思考プロセスに限界を感じており、一段上のレベルに上がりたい。
いきなり、少し厳しいことを言わせてください。
フェルミ推定ができないITコンサルタントは、100%、使えません。
「なんてことを言うんだ」と、不快に思ったかもしれません。しかし、これは決してあなたを貶めるための、大げさな煽り文句ではありません。私がこれまで見てきた、優秀と呼ばれるコンサルタントと、そうでないコンサルタントを分ける、一つの残酷な、しかし紛れもない事実なのです。
なぜなら、ITコンサルタントの仕事とは、突き詰めれば「正解のない問いに、仮説を立て、答えを創り出す」ことの連続だからです。そして、フェルミ推定とは、その根幹をなす「思考のOS(オペレーティングシステム)」そのものだからです。
この記事では、なぜ私がそこまで断言するのか、その理由をITコンサルタントの日常業務と絡めて解き明かし、そして、あなたの頭に「できるコンサル」の思考OSをインストールするための、超具体的なトレーニング方法までを、徹底的に解説します。この記事を読み終えた時、あなたはもうフェルミ推定を「面倒な面接対策」とは感じなくなっているでしょう。
フェルミ推定とは?クイズではなく「未知と格闘する思考体力テスト」だ
「日本全国にある電柱の数は?」「シカゴにいるピアノ調律師の数は?」 フェルミ推定と聞くと、多くの人がこうした「奇妙なクイズ」を思い浮かべるでしょう。そして、「そんなこと知ってて、何の意味があるの?」と感じてしまう。これが、多くの人がフェルミ推定を誤解する、最初のつまずきポイントです。
フェルミ推定の本質は、答えの正解・不正解を当てることではありません。 その本質は、「全く見当もつかない数字(未知)に対して、自分の持っている知識(既知)と論理を武器に、どう立ち向かい、現実的な答えの”あたり”をつけるか」という、思考のプロセス、いわば「未知との格闘技」なのです。
コンサルタントの採用面接官は、あなたが導き出した「電柱は1500万本です」という答えの数字自体には、ほとんど興味がありません。彼らが見ているのは、その数字に至るまでの、あなたの思考の体力、つまり、
- 問題をどう分解し、構造化したか(構造化能力)
- どんな仮説を立て、その根拠を示したか(仮説構築力)
- 議論を前に進めるための、コミュニケーションが取れるか(対話力)
といった、コンサルタントとしての基礎能力なのです。
なぜ「使えない」のか?仕事が「フェルミ推定の連続」だからだ
では、なぜこの「未知との格闘技」ができないと、ITコンサルタントとして「使えない」のでしょうか? 答えはシンプル。ITコンサルタントの日常業務が、大小さまざまなフェルミ推定の連続だからです。
想像してみてください。あなたは、ある大手製造業のDX推進プロジェクトに配属されました。
- クライアントの役員: 「この新しいIoTシステムを導入したら、うちの工場の生産性は、ざっくりどれくらい上がるのかね?」
- プロジェクトマネージャー: 「来週の提案までに、このシステム開発に必要な工数を概算で見積もってくれないか?」
- あなたの心の声: (クライアントは『この新サービスで市場規模100億円を狙う』と言っているが、その数字に妥当性はあるのだろうか?)
これらの問いに、どう答えますか? Googleで検索しても、答えはどこにも載っていません。社内の過去の資料を探しても、全く同じ事例は見つかりません。
この、「データがない」「前例がない」という八方塞がりの状況で、フリーズしてしまうのが「使えない」コンサルタントです。
一方で、「できる」コンサルタントは、こう考えます。 「分かりました。いくつかの仮説を置いた上で、概算値を算出してみます。まず、生産性を定義するために、製造ラインのボトルネックとなっている工程を特定し…」
そう、彼らは自然にフェルミ推定を始めているのです。 「分からない」で終わらせず、「分からないなりに、現時点で最も確からしい答えを導き出す」。この思考のOSがインストールされているかどうかが、プロフェッショナルとしての価値を決定的に分けるのです。
実践!思考OSインストール講座「日本のEV充電器の必要数を推定せよ」
理屈はもう十分でしょう。ここからは、実際にあなたの頭に思考OSをインストールしていきます。 題材は、ITコンサルタントなら扱う可能性のある、現代的なテーマにしましょう。
お題:『日本全国に必要な、公共用の急速EV充電器の数は?』
ステップ1:前提の確認(ゴールを明確にする)
まず、格闘を始める前に、相手(問題)の姿をハッキリさせます。
- 「公共用」とは?(高速道路のSA、道の駅、商業施設など。個人の家は除く)
- 「急速」とは?(30分程度で充電できるものを想定)
- 「必要数」とは?(将来のEV普及率がピークになった時点での、需要を満たす数)
この前提確認を怠ると、議論がズレてしまいます。
ステップ2:式の立案(思考の骨格を作る)
次に、この問題を解くための「骨格」となる計算式を立てます。これが最も重要です。
(日本全国のEVが、1日に必要とする公共での総充電回数) ÷ (充電器1基が、1日に対応できる充電回数) = 必要な充電器の数
どうでしょうか。この式さえ立てられれば、あとはそれぞれの項目を分解していくだけです。巨大な問題が、解けるレベルのパーツに分かれました。
ステップ3:要素の分解と仮説設定(肉付けをする)
ここからは、分解した要素を、自分の知識や仮説で埋めていきます。
A:1日の総充電回数
- 日本のEV保有台数
- 日本の自動車保有台数:約8,000万台(既知のデータ)
- 将来のEV普及率:30%と仮定(政府目標などを参考に仮説設定)
- → 8,000万台 × 30% = 2,400万台
- 公共充電器の利用頻度
- 多くの人は自宅で充電するはず。公共充電器を使うのは、主に長距離移動や緊急時。
- 平均して、1台あたり2週間に1回(月2回)公共充電器を使うと仮定。
- → 2,400万台 × (1回 / 14日) ≒ 約170万回/日
B:充電器1基あたりの対応回数
- 充電器の稼働時間
- 24時間稼働しているが、深夜の利用は少ない。実質的なピーク稼働時間を1日12時間と仮定。
- 1回あたりの充電・入れ替え時間
- 急速充電30分 + 車の入れ替え等で15分 = 平均45分/回と仮定。
- → (12時間 × 60分) ÷ 45分/回 = 16回/日
ステップ4:計算と現実性チェック(答えを出す)
さあ、全てのパーツが揃いました。計算してみましょう。
170万回 ÷ 16回 ≒ 約106,000基
答えが出ました。しかし、ここで終わりではありません。プロは必ず「現実性チェック(リアリティチェック)」を行います。 「約10万基か…。今のガソリンスタンドの数が全国で約3万箇所だから、その3倍以上か。主要な施設に複数台置かれることを考えれば、非現実的な数字ではなさそうだな」 このように、他の数字と比較して、自分の答えの妥当性を検証する癖をつけましょう。
以上が、思考OSの基本的な動きです。このプロセスを、どれだけ速く、そして正確に回せるかが、あなたの価値を決めます。
フェルミ推定で絶対にやってはいけないこと
最後に、この思考OSを使いこなす上での注意点を2つだけお伝えします。
- 知らないことを知ったかぶること 「日本の自動車保有台数は、確か…8,000万台だったと思います」のように、知らない、あるいはうろ覚えのデータを使う際は、必ず「思います」「と仮定します」と断りを入れましょう。知ったかぶりは、あなたの信頼を一瞬で失わせます。
- 完璧な数字に固執すること フェルミ推定の目的は、あくまで「あたりをつける」ことです。8,253万台のような細かい数字にこだわる必要はありません。「約8,000万台」で十分です。スピード感と、思考の構造こそが命です。
私が冒頭で「使えない」という強い言葉を使ったのは、この思考OSを持たないままコンサルタントになると、あなた自身が最も苦しむことになるからです。クライアントの期待と、自分の実力のギャップに、必ず押しつぶされてしまいます。
しかし、裏を返せば、このOSさえインストールしてしまえば、あなたはどんな未知の問題にも立ち向かえる、極めて「使える」=価値の高いプロフェッショナルになれるのです。 さあ、今日から、身の回りのあらゆるものを題材に、この思考のトレーニングを始めてみてください。

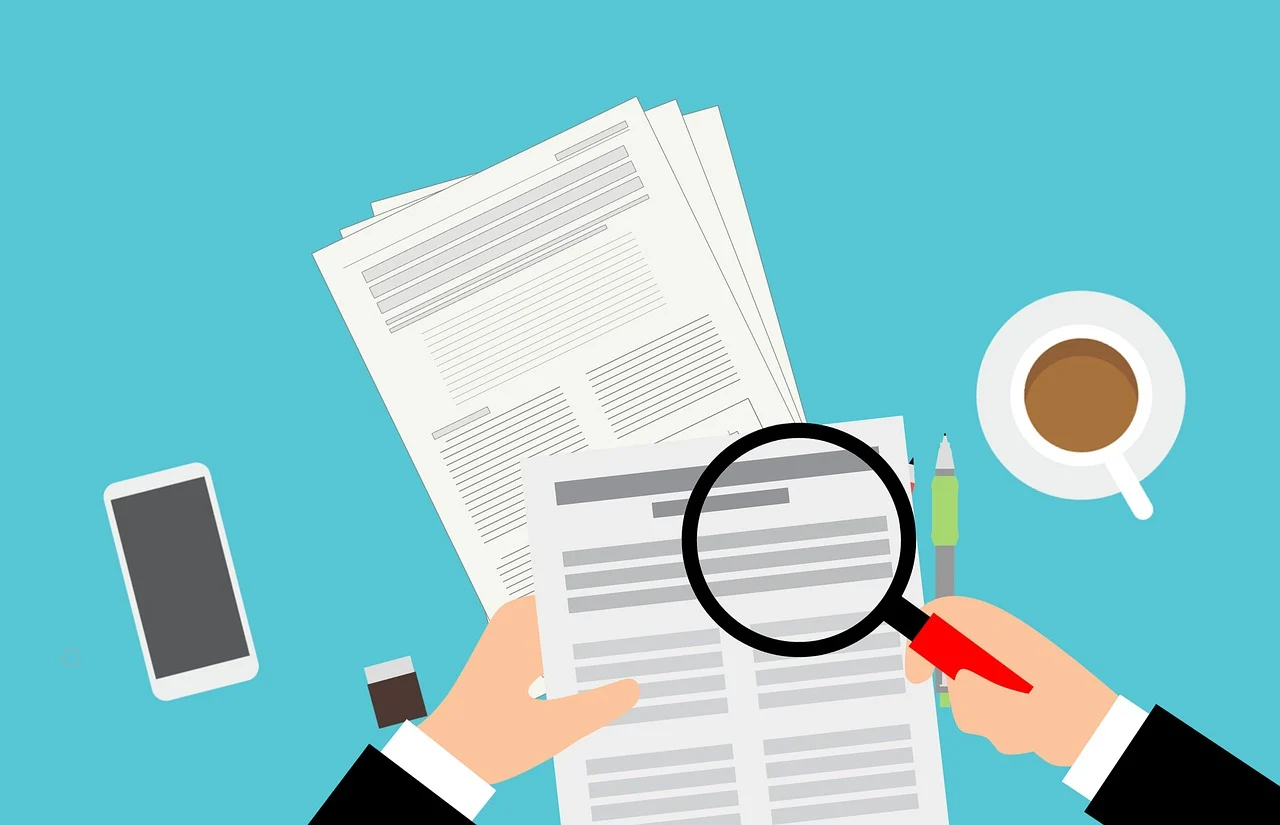
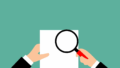
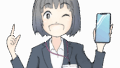
コメント