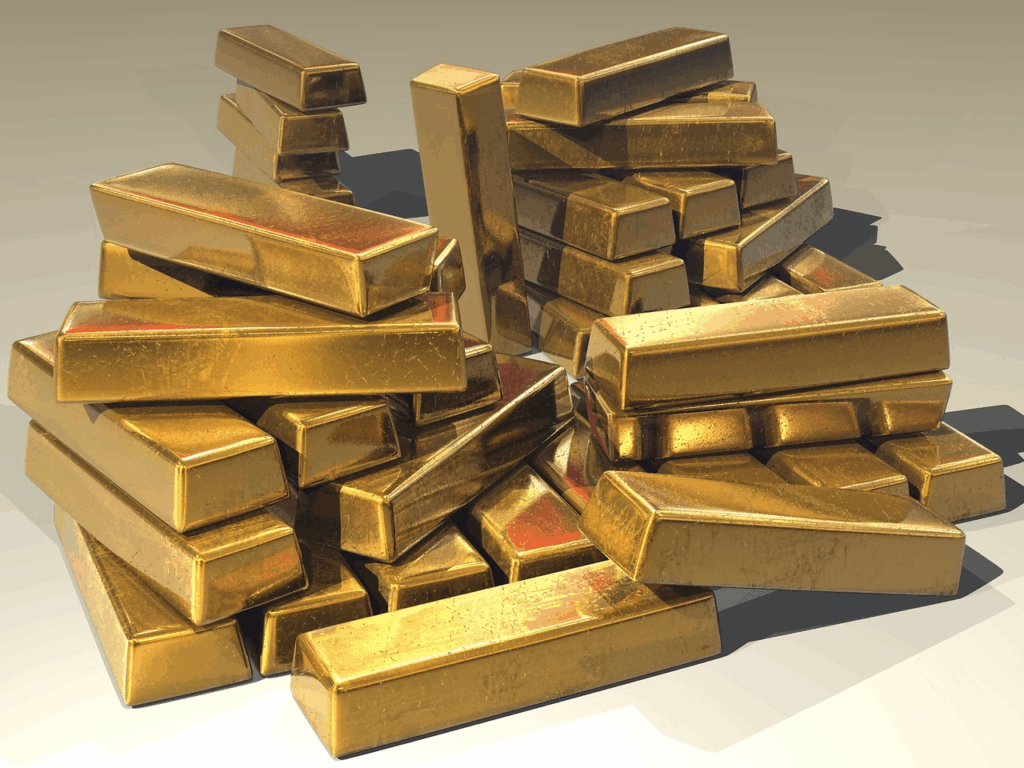
【この記事はこんな方に向けて書いています】
・スキルや経験に見合わない要求をするエンジニアに、頭を悩ませているSES営業・経営者の方
・「自分は特別だ」と勘違いしている同僚や先輩を見て、将来に不安を感じる若手エンジニアの方
・SESのビジネスモデルや、業界が抱える構造的な課題について深く理解したい方
・エンジニアとして、市場価値と自己評価のバランスを取り、健全なキャリアを築きたい方
・クライアントとして、SESパートナーとより良い関係を築きたいと考えている企業の担当者の方
「ウチのエンジニア、スキルシートは出したのに、面談直前になって『気が乗らない』と断ってくるんです…」「新しい技術を学ぶ姿勢はないのに、単金アップの要求だけは人一倍…」。これは、多くのSES企業で日常的に聞かれる嘆きの声です。なぜ、市場価値と自己評価が大きく乖離し、まるで「お客様」かのように振る舞う、通称「エンジニア様」が生まれてしまうのでしょうか。個人の資質や性格の問題だと片付けてしまうのは簡単です。しかし、本質はもっと根深いところにあります。結論から言えば、この問題は、SESという業界構造そのものが、意図せずして「勘違い」を助長してしまっているという、極めて構造的なジレンマなのです。この記事では、感情論を一切排除し、データとロジックに基づいてこの「不都合な真実」を徹底解剖。その上で、エンジニア、企業、双方がこの罠から抜け出し、健全な成長を遂げるための具体的な処方箋を提示します。
データが語る「エンジニアが強い」時代の到来
まず、なぜこのような現象が起きるのか、大前提となる市場環境を客観的なデータで確認しましょう。すべての根源は、深刻な「IT人材不足」にあります。
経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査(2019年)」では、IT需要が中位シナリオで推移した場合、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると試算されています。これは単なる数字ではありません。あらゆる業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる中、その担い手であるエンジニアの需要が供給を圧倒的に上回っている、という厳然たる事実を示しています。
需要が供給を上回れば、供給側の価値が上がるのは市場の原理原則です。つまり、現代のIT市場は、構造的に「エンジニア側が強い(売り手市場)」という状況にあるのです。この抗いがたい市場原理が、「エンジニア様」が生まれる土壌となっていることを、まず私たちは認識しなければなりません。彼らが特別なのではなく、市場が彼らを特別な存在に「見せている」のです。
「エンジニア様」を製造する3つの構造的欠陥
売り手市場であるというだけでは、すべてのエンジニアが「お客様」化するわけではありません。問題は、SESというビジネスモデルが持つ、以下の3つの構造的要因と、売り手市場が化学反応を起こしてしまうことにあります。
構造1:価値尺度が「単金」に過度に依存するシステム
人の価値は、本来多面的なものです。技術力、問題解決能力、コミュニケーション能力、リーダーシップ、チームへの貢献意欲。これらが複雑に絡み合って、一人のプロフェッショナルの価値が決まります。
しかし、SESの現場では、その価値が「月額単価」という、あまりにも分かりやすい一つの数字に集約されがちです。特に、給与体系が単価に連動する「単金連動型」を採用している企業では、この傾向が顕著になります。
| 本来のエンジニアの価値 | SES業界で評価されやすい価値 |
| 技術力・問題解決能力 | 単金 |
| チームへの貢献度 | 案件の継続期間 |
| 後輩育成・ナレッジ共有 | 求められるスキルセットとの一致度 |
| 新技術への探究心 | 稼働率 |
Google スプレッドシートにエクスポート
エンジニアの関心が「顧客の事業にどう貢献するか」よりも「自分の単金をいかに上げるか」に向かってしまうのは、ある意味で合理的な行動です。システムが「単金こそが正義」と囁いているのですから。その結果、技術力や貢献意欲の向上よりも、単金を上げるための「交渉術」ばかりが巧みになっていく、という歪な成長を遂げるリスクが生まれます。
構造2:帰属意識を奪う「客先常駐」という働き方
SESの基本的な働き方は、クライアント企業に常駐することです。これは、自社(所属するSES企業)のオフィスで働く機会が極端に少ないことを意味します。その結果、多くのエンジニアが「自社への帰属意識の希薄化」という問題に直面します。
現場では、彼らは「〇〇(自社名)の社員」としてではなく、「〇〇ができる便利な人」として扱われることが少なくありません。自社の理念や文化に触れる機会も、同僚との一体感を育む機会も乏しい。こうなると、意識が「会社の一員」から「独立した個人事業主」へとシフトしていくのは自然な流れです。
この個人事業主的なマインドは、自律的にキャリアを築く上ではプラスに働くこともあります。しかし、行き過ぎると、組織人として果たすべき責任や義務を軽視し、自らの権利ばかりを主張するようになります。
・自社の研修や勉強会には参加しない(自分のスキルアップに直接関係ないから) ・現場の文化に馴染む努力をしない(どうせ次の現場に行けばリセットされるから) ・会社のルールよりも自分のやり方を優先する(自分は特別だから)
こうした行動は、帰属意識の欠如が生み出す、必然的な帰結とも言えるのです。
構造3:営業 vs エンジニアの「いびつなパワーバランス」
深刻な人材不足を背景に、SES営業は「クライアントを探す」ことよりも「案件を動かせるエンジニアを確保する」ことの方が、はるかに困難なミッションとなっています。これにより、本来対等であるはずの営業とエンジニアの間に、いびつな力関係が生まれがちです。
健全な関係と、いびつな関係の比較
| 観点 | 健全な関係(対等なパートナー) | いびつな関係(営業 < エンジニア) |
| 案件探し | 営業が市場動向と本人のキャリアを考慮し、複数の選択肢を提案。共に最適な案件を選ぶ。 | エンジニアが提示した条件(単金、場所、技術)に合う案件を、営業が必死に探してくる。 |
| 面談 | 営業とエンジニアがタッグを組み、顧客に価値をアピールする「共闘関係」。 | 営業が「どうか面談に行ってください」とお願いする。エンジニアは「気が乗れば」受ける。 |
| 交渉 | 営業がプロとして、顧客とエンジニア双方にとって最適な条件を引き出す。 | エンジニアの希望単金を、営業がそのまま顧客に伝え、ただのメッセンジャーになる。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
営業がエンジニアの顔色をうかがい、理不尽な要求すら飲まざるを得ない状況が常態化すると、エンジニアの自己評価は際限なく高まっていきます。「営業は自分のために動いて当たり前」「会社は自分の希望を叶えて当たり前」という思考に陥るのです。
誰も得しない。「勘違い」がもたらす負のスパイラル
この構造的な問題が引き起こす「エンジニア様」化は、一見するとエンジニア本人だけが得をしているように見えるかもしれません。しかし、長期的に見れば、これは関わる全員が不幸になる「負のスパイラル」の入り口なのです。
・エンジニア本人: 耳の痛いフィードバックをくれる人がいなくなり、客観的な自己評価ができなくなります。居心地の良い環境に安住し、スキルアップを怠った結果、数年後には市場価値が暴落。年齢を重ねてからキャリアの行き詰まりに直面します。
・SES企業: エンゲージメントの低いエンジニアが増え、教育投資をしても無駄になるリスクが高まります。顧客からの信頼も低下し、「〇〇社のエンジニアは扱いにくい」という評判が立てば、事業の根幹が揺らぎます。
・クライアント企業: 高い契約金を支払っているにも関わらず、期待されるパフォーマンスが得られません。チームの和を乱し、他のメンバーのモチベーションまで低下させ、プロジェクト全体の生産性を著しく損なう結果となります。
この問題は、特定の誰かが悪いのではなく、業界構造そのものが生み出した病理です。そして、この病理は、日本のIT業界全体の競争力を静かに蝕んでいくのです。
罠から抜け出し、共に成長するための処方箋
では、私たちはこの構造的欠陥を前に、ただ手をこまねいているしかないのでしょうか。決してそんなことはありません。構造を理解した上で、各々が意識を変え、賢く行動することで、この負のスパイラルを断ち切ることは可能です。
エンジニア自身ができること:「お客様」から「プロフェッショナル」へ
- 3つの資産でキャリアを考える: 「単金」という目先の指標だけでなく、「経験(どんな課題を解決したか)」「スキル(市場価値の高い技術)」「信頼(あの人に任せたいと思われるか)」という3つの無形資産を意識的に蓄積しましょう。
- 市場価値を客観視する: 社内の評価だけでなく、転職サイトに登録してスカウトを受けたり、勉強会やイベントに参加して社外のエンジニアと交流したりすることで、自分の現在地を客観的に把握しましょう。
- 顧客への貢献を第一に考える: 目の前の顧客の事業成功に貢献することこそが、結果的に最も自分の市場価値を高める近道である、という視点を持つことが重要です。
SES企業(経営者・営業)ができること:「管理」から「支援」へ
- 評価制度の多様化: 単金連動型だけでなく、360度評価や、会社やチームへの貢献度を測る指標を取り入れた、多角的な評価制度を構築しましょう。
- 帰属意識を高める「本気の」施策: 月に一度の帰社日を形骸化させず、エンジニアが「帰りたい」と思えるような質の高い勉強会や、部署を超えた交流の場を企画・実行しましょう。定期的な1on1で、キャリアの悩みを親身に聞く姿勢も不可欠です。
- プロとしての対等な関係構築: エンジニアの言いなりになるのではなく、時には厳しいフィードバックも厭わない覚悟が必要です。「あなたのキャリアのために、この経験が必要です」と、プロとして対等な立場で言うべきことを言う勇気が、最終的にエンジニアと会社の成長に繋がります。
あなたは「お客様」ですか? それとも「プロフェッショナル」ですか?
「エンジニア様」という現象は、個人の性格だけに起因するものではなく、IT業界の急成長とSESというビジネスモデルが交差する点で発生した、構造的なバグと言えるかもしれません。
しかし、構造のせいにして思考を止めてしまえば、未来はありません。 エンジニア一人ひとりが、自らを「お客様」ではなく、価値を提供する「プロフェッショナル」として律すること。 企業が、エンジニアを単なる「商品」ではなく、共に成長する「パートナー」として遇すること。
この両輪が噛み合った時、SES業界は、多くのエンジニアにとって、多様な経験を積みながら市場価値を高められる、最高のプラットフォームになり得ます。この記事が、そのための小さな一歩となることを、心から願っています。


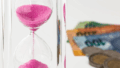
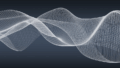
コメント