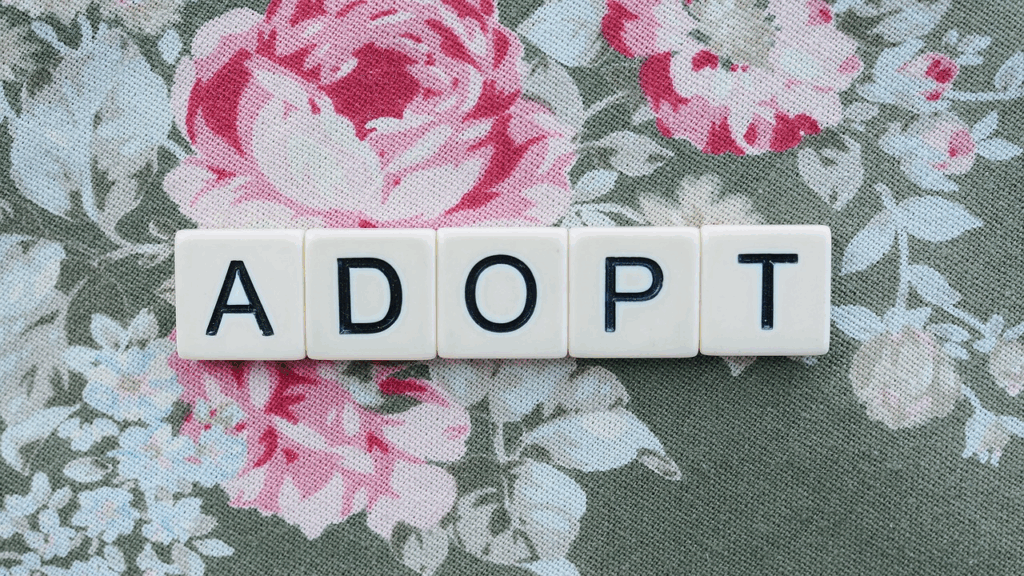
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 求人を出しても応募が全く来なくて、頭を抱えている経営者・採用担当者
- 応募は来るが、求める人材に全く会えないと嘆いている方
- いい人材だと思っても、内定を出すと辞退されてしまうことが続いている方
- 「うちの会社は給料が低いから仕方ない」と、採用できない理由を一つに絞って諦めかけている方
- 採用活動のどこに本当の問題があるのか、本気で知りたいと思っている方
「人が採れないんです。どうすればいいでしょうか…」
もう、この相談を何百回と受けてきたか分かりません。その声色には、焦りと、疲弊と、そして諦めが混じっています。本当に、頭の痛い問題ですよね。
そして、多くの経営者がこう続けます。「やっぱり、給料が安いからでしょうか」「もっと求人広告にお金をかけるべきですかね?」と。
もし、あなたが本気でそう思っているのだとしたら、残念ながら、その考えがすでに行き止まりです。ハッキリ言いますが、あなたの会社が採用できないのは、給料や知名度といった、たった一つの原因のせいではありません。
それは、あなたの会社が、気づかぬうちに蝕まれている複数の「病」が絡み合った結果、つまり「複合要因」なのです。そして、その病に気づかず、給料アップという対症療法に手を出しても、根本的な解決にはなりません。
この記事は、あなたの会社が抱える「不採用の病」を診断するための、少し苦い薬です。耳の痛い話が続きますが、本気で会社を再生させたいなら、目をそらさずに最後まで読んでください。
病その1:自分を客観視できない「自己評価高すぎ病」
まず、最も根深く、そして経営者が最も認めたがらない病がこれです。
「うちは社長と社員の距離が近くて、アットホームな良い会社なんですけどねぇ…」 「大手にはない、風通しの良さが魅力なんですが、なかなか伝わらなくて…」
本気でそう思っていませんか?その「アットホーム」は、見方を変えれば「プライベートに干渉してくる馴れ合い」かもしれません。「風通しの良さ」は、「仕組みがなく、鶴の一声で全てが決まる不安定さ」の裏返しではないでしょうか。
多くの会社が、自分たちの会社の魅力を、社内の論理だけで語ってしまいます。しかし、採用とは、労働市場という戦場で、数多の競合他社と候補者を奪い合う行為です。その戦場で、あなたの会社の「給与水準」「福利厚生」「働き方の柔軟性」「将来性」「ブランドイメージ」は、客観的に見て、どのレベルに位置していますか?
まずは、厳しい現実を直視することです。競合の求人票を研究し、転職サイトの口コミに書かれている(たとえそれが不本意な内容であっても)自社の評価と向き合う。自分たちの「強み」と「弱み」を、客観的な事実に基づいて洗い出すことから、全ては始まります。この健康診断を怠っている会社に、採用戦略を語る資格はありません。
病その2:「誰でもいいから来てくれ病」という名の無策
次に多いのがこの病です。とにかく人手が足りないから、「誰か良い人がいれば採りたい」「真面目でやる気のある若手が欲しい」と、漠然とした求人を出してしまう。
これは、大海原で「何か大きな魚が釣りたい」と言いながら、釣り糸を垂れているのと同じです。釣れるわけがありません。
- なぜ、人が必要なのですか?
- どんなスキルと経験を持った人が、具体的に必要なのですか?
- その人に、どんな仕事で、どんな成果を出してほしいのですか?
- その人の加入で、会社は3年後どうなっていたいのですか?
- そのターゲット人材は、普段どんな情報をどこで見ていますか?
ここまで具体的に「採用ペルソナ(理想の人物像)」を描けていますか? ターゲットが明確でなければ、心に響くメッセージは作れません。使うべき求人媒体も、提示すべき条件も、面接で聞くべき質問も、全てがブレてしまいます。
結果として、誰の心にも刺さらない、当たり障りのない求人票が出来上がり、応募が全く来ないか、あるいは全くターゲットと違う層からの応募ばかりが来て、お互いに時間を無駄にするのです。「誰でもいい」は、結局「誰も来ない」と同じ意味です。
病その3:求職者がドン引きする「時代遅れの求人票」
ペルソナを明確にしても、その「伝え方」が古いままだと、やはり人は来ません。多くの会社、特に歴史のある中小企業がこの病に罹っています。
あなたの会社の求人票、こんな内容になっていませんか?
- 社長の武勇伝や、会社の沿革が延々と書かれている。
- 「やりがい」「成長」「感動」といった、抽象的な言葉が並んでいる。
- 「やる気のある方、お待ちしています!」という、根性論で締めくくられている。
厳しいことを言いますが、今の求職者は、そんな情報に1ミリも興味はありません。 彼らが本当に知りたいのは、もっとリアルで、自分の未来に直結する情報です。
- 入社後、具体的にどんな業務を、どんなツールを使って行うのか?
- どれくらいの裁量権が与えられるのか?
- 3年後、5年後、どんなキャリアパスを歩める可能性があるのか?
- 給与の具体的なレンジはいくらで、評価制度はどうなっているのか?
- 月平均の残業時間は、正直に言って、何時間くらいか?
- どんな人が、どんな雰囲気で働いているのか?(できれば写真や動画で)
求人票は、会社のパンフレットではありません。求職者という「顧客」に、自社という「商品」の魅力を伝えるための「ラブレター」です。自分の言いたいことばかり書くのではなく、相手が知りたいことに、誠実に、具体的に応える。この視点が、決定的に欠けているのです。
病その4:応募者を顧客と思えない「上から目線の選考」
奇跡的に応募があり、面接まで進んだとしても、ここで候補者を逃してしまう会社が後を絶ちません。それは、応募者を「選んでやる」対象だと勘違いしている、「上から目線」の病です。
- 面接官が腕組みをして、候補者の経歴を詰問するように質問する。
- 候補者からの質問に対して、「それは入社してから考えればいい」と不誠実に回答する。
- 結果の連絡が、約束した期日を過ぎても一向に来ない。
- 圧迫面接を「ストレス耐性を見るため」などと正当化している。
一つでも心当たりがあるなら、重症です。 今の時代、候補者はあなたの会社だけを受けているわけではありません。彼らは、複数の選択肢の中から、自分を最も尊重し、大切にしてくれる会社を「選んで」います。劣悪な選考体験(Candidate Experience)は、SNSや口コミサイトを通じて、瞬く間に拡散されます。
応募者は、あなたの会社に興味を持ってくれた「お客様」です。そして、採用に至らなかったとしても、未来の「顧客」になるかもしれないし、あなたの会社の評判を友人に伝える「広報担当者」にもなり得ます。この意識がない会社に、良い人材が集まるはずがありません。
病その5:入ってからが地獄。「育成・定着の崩壊」という根本問題
最後に、最も根深い病の話をします。それは、「人を定着させられない」という問題です。
採用はゴールではありません。スタートです。どんなにコストと時間をかけて優秀な人材を採用しても、すぐに辞めてしまっては、穴の空いたバケツに水を注ぎ続けるようなもの。全く意味がありません。
- 入社後の教育体制が整っておらず、現場に丸投げになっている。
- 上司がマネジメントを放棄し、部下のキャリアに無関心。
- 評価制度が不透明で、頑張りが正当に報われない。
- 一部の社員に業務が偏り、心身ともに疲弊している人がいる。
社員の離職率が高いという事実は、採用市場における最悪のネガティブキャンペーンです。社員紹介(リファラル採用)が全く機能していないのなら、それは社員が、自分の大切な友人や知人に「うちの会社はいいよ」と、胸を張って言えない証拠です。
採用に苦しんでいる会社ほど、外にばかり目を向けて、求人広告や人材紹介会社にお金を使おうとします。しかし、本当に最初にやるべきことは、内側に目を向け、今いる社員が「この会社で働き続けたい」と心から思える環境を整えることです。それこそが、最強の採用戦略なのです。
まとめ:採用活動とは、会社の健康状態を映す「鏡」である
ここまで、5つの「病」についてお話ししてきました。
採用がうまくいかないのは、採用担当者の能力不足や、給料だけの問題ではありません。それは、経営のあり方、組織の文化、社員との向き合い方といった、会社全体の健康状態が、如実に表れた「結果」なのです。採用活動とは、いわば会社の健康状態を映し出す「鏡」です。
この問題に、特効薬はありません。一つ一つの病と真摯に向き合い、組織の体質を地道に改善していく以外に、道はないのです。
さあ、まずは何から始めますか? 手始めに、あなたの会社の求人票を、初めて見る求職者の冷めた視点で、もう一度じっくりと読み返してみてはいかがでしょうか。きっと、治すべき病のヒントが、そこかしこに隠されているはずですから。


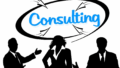

コメント