
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 鳴り物入りで採用した人材が、早期に離職してしまい、頭を抱えている経営者や人事担当者の方
- 現場のリーダーとして、新メンバーの受け入れやオンボーディングに課題を感じている方
- 採用面接で、自社の魅力をアピールすることに必死になりすぎているかもしれない、と感じている方
- 候補者との間に「入社後ギャップ」が生まれてしまう根本原因を知り、対策を打ちたい方
- 長期的に会社に貢献し、活躍してくれる、本当に自社にマッチした人材を採用したいと心から願っている、すべての方
「ぜひ、うちに来てほしい!」 何十人もの候補者と会い、ようやく見つけ出した期待の星。口説き文句を並べ、最高の条件を提示し、やっとの思いで入社してくれた。
しかし、3ヶ月後。彼の口から出てきたのは、こんな言葉でした。 「…聞いていた話と、違います。こんなはずじゃありませんでした」
こんな、悲しい退職届を受け取った経験はありませんか?
厚生労働省の調査によれば、大学を卒業して就職した人のうち、実に3割以上が3年以内にその職場を去っています。その離職理由の上位を常に占めるのが、「仕事内容のミスマッチ」や「労働条件の不一致」、つまり「こんなはずじゃなかった」という入社後のギャップです。
断言しますが、この「聞いてない」問題は、候補者のわがままや、あなたの会社の「運の悪さ」ではありません。その原因の99%は、採用プロセスにおける、企業側の「情報開示の失敗」にあるのです。
この記事では、候補者を魅力的な言葉で飾り立てて「口説き落とす」という、時代遅れの採用活動から決別します。そして、むしろ会社の「不都合な真実」を正直に語ることで、ミスマッチを劇的に減らし、入社後のエンゲージメントと定着率を最大化する、逆転の採用戦略を徹底的に解説していきます。
そのアピール、逆効果かも?”いい人”を演じる採用の限界
まず、採用担当者であるあなたに、一つだけ、胸に手を当てて考えてみてほしいことがあります。 あなたは、面接の場で、候補者に対して「いい人」を演じすぎてはいませんか?
「うちは、風通しが良くて、若手でもどんどん意見が言える社風です」 「フレックスタイム制で、働き方は非常に自由です」 「あなたの〇〇という経験は、弊社の△△という事業で、間違いなく活かせます」
もちろん、これらは事実なのでしょう。しかし、同時に、語られていない「もう半分の真実」があるのではないでしょうか?
「風通しは良いけれど、その分、会議が多くてなかなか前に進まないこともある」 「フレックス制だけど、結局クライアントの都合に合わせるので、コアタイムはほぼ全員出社している」 「その事業で経験は活かせるけれど、同時に、泥臭いレガシーシステムの運用も当分は担当してもらうことになる」
採用とは、自社の魅力をアピールする場であると同時に、候補者が「ここで働く」という、人生の重要な意思決定をするための情報を得る場でもあります。候補者は、企業のキラキラした採用サイトや、美辞麗句が並んだ広報記事には、もはや飽き飽きしています。彼らが本当に知りたいのは、転職会議サイトの口コミに書かれているような、生々しい「リアルな情報」なのです。
あなたの過剰なアピールは、候補者から見れば「何かを隠しているのではないか?」という不信感に繋がりかねません。採用活動における最初のステップは、「いい人」を演じるのをやめ、「正直な人」になることから始まるのです。
“あえて欠点を話す”勇気。RJP理論という最強のスクリーニング
「正直になるのは分かった。でも、うちの会社の欠点を話したら、誰も応募してくれなくなるんじゃないか…」 そう心配する気持ちも、痛いほど分かります。しかし、ここに一つ、あなたの採用活動を根底から変える、強力な理論があります。それが、「RJP(Realistic Job Preview)」理論です。
RJPとは、日本語で「現実的な仕事情報の事前開示」と訳されます。簡単に言えば、「仕事の良い面だけでなく、あえて、厳しい面、泥臭い面、大変な面も、包み隠さず正直に伝える」という採用手法です。
なぜ、このRJPが、結果的に良い採用に繋がるのでしょうか? それには、3つの強力な効果があるからです。
- ワクチン効果: 人は、事前に小さなネガティブ情報に触れておくことで、後で大きなショックを受けた時の精神的なダメージに対する「免疫」ができます。入社前に「うちは結構、泥臭い作業も多いよ」と聞いていれば、実際に入社してそれを目の当たりにしても、「まあ、聞いていた通りだな」と、冷静に受け止めることができるのです。
- スクリーニング効果: あなたが会社の欠点を正直に話した時、「え、そんな大変なんですか? 私には無理そうです…」と感じる候補者は、自ら選考を辞退してくれるようになります。これは、採用する側とされる側の双方にとって、不幸なミスマッチを未然に防ぐ、極めて効率的な「ふるい分け(スクリーニング)」になります。
- コミットメント効果: そして、最も重要なのがこの効果です。会社の良い面も悪い面も、すべてを知った上で、「それでも、この環境で挑戦してみたい」と覚悟を決めて入社してくれた人材は、入社後のエンゲージメントが驚くほど高くなります。彼らは、困難な状況に直面しても、「覚悟の上だ」と、簡単には心が折れないのです。
「うちのチームは、まだ立ち上げ期なので、整ったマニュアルや研修制度はありません。正直、カオスを楽しみながら、自分で道を切り拓いていける人じゃないと、かなりキツいと思います」
この一言で去っていく候補者を、追う必要はありません。この言葉を聞いて、目を輝かせる人材こそが、あなたの会社が本当に求めるべき「仲間」なのです。
面接は”見定める場”ではなく”見せ合う場”。相互理解を深める3つの仕掛け
「候補者の本音」と「会社のリアル」をお互いに開示し、ミスマッチを防ぐためには、従来の「面接官が一方的に質問し、候補者を見定める」という、権威的な選考プロセスそのものを見直す必要があります。
面接は、「選考」の場であると同時に、お互いの素顔を正直に「見せ合う」、相互理解のワークショップであるべきです。そのために、今日から導入できる3つの仕掛けをご紹介します。
1. 逆リファレンスチェックの機会を提供する 企業が候補者の前職の同僚に評判を聞く「リファレンスチェック」は一般的になりました。その逆をやってみるのです。 「もしよろしければ、あなたと年齢や職種の近い、現場の社員と1対1で話す、カジュアルな面談をセッティングしましょうか? 私たち人事には言いにくいことも、何でも自由に質問してみてください」 こう提案することで、候補者は、会社がオープンな姿勢であることを理解し、より深い情報を得ることができます。
2. ワークサンプルテストで「仕事を体験」してもらう 履歴書や面接での受け答えだけでは、その人の本当のスキルや仕事の進め方は分かりません。 「もしよろしければ、弊社のリアルな業務に近い、こんな課題に取り組んでみませんか?」と、有償でワークサンプルテストを依頼してみましょう。これは、候補者のスキルレベルを正確に把握できるだけでなく、候補者自身にとっても、「この会社の仕事は、自分に合っているか?」を判断する最高の機会となります。
3. 「いろんな社員」に会わせる 面接に出てくるのが、いつも人事と役員だけ、ということはありませんか? 候補者が一番知りたいのは、「実際に一緒に働くことになる人たち」の人柄や雰囲気です。 入社後に上司や同僚になるメンバーと話す機会を、必ず設けましょう。キラキラしたエース社員だけでなく、少し癖のあるベテラン社員や、入社したての若手社員など、様々な立場の「リアルな社員」に会わせることで、候補者は、入社後の自分の姿を、より具体的にイメージすることができるのです。
契約書には書かれない”約束”を交わす。期待値調整の最終兵器
採用プロセスの最終盤。内定を出し、候補者が承諾してくれたら、最後の仕上げとして、最も重要な「期待値のすり合わせ」を行います。入社後の「言った、言わない」「聞いてない」を撲滅するための、最終兵器です。
給与や待遇といった、雇用契約書に書かれる形式的な条件だけではありません。仕事の役割、裁量権の範囲、キャリアパス、そして会社が候補者に何を期待しているのかを、明確に「言葉」にして、双方で合意するのです。
例えば、オファー面談で、以下のような「期待値すり合わせシート」をお互いに確認します。
- 会社から候補者への期待
- 入社後3ヶ月のゴール:〇〇を一人で完遂できる状態になる。
- 入社後1年のゴール:△△プロジェクトのリーダーとして、チームを牽引する。
- 候補者から会社への期待
- 実現したいこと:□□の分野で、専門性を高めたい。
- 会社に求める支援:将来的には、マネジメント研修への参加機会がほしい。
この「約束の書」は、入社後のオンボーディングや、最初の評価面談の際の、極めて重要な指針となります。
そして、この面談の最後には、こう付け加えることを忘れないでください。 「何か、入社前に聞いておきたいけど、ちょっと聞きにくいことって、正直ありませんか? 例えば、チームのリアルな残業時間とか、評価制度の細かい運用実態とか…。どんなことでも、今、正直にお答えしますよ」
この、こちらから一歩踏み込む「誠実さ」こそが、候補者の最後の不安を取り除き、固い信頼関係を築くための、最高のクロージングになるのです。
まとめ:最高の採用戦略とは、究極の「誠実さ」である
転職後の「聞いてない」を防ぐための、具体的な戦略。 いかがでしたでしょうか。
- “いい人”を演じるのをやめ、”正直な人”になる。
- RJP理論を使い、あえて”会社の欠点”を語る勇気を持つ。
- 面接を「相互理解の場」と再定義し、リアルな仕事を体験してもらう。
- 入社前に、お互いの「期待値」を言語化し、約束を交わす。
突き詰めれば、これらは小手先の採用テクニックではありません。 その根底にあるのは、たった一つ。候補者を、一人の対等なパートナーとして尊重し、どこまでも「誠実」に向き合うという、企業としての「姿勢」そのものです。
その誠実な姿勢こそが、短期的な採用成功ではなく、長期的に会社を支え、成長させてくれる、本当の「仲間」を引き寄せる、唯一にして最高の採用戦略なのだと、私は信じています。


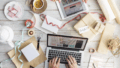
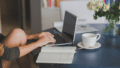
コメント