
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 高額なフィーを払っているのに、コンサルタントの言うことが机上の空論にしか聞こえない、企業の経営者・担当者の方
- 会議でコンサル同士が難解な専門用語で言い争いを始め、完全に置いてきぼりにされた経験がある方
- 優秀なはずのコンサルタントがプロジェクトに入ってから、なぜか社内の雰囲気がギスギスし始めたと感じる方
- これからコンサルタントの活用を考えているが、絶対に失敗したくないと思っている方
- コンサルティング業界の、キラキラしたイメージの裏側にある「リアル」を知りたい、すべてのビジネスパーソンの方
鋭い分析、華麗なプレゼンテーション、そして高額なコンサルティングフィー。 企業の困難な課題を解決に導く「外部の頭脳」として、コンサルタントに大きな期待を寄せるのは当然のことです。
しかし、その裏側で、あなたの会社の貴重な会議室が、彼らのプライドと自尊心を懸けた「マウント合戦」のリングと化しているとしたら…?
「そのフレームワークはもう古いですね」「私のいたファームでは、まずその前提を疑います」「それはファクトベースで語られていますか?」。
そんな言葉が矢のように飛び交い、議論は本質から大きく逸れていく。社内の担当者は萎縮し、活発な意見交換は消え失せる。気づけば、プロジェクトは停滞し、莫大なフィーだけが、まるで砂時計の砂のように、静かに、しかし確実に消えていく…。
これは、決して笑い話ではありません。多くの企業で実際に起きている、しかし誰もが口に出すのをためらう、深刻な悲劇なのです。
なぜ彼らは、クライアントの課題そっちのけで、仲間同士のマウント合戦に明け暮れてしまうのか?そして、その不毛な戦いが、いかにクライアント企業を静かに、しかし確実に蝕んでいくのか?
この記事では、その知られざるメカニズムを、心理学的な背景や客観的なデータと共に徹底解剖。あなたの会社を「ダメにするコンサル」から守るための、具体的な見極め方までを、余すことなくお伝えします。
それ、全部ムダです。会議を破壊する「コンサルマウント」あるある10選
まず、皆さんの会社で起きている「違和感」の正体を、具体的な言動で言語化してみましょう。もし3つ以上当てはまったら、要注意信号です。
- 難解な横文字・専門用語のオンパレード 「イシュー」「バリュー」「アジェンダ」は序の口。「MECE」「ロジックツリー」「コアコンピタンス」などを、あえて難しく、さも当然のように使い、相手がポカンとしているのを見て、心の中で優越感に浸る。
- 伝家の宝刀「それはファクトですか?」 相手の意見やアイデアに対し、議論を深めるためではなく、思考を停止させるためにこの言葉を使う。反論されると「それはあなたの感想ですよね?」と畳みかける。
- 事あるごとに炸裂する「出身ファーム・学歴」自慢 「私が以前いた戦略ファームでは…」「MBAのケーススタディで言うと…」と、過去の栄光をチラつかせることで、現在の発言の権威性を高めようとする。
- 議論の本質を忘れた「MECEになってない」警察 アイデアの斬新さや実現性よりも、分類の「漏れなく、ダブりなく」という形式的な正しさに異常に固執し、議論を停滞させる。
- 重箱の隅をつつくような「パワポ資料」のダメ出し 内容よりも、「フォントが違う」「インデントが1mmズレている」といった、資料の体裁に関する細かすぎる指摘で、相手の自信を削ぎ落とす。
- やたらと海外の成功事例を持ち出す 日本の市場環境や企業文化を無視して、「Googleでは」「Amazonでは」と海外の事例を持ち出し、自分がいかにグローバルな知見を持っているかをアピールする。
- 思考放棄の呪文「それはスコープ外です」 少しでも契約の範囲から外れそうな、しかし本質的な課題が見つかると、この言葉で思考をシャットダウン。クライアントの課題解決より、自分の仕事の範囲を守ることを優先する。
- 自分より若い、あるいは役職が下の社員を見下す態度 クライアント企業の若手社員からの真っ当な質問や意見を、「まだ若いね」とばかりに、鼻で笑うような態度を取る。
- クライアントそっちのけで、コンサル同士の白熱バトル クライアントの担当者がいるにもかかわらず、コンサルタント同士が高度な(ように見える)議論を始め、完全に内輪の空間を作り上げてしまう。
- 最終手段「そもそも、その問いは正しいのですか?」 議論に行き詰まると、論点をすり替えるために、課題設定そのものに疑問を呈し、議論を振り出しに戻す。
これらの行動の根底にあるのは、クライアントへの価値提供ではなく、「自分が、この場で最も優秀な人間である」と証明したい、という歪んだ欲求なのです。
なぜコンサルはマウントを取りたがるのか?3つの構造的・心理的背景
では、なぜ彼らは、これほどまでにマウント行為に走ってしまうのでしょうか。そこには、コンサルティング業界が抱える、構造的・心理的な3つの背景が存在します。
背景1:「Up or Out(昇進か、さもなくば去れ)」が生み出す過剰な生存競争
多くのコンサルティングファームには、「Up or Out」という厳しい人事文化が根付いています。一定期間内に昇進(Up)できなければ、会社を去る(Out)ことを暗に求められる。このシステムは、必然的に同僚を「仲間」ではなく「蹴落とすべきライバル」と見なす文化を醸成します。プロジェクトでいかに自分が優れているかを、上司や同僚にアピールし続けなければ、生き残れない。そのプレッシャーが、過剰なマウント行為となって現れるのです。
背景2:高すぎるプライドと「インポスター症候群」の奇妙な同居
高学歴で、難関の選考を突破してきたという自負は、彼らの高いプライドを形成します。しかし、その一方で、彼らの多くは「インポスター症候群」に苛まれています。これは、「自分は周囲が思っているほど優秀ではない」「いつか能力のなさがバレてしまうのではないか」という、根深い不安感です。この不安を隠し、自分を守るための防衛機制として、他人を攻撃・論破し、相対的に自分の優位性を確認しようとするのです。マウントは、彼らにとって心の鎧なのです。
背景3:クライアントより「社内評価」を気にする、悲しい力学
コンサルタントの評価や昇進を決めるのは、クライアントではありません。プロジェクトの責任者である、自社のパートナーやマネージャーです。そのため、彼らの関心は、「クライアントの課題が本当に解決するか」ということ以上に、「自分がこのプロジェクトで、いかに聡明で、価値のある働きをしたと、上司に評価されるか」という点に向かいがちです。クライアントの前で繰り広げられるマウント合戦は、実は上司に向けた、必死の「自分はデキます」アピールに他ならないのです。
データで見る、マウント合戦が会社をダメにする「3つの大罪」
この不毛なマウント合戦は、単に「感じが悪い」というだけでは済みません。それは、クライアント企業に着実に、そして深刻なダメージを与えていきます。
大罪1:【心理的安全性の破壊】による、チームの思考停止
Google社が、生産性の高いチームの共通点を探るために行った調査「プロジェクト・アリストテレス」で、チームの成功に最も重要な因子として結論づけられたのが「心理的安全性」です。「こんな初歩的な質問をしたら馬鹿にされるかも」「反対意見を言ったら、徹底的に論破されるかもしれない」。マウントが横行する会議では、まさにこの心理的安全性が徹底的に破壊されます。結果、クライアント企業の社員は萎縮し、自由な発言や、斬新なアイデアを口にしなくなり、チームは完全に思考停止状態に陥ります。
大罪2:【本質的でない議論】による、時間とコストの浪費
マウント合戦の目的は、「クライアントの課題を解決すること」ではなく、「議論の相手に勝利すること」です。そのため、議論は本質からどんどんズレていき、揚げ足取りや、言葉の定義の確認、形式的な正しさの証明といった、極めて生産性の低い活動に、膨大な時間と、高額なフィーが浪費されます。プロジェクトマネジメント協会(PMI)の調査でも、プロジェクト失敗の主要因として、常に「コミュニケーション不足」や「目的の不一致」が挙げられていますが、マウント合戦は、まさにこれを意図的に引き起こしているのです。
大罪3:【クライアントの当事者意識の剥奪】による、実行なき「絵に描いた餅」
コンサルタントが「我々が考えた、これが唯一の正解です」とばかりに、高圧的に戦略を押し付けてくると、クライアント企業の社員は、次第に「自分たちのプロジェクトだ」という当事者意識を失っていきます。「どうせ、あの高給取りのコンサルさんたちが、全部うまくやってくれるんでしょ」と、思考を停止し、完全な受け身姿勢になってしまうのです。結果、どんなに立派な分析や戦略が報告書にまとめられても、現場の社員がそれを「自分ごと」として実行に移すことはなく、プロジェクトは「絵に描いた餅」で終わります。
あなたの会社は大丈夫?「ダメなコンサル」を即座に見抜く5つの質問
では、私たちは、どうすれば自社を「ダメにするコンサル」から守ることができるのでしょうか。契約前や、プロジェクトの初期段階で、以下の5つの質問を投げかけてみてください。その反応で、彼らの本質が見えてきます。
- 「今の話を、私たちの社内で使われている言葉で、もう一度説明してもらえますか?」 → 良いコンサルは、相手の理解度に合わせて、専門用語を平易な言葉に翻訳して話せます。マウントコンサルは、難しい言葉を使うこと自体が目的化しているため、これができません。
- 「その素晴らしい計画の、うまくいかない可能性(リスク)は何だとお考えですか?」 → 良いコンサルは、成功の側面だけでなく、現実的なリスクやデメリットも正直に語り、その対策までをセットで考えます。マウントコンサルは、自分の提案の完璧さを主張することに固執します。
- 「この分野で、過去にどんな失敗をされましたか?そこから何を学びましたか?」 → 良いコンサルは、自らの失敗談をオープンに語り、そこからの学びを誠実に伝えられます。マウントコンサルは、自分の経歴に傷がつくことを恐れ、失敗を認めようとしません。
- 「もし、私たちの現場の意見が、その提案と正反対だった場合、どうしますか?」 → 良いコンサルは、「なるほど、なぜそう思われるのか、ぜひ詳しく聞かせてください」と対話しようとします。マウントコンサルは、「いや、データがこう示しているので、そちらが間違っています」と、意見を封殺しようとします。
- 「〇〇さん(現場の若手社員)の意見は、どう思われますか?」 → 良いコンサルは、役職や年齢に関係なく、すべての関係者の意見に真摯に耳を傾け、尊重する姿勢を示します。マウントコンサルは、自分より立場が下だと思う相手の意見を軽視する傾向があります。
まとめ:コンサルは「答えをくれる人」ではなく、「一緒に考えるパートナー」である
コンサルタントは、決して「魔法の杖」や「万能の答え」をくれる存在ではありません。もし、そう期待しているのだとすれば、それは発注する側にも問題があるのかもしれません。
これからの時代に本当に価値のあるコンサルタントとは、絶対的な正解を提示する「賢い人」ではなく、クライアント企業の社員一人ひとりの声に耳を傾け、対話を促し、組織が自ら答えを見つけ、自走していくための「触媒」や「伴走者」としての役割を担える人です。
彼らは、マウントを取って相手を支配するのではなく、相手をエンパワーメント(勇気づけ、力を与える)します。
私たち企業側も、コンサルタントに全てを丸投げするのではなく、主体的にプロジェクトに関わり、彼らを「先生」ではなく「対等なパートナー」として迎え入れ、健全な緊張感を持った関係性を築いていく努力が不可欠です。
高額なフィーを払って、社内の空気を悪くし、社員のやる気を削ぐ。そんな最悪の事態を避けるために、この記事が、皆さんの「コンサルタントを見る目」を養う一助となれば、幸いです。


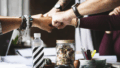
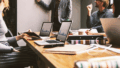
コメント