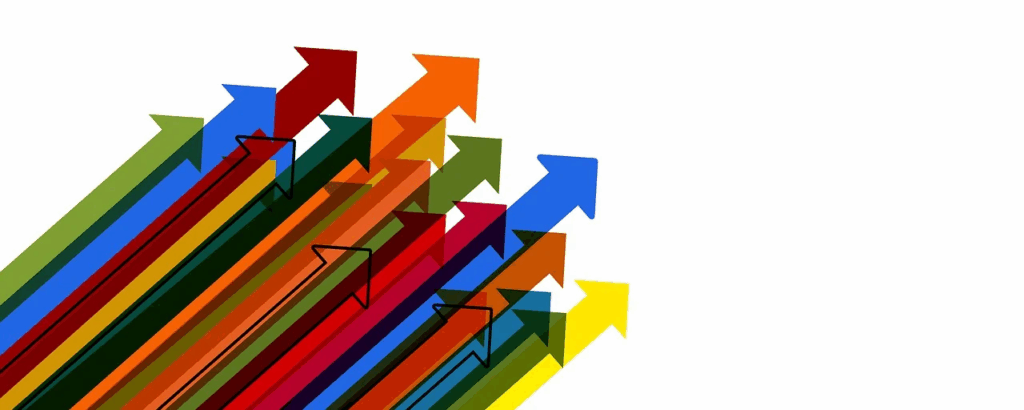
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 「新規開拓、もう限界だ…」と、コストと労力ばかりかかって成果が出ない状況に疲弊している経営者、営業責任者の方
- 既存のお客様との関係が、いつの間にか納品と世間話だけの「御用聞き」になってしまっていると感じる方
- お客様から「ちょっと検討します」と言われたまま、数ヶ月、あるいは1年以上も放置してしまっている案件が山ほどある方
- 過去に失注した案件に対して、「もう一度アプローチするのは気まずいな…」と、なんとなく避けてしまっている営業担当者の方
- SFAやCRM(顧客管理システム)を導入したはいいが、単なる営業報告ツールと化し、全く活用できていないと感じている方
もし、一つでも「うちの会社のことだ…」と胸に刺さるものがあれば、ぜひこのまま読み進めてください。
これは、多くの専門商社が抱える「新規開拓の壁」にぶち当たり、苦しんでいたA社が、視点を180度変えることで、社内に眠る“宝の山”を発見し、一人の営業担当者あたりの月間受注件数を3.5倍に引き上げた、嘘のような本当の物語です。
この記事を読み終える頃には、多大なコストをかけて新規顧客を追いかけるだけが営業ではないこと、そして、あなたの会社に今すぐ実践できる、売上アップの具体的なヒントが手に入っているはずです。
「新規はもう限界…」受注が頭打ちになった専門商社A社の苦悩
A社は、特定の産業で使われる精密機器を扱う、従業員50名ほどの専門商社。長年の実績と知識で、業界内では一目置かれる存在でした。しかし、近年、そのA社を大きな悩みが襲っていました。それは、「新規顧客からの受注が、ほとんど取れなくなってしまった」ことです。
市場は成熟し、競合も多数。インターネットで誰でも情報が手に入る時代、A社の強みだった専門知識だけでは、なかなかお客様の心を掴めなくなっていました。
営業チームの日常は、こんな感じです。
- 成果の出ないテレアポと飛び込み: 新しいリストに上から順に電話をかけ続ける毎日。受付で断られるのは当たり前。運良く担当者に繋がっても、「間に合ってます」「今は考えてません」の一言で終了。チーム全体が、先の見えない新規開拓に疲弊しきっていました。
- 「御用聞き」と化す既存顧客への訪問: 一方で、長年付き合いのある既存のお客様への訪問は、新製品の納品や、定期メンテナンスの案内が中心。「何か変わりないですか?」と聞くだけの、完全な御用聞きスタイル。新しい提案をするきっかけも、時間的・精神的な余裕もありませんでした。
A社の経営陣は「とにかく新規だ!新しいお客様を見つけろ!」と檄を飛ばし続けます。しかし、現場の疲弊とは裏腹に、成果は一向に上がりませんでした。
実はこの状況、多くの企業が陥る典型的なパターンなのです。マーケティングの世界には、有名な2つの法則があります。
- 「1:5の法則」: 新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかる。
- 「5:25の法則」: 顧客離れを5%改善すれば、利益が最低でも25%改善される。
A社は、この法則とは真逆の、最もコストがかかり、最も効率の悪い営業活動に、会社のリソースを注ぎ込み続けていたのです。
売上の鉱脈は社内にあった?「死蔵案件」という名の宝の山
営業会議で、重い空気が流れるある日のこと。営業部長のBさんは、ふと、自社で導入しているSFA(営業支援ツール)の過去のデータに目をやりました。そこには、この数年間で営業担当者たちが入力してきた、膨大な商談履歴が眠っていました。
Bさんは、そのデータを見ていて、ある事実に気づき、愕然とします。 それは、「受注にも失注にもならず、放置されている案件」が、あまりにも多すぎることでした。
私たちは、こうした案件を「死蔵(しぞう)案件」と呼んでいます。具体的には、以下のようなものです。
- 「検討します」案件: 見積もりを提出し、「前向きに検討します」と言われたきり、フォローされないまま数ヶ月が経過している。
- 「タイミング待ち」案件: 「来期の予算が取れたら…」「担当者が変わったら…」と言われ、ペンディングになっている。
- 「惜敗」案件: 最終選考まで残ったが、価格やわずかな仕様の差で競合に負けてしまった。
- 「休眠顧客」案件: 数年前に大きな取引があったが、担当者の引き継ぎミスなどで、今は全く関係が途切れてしまっている。
A社では、こうした「死蔵案件」が、SFA上で確認できるだけでも年間100件以上も存在していました。これは、まさに手つかずのまま放置された「宝の山」です。なぜ、こんなにも多くのチャンスが見過ごされていたのでしょうか。理由は、営業担当者なら誰でも思い当たる、シンプルなものでした。
「日々の業務が忙しくて、過去の案件まで手が回らない」 「一度断られた相手に、またアプローチするのはなんとなく気まずい…」 「どうせもう決まっているだろう、今さら連絡しても迷惑なだけだ」
こうした、ささいな思い込みや心理的なハードルが、大きな機会損失を生み出していたのです。
劇的改善の秘訣!「死蔵案件」を蘇らせる3ステップ再提案術
「この宝の山を、このまま眠らせておくわけにはいかない!」 B部長は、すぐにチームメンバーを集め、新しい方針を打ち出しました。それは、「新規開拓に使う時間の半分を、死蔵案件の掘り起こしに充てる」という、大胆な戦略転換でした。
そして、私たちがサポート役として入り、構築したのが、誰でも実践できる「3ステップ再提案術」です。
ステップ1:案件の「棚卸し」と「戦略的格付け」
まず、SFAや過去の見積もりファイルから、この2年間で「死蔵」状態になっている案件を、すべてリストアップしました。そして、それらを一枚のスプレッドシートにまとめ、以下の基準で「格付け」を行いました。
- Aランク(今すぐアプローチすべき): 失注理由が「タイミング」や「予算」だった案件。顧客の状況さえ変われば、成約の可能性が非常に高い。
- Bランク(情報提供から始める): 価格や機能で競合に負けた案件。すぐに覆すのは難しいが、新製品や代替案を情報提供することで、関係を再構築できる可能性がある。
- Cランク(長期的なアプローチ): 顧客のニーズそのものが消滅した案件。今は動かないが、市場動向などを定期的に連絡し、忘れられないようにしておく。
この「棚卸し」と「格付け」によって、闇雲にアプローチするのではなく、どこから手をつければ最も効果的かが、一目瞭然になったのです。
ステップ2:相手に喜ばれる「再アプローチの口実」を作る
格付けができたら、次はいよいよアプローチです。しかし、いきなり電話して「あの件、その後どうなりましたか?」と聞くのは、最もやってはいけないNG行動です。相手に「ああ、営業の電話か…」と警戒されてしまいます。
重要なのは、相手にとって「聞いておいて損はないな」と思えるような、有益な情報提供を「口実」にすることです。
私たちがA社と考案した「口実」の例:
- 新情報提供タイプ: 「〇〇様が以前ご検討されていた製品の後継機が、このたび発売されました。性能が格段にアップしていますので、参考情報としてだけでもお送りしてよろしいでしょうか?」
- 事例紹介タイプ: 「最近、〇〇様の同業であるB社様で、以前ご提案したあの製品を導入いただき、生産性が30%向上したという事例が出まして。ご興味があれば、簡単にご紹介させていただけませんか?」
- キャンペーンタイプ: 「〇〇様からお見積もりをいただいていた製品ですが、今月末までの期間限定で、特別なキャンペーン価格をご用意できることになりました。もしご検討が再開されるようでしたらと思いまして」
この「口実」があるだけで、営業電話は「売り込み」から「有益な情報提供」へと変わり、相手の心理的な壁をぐっと下げることができます。
ステップ3:「タイミングの変化」を捉えて、的確に再提案する
顧客を取り巻く環境は、常に変化しています。私たちはこれを「タイミングの変化」と呼んでいます。
- 担当者が変わった
- 使っている競合製品に、不満やトラブルが出始めた
- 会社の経営方針が変わり、新しい課題が生まれた
- 新年度になり、新しい予算が組まれた
ステップ2の情報提供を通じて、顧客との接点を持ち続けることで、こうした「タイミングの変化」のサインをいち早くキャッチすることができます。そして、「今だ!」という絶好のタイミングで、顧客の新しい課題に寄り添った再提案を行うのです。一度関係性ができているため、その提案は、初対面の新規営業とは比べ物にならないほど、深く、鋭く、相手の心に突き刺さります。
月2本→月7本へ!再提案術がA社にもたらした3つのポジティブな変化
この「3ステップ再提案術」をチーム全体で実践した結果、A社には驚くべき変化が訪れました。
変化1:営業成果の劇的な向上(受注数3.5倍) これまで、営業担当者一人が月に獲得する受注件数は、平均して2.1本でした。それが、この取り組みを始めてから3ヶ月後には、平均7.3本にまで増加したのです。死蔵案件は、一度提案しているため顧客の課題を把握しており、関係性もゼロではないため、新規開拓に比べて成約率が5倍以上に跳ね上がりました。
変化2:疲弊から「宝探し」へ。営業チームのモチベーション革命 成果の出ない新規開拓に疲弊していたチームの雰囲気が、一変しました。「SFAのデータを見ていたら、こんなお宝案件を見つけました!」「Bランクだったお客様から、後継機の問い合わせが来ました!」といった、ポジティブな報告が飛び交うようになったのです。成果が目に見えて出る「宝探し」のような感覚が、チームに活気と自信を取り戻させました。
変化3:顧客との関係深化と「LTV」の最大化 再アプローチは、顧客に「うちのことを忘れずに、気にかけてくれていたんだな」というポジティブな印象を与えます。これにより、単なる「業者」から、課題を一緒に解決してくれる「信頼できるパートナー」へと、関係性が深化しました。結果、一度の取引で終わらず、追加の受注や、別部署の紹介に繋がるケースも増加。顧客一人ひとりが生涯にわたって企業にもたらす利益(LTV:顧客生涯価値)が、格段に向上したのです。
あなたの会社の「宝の山」を見つける、はじめの一歩
A社の話は、決して特別な成功物語ではありません。あなたの会社にも、SFA、Excelの見積もり管理表、あるいは担当者の引き出しの中に、手つかずの「死蔵案件」が必ず眠っています。
まずは、その存在に気づくことが、はじめの一歩です。 しかし、いざやろうとすると、「データが整理されていなくて、どこから手をつけたら…」「うちの商材に合った、うまいアプローチの口実が思いつかない」「日々の業務に追われて、結局後回しになってしまう」といった、新たな壁にぶつかるかもしれません。
そんな時こそ、私たちのような外部の専門家を頼ってください。
新規開拓という「狩り」から、既存顧客を育てる「農耕」へ
これからの時代の営業は、常に新しい獲物を追いかけ続ける、消耗戦のような「狩猟型」のスタイルだけでは、立ち行かなくなります。 一度繋がったお客様という畑を、丁寧に耕し、適切なタイミングで水や肥料(情報提供)を与え、より大きな果実を、繰り返し収穫する。そんな「農耕型」の視点を持つことが、企業の持続的な成長には不可欠です。
あなたの会社に眠っている「死蔵案件」という名の広大な畑。 その発掘から、耕し方、そして収穫まで、私たちが専門家の知識と経験で、全面的にサポートします。
「うちの会社には、どれくらいのお宝が眠っているんだろう?」 まずは、そんな興味本位からで構いません。無料の「案件棚卸し相談」で、あなたの会社の可能性を一緒に探ってみませんか?


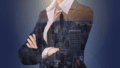

コメント