
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- マーケティングが頑張ってリードを取っても、営業がなかなかフォローしてくれないとお悩みの担当者の方
- 営業から「最近のリードは質が低い」と文句を言われ、両者の板挟みになっているマネージャーの方
- リードが商談になる確率(商談化率)が低く、その原因もよく分かっていない方
- 営業とマーケティングの会議が、ただの数字報告会や責任のなすりつけ合いで終わっている経営者の方
- 場当たり的な改善ではなく、継続的に成果を出し続ける「仕組み」を会社に導入したいと考えている方
Webからの問い合わせ(リード)が増えてきた!これは喜ばしいことですが、本当の戦いは、実はここから始まります。せっかく獲得したリードも、その後のフォロー体制が整っていなければ、まるで穴の空いたバケツの水のように、商談や受注に至る前にどんどん漏れ落ちていってしまいます。多くの企業が、リードを「獲得すること」に躍起になりますが、その裏側で、価値ある見込み客が誰にも気づかれず”塩漬け”になっているとしたら、これほどもったいないことはありません。この致命的な「漏れ」を防ぎ、一つひとつのリードの価値を最大化する鍵。それが、営業とマーケティングが一体となって回す「週次運用」のサイクルです。この記事では、リードの商談化率の低迷に悩んでいたA社が、たった一つの「週次定例会」を軸にした運用ロードマップを導入し、どのようにして両部門の壁を壊し、最終的な受注数を倍増させたのか。その具体的な会議のアジェンダまで、余すところなく全公開します。
「宝の山」か「ゴミの山」か?獲得したリードが”塩漬け”になる恐怖
今回ご紹介するA社は、ABM(アカウントベースドマーケティング)の導入に成功し、ターゲットとなる優良企業からの質の高いリードを、安定的に獲得できるようになっていました。マーケティング部は「これだけ質の高いリードを渡しているのだから、売上も上がるはずだ」と期待に胸を膨らませていました。
しかし、3ヶ月経っても、受注数は思ったように伸びていきません。いったい、何が起きているのか? A社の社長が、営業支援ツール(SFA)の中身を詳しく見てみると、そこには愕然とする光景が広がっていました。
- リードの大量”塩漬け”: マーケティング部から営業部に引き渡されたリードのうち、約40%が、誰にも一度もフォローされないまま、ツールの中で眠っていたのです。
- フォローの属人化と短期化: フォローされているリードも、その対応は完全に営業担当者任せ。一度電話して繋がらなかったら、そのまま放置されているケースが多数見受けられました。
- フィードバックなき断絶: 営業担当者は、なぜそのリードをフォローしないのか、なぜ商談に至らなかったのかを、一切マーケティング部にフィードバックしていません。一方、マーケティング部は、営業がなぜ動いてくれないのか分からず、不満だけが募っていきます。
これは、まさに「宝の山」になるはずだったリードが、誰にも見向きもされずに「ゴミの山」へと変わっていく、恐ろしい瞬間でした。
世界的に有名な調査「The Lead Response Management Study」によれば、リード発生から5分以内に連絡した場合と、30分後に連絡した場合とでは、その後の商談に繋がる確率が実に21倍も違う、というデータがあります。リードへの対応速度は、成果に直結するのです。A社で起きていたリードの”塩漬け”は、毎日、毎時間、莫大な機会損失を生み出し続けていました。
問題は”部門”じゃない。”プロセス”にある。全てのカギは「週次定例」
この状況を知ったA社の社長は、当初「営業担当者の怠慢だ!」と憤慨しました。しかし、問題の根っこは、もっと別のところにありました。
営業担当者に話を聞くと、「日々の既存顧客の対応で手一杯で、新規リードにまで手が回らない」「マーケから送られてくる情報だけでは、どんなお客様か分からず、電話しづらい」といった、切実な声が上がってきました。
これは、営業担当者個人の問題ではありません。マーケティング部がリードを獲得してから、営業部が受注するまでの「プロセス」に、情報や想いがスムーズに流れるための”パイプ”が詰まってしまっている、という構造的な問題だったのです。
では、どうすれば、この詰まりを取り除き、サラサラと流れるパイプを再構築できるのか? A社がたどり着いた答えは、非常にシンプルでした。それは、営業とマーケティングの主要メンバーが参加する「週次定例会」を設置することです。
ただし、この会議は、過去の失敗を責めたり、責任をなすりつけ合ったりする場ではありません。 お互いの専門知識と現場感覚を持ち寄り、今、目の前にいる一人ひとりのお客様を、「リード」から「商談」、そして「受注」へと、チーム一丸となって引き上げていくための”作戦会議”です。
ある調査では、営業とマーケティングの連携(セールス&マーケティング アライメント)が緊密な企業は、そうでない企業に比べて、年間収益成長率が平均で20%以上も高い、という結果が出ています。週に一度、たった60分の会議が、会社の未来を大きく変えるエンジンになり得るのです。
これが成果を生む会議のすべて。週次運用ロードマップ(アジェンダ編)
A社は、毎週月曜日の朝9時から60分間、営業部長、マーケティング部長、そしてそれぞれの現場担当者が参加する「週次定例会」をスタートしました。会議の生産性を最大化するため、事前に明確なロードマップ、すなわち「アジェンダ」を定めています。
【最初の10分】数字の共通言語化:KGI/KPIの定点観測 全員が同じデータを見て、現状を客観的に把握する時間。
【次の20分】顧客の解像度UP:注目リードのレビュー 数字の裏側にいる「個」客にフォーカスし、血の通った情報を共有する時間。
【続く20分】未来のアクション設計:施策の振り返りと計画 過去の学びを、未来の具体的な行動へと転換する時間。
【最後の10分】課題の共有と解決:ボトルネックの特定と対策 部門間の「詰まり」を発見し、解消するための方策を議論する時間。
この4つのアジェンダを、決められた時間通りに、毎週淡々と繰り返す。この”リズム”こそが、場当たり的ではない、継続的な改善の文化を組織に根付かせる鍵となります。それでは、各アジェンダで、具体的に何が行われたのかを見ていきましょう。
アジェンダ①(10分):数字で語る。感情論を排除し、事実を見る
会議の冒頭、ファシリテーター役のマーケティング部長が、全員に共有されたダッシュボードをスクリーンに映し出します。そこには、先週一週間の主要なKPI(重要業績評価指標)が、グラフで分かりやすく可視化されています。
【A社の週次ダッシュボード(例)】
- リード獲得数: 15件(広告経由:5件, SEO経由:10件)
- 商談化数(MQL→SQL): 3件
- 商談化率: 20%(目標:25%)
- 受注数: 1件
- 受注率: 33%
- 平均受注単価: 500万円
ここで最も重要なルールは、「この場で、数字の良し悪しについて、個人を責めないこと」です。 「おい営業部、商談化率が目標に達してないじゃないか!」といった吊し上げが始まった瞬間に、その会議は機能不全に陥ります。
司会進行役は、ただ事実を読み上げます。「先週の商談化率は20%で、目標に対してマイナス5ポイントでした。この事実について、次のアジェンダで少し深掘りしてみましょう」。
この10分間は、感情や憶測を挟まず、全員が「今、私たちの船は、どの位置にいて、どちらの方向に向かっているのか」という事実を、共通言語である”数字”を通して冷静に確認するための、大切な儀式なのです。
アジェンダ②(20分):”個”客を語る。一人の顧客を深く知る
数字の確認が終わると、会議は一転して、非常に人間味のある時間へと移ります。この20分間が、A社の週次定例会のまさに心臓部です。
マーケティング担当者が、先週獲得したリードの中から、特に注目すべきリードを3件ほどピックアップし、その背景を説明します。
マーケ担当者: 「まず1件目、B社の佐藤様です。佐藤様は、弊社の『〇〇業界のDX事例』というブログ記事を検索で見つけ、その後、『△△導入のためのROIシミュレーション』というホワイトペーパーをダウンロードされています。おそらく、コスト削減と生産性向上に強い課題意識をお持ちだと推測されます」
これを受けて、実際に佐藤様と話をした営業担当者が、現場の情報を加えます。
営業担当者: 「はい、佐藤様とは昨日お話ししました。マーケさんの分析通り、コスト削減が一番の関心事でした。ただ、話してみると、最終的な決裁権は佐藤様の上司である、C部長が握っていることが分かりました。C部長は、コストよりも『セキュリティ面の安全性』を重視するタイプだという、貴重な情報も得られました」
この会話、いかがでしょうか。 マーケティング部は、「ROI」というキーワードでアプローチした顧客の、真のニーズが「セキュリティ」にあることを知ることができます。一方、営業部は、単なるリードの情報ではなく、「佐藤様」という一人の人間が、どんな背景や課題を持っているのかを深く理解した上で、次のアクションを考えられるようになります。
このように、注目すべき顧客(商談化/失注/塩漬けなど)について、数珠繋ぎで情報を交換していくことで、顧客の解像度が飛躍的に高まります。これは、営業とマーケの間に、最強の”顧客カルテ”がリアルタイムで共有されていくようなものです。
アジェンダ③&④(30分):行動を語る。次の”一手”を決める
顧客の解像度が高まったところで、会議は最後の30分、未来志向のアクション設計へと進みます。
まず、【施策の振り返りと計画】の時間です。アジェンダ②での学びを、具体的な”次のアクション”に落とし込みます。
マーケティング部長: 「なるほど、B社のC部長はセキュリティを重視する、と。では、来週、C部長個人をターゲットにして、『金融機関も採用する、弊社の強固なセキュリティ体制』という内容のメールと広告を配信してみるのはどうだろう?」
営業部長: 「それは良いね。その配信の2日後に、うちの担当者から『セキュリティに関する新しい資料をお送りしました』という流れで、C部長に直接アプローチをかけてみよう」
このように、その場で具体的な「誰が」「何を」「いつまでに」やるのかを決めていきます。
そして最後の10分は、【ボトルネックの共有と解決】の時間です。より大きな、組織的な課題について議論します。
営業担当者: 「正直なところ、リードをいただいてから、初回のご連絡をするまでに平均で2日かかってしまっています。日中の外出が多くて、なかなか時間が取れず…」
これに対し、社長や両部長が解決策を考えます。
社長: 「なるほど。それは個人の問題ではないな。試験的に、リードへの一次対応(電話やメール)を専門に行うインサイドセールスチームを、来月から1名体制で立ち上げてみてはどうだろうか。営業担当は、アポが取れた商談に集中できるようにしよう」
このように、週次定例会は、日々の戦術的な改善だけでなく、会社の仕組みそのものを変えていく、戦略的な場へと進化していくのです。
A社では、この週次運用を3ヶ月間、愚直に続けた結果、驚くべき成果が生まれました。リードの”塩漬け”はほぼゼロになり、商談化率は15%から30%へと倍増。それに伴い、最終的な月間受注数も、以前の2.2倍を記録したのです。
あなたの会社の「月曜の朝」、変えてみませんか?
A社の物語は、特別な成功事例ではありません。それは、正しい「仕組み」を、正しい「リズム」で、ただ愚直に続けた結果です。リードから受注までのプロセスは、一度作って終わり、ではありません。顧客も、市場も、常に変化しています。その変化に対応し続けるためには、毎週、毎週、プロセスの”チューニング”を続けていく必要があるのです。
そのチューニングの場こそが、営業とマーケティングがONE TEAMとなる「週次定例会」です。
あなたの会社の月曜の朝は、どんな時間でしょうか? どんよりとした空気の中、先週の反省会から始まってはいませんか?
その時間を、未来を創るための、エキサイティングな作戦会議に変えることができます。
- 「うちの会社の”ザル”の穴が、いったいどこにあるのか、客観的に診断してほしい」
- 「最初の1回だけでいい。成果に繋がる”週次定例会”の進め方を、ファシリテーターとして伴走してほしい」
- 「この記事で紹介された週次運用ロードマップを、うちの会社に最適化した形で導入するのを手伝ってほしい」
どんなご相談でも構いません。 まずは、あなたの会社の「月曜の朝」を変えることから、一緒に始めてみませんか?たった60分の会議が、あなたの会社の未来を、大きく変えるかもしれません。


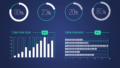

コメント