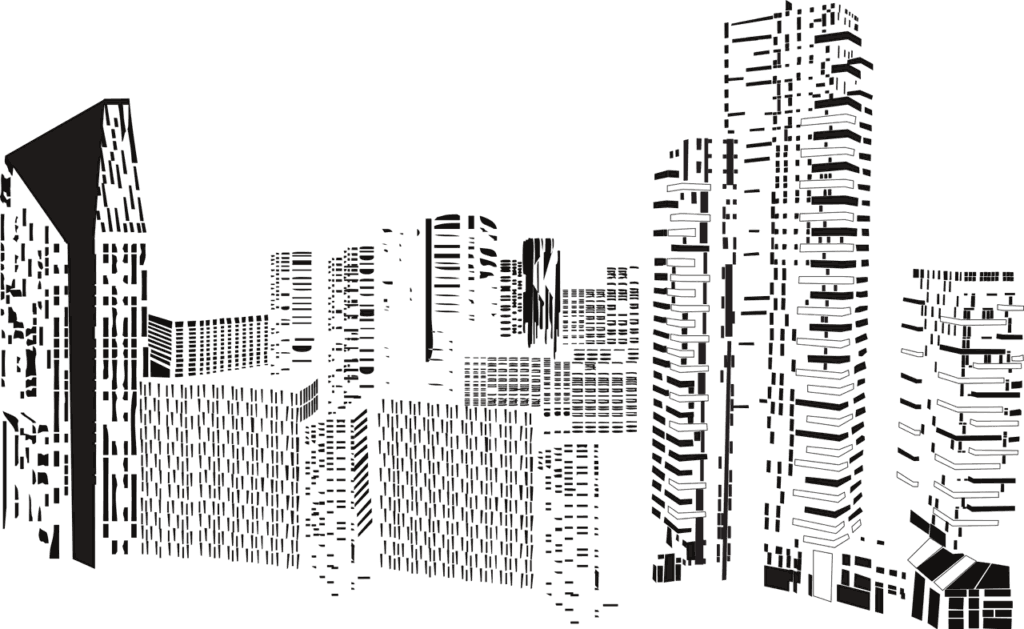
【この記事はこんな方に向けて書いています】
✅ 担当しているプロジェクトの進捗が思わしくなく、焦っているプロジェクトマネージャーの方
✅ 「順調です」という報告は受けるものの、実態がよく見えず不安な経営者・役員の方
✅ 仕様変更や手戻りが頻発し、メンバーが疲弊しているのを感じているリーダーの方
✅ ベンダーとのコミュニケーションがうまくいかず、会議が紛糾しがちな方
✅ 過去にプロジェクトの遅延や失敗で、苦い経験をしたことがある方
「このプロジェクトは絶対に成功させるぞ!」
固い決意でスタートしたはずのITシステム導入プロジェクト。最初の数ヶ月は計画通りに進んでいたのに、気づけば、報告される進捗はいつも「90%完了」のまま。会議は増える一方なのに、何も決まらない。現場からは不満の声が聞こえ始め、ベンダーとの関係もどこかギクシャクしている…。
これは、決して特別な話ではありません。多くのプロジェクトが、このような「炎上」と呼ばれる危機的状況に陥るリスクを抱えています。ある調査では、ITプロジェクトの約7割が、当初の予算や納期を守れていないというデータもあるほどです。
しかし、もしその炎上の本当の原因が、メンバーの能力不足や、ベンダーの怠慢ではなく、誰も気づいていない「隠れた構造的問題」にあるとしたら?
本記事では、まさに炎上の真っ只中にあった中小企業C社が、外部のPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)の支援を受けることで、どのようにして遅延の根本原因を突き止め、プロジェクトを奇跡的なV字回復へと導いたのか、その一部始終をリアルな事例としてご紹介します。「もうダメかもしれない…」と諦めかける前に、ぜひ読んでみてください。
なぜプロジェクトは「炎上」するのか?見えていない本当の原因
そもそも、なぜ順調だったはずのプロジェクトが、突然コントロール不能な「炎上」状態に陥ってしまうのでしょうか。その兆候は、じわじわと現れます。
プロジェクトで問題として表面化するのは、以下のような事象です。
| 表面的な問題(症状) | その裏で起こっていること |
| 納期遅延 | タスクの依存関係が考慮されておらず、一つの遅れが全体に波及している。 |
| 品質の低下 | 度重なる仕様変更で、テストが不十分なままリリースを急いでいる。 |
| 予算超過 | 手戻り作業が多発し、追加の開発工数や人件費が膨らんでいる。 |
| チームの疲弊 | ゴールが見えないまま深夜残業が続き、メンバーの士気が低下している。 |
これらは、いわばプロジェクトという病気における「咳」や「熱」のような症状にすぎません。本当に治すべきは、その症状を引き起こしている病原菌、つまり「根本原因」です。
多くの炎上プロジェクトでは、この根本原因に誰も気づかないまま、「もっと頑張れ」「コミュニケーションを密に」といった精神論や、場当たり的な対策に終始してしまいます。その結果、さらに状況を悪化させてしまうのです。C社のプロジェクトも、まさにその典型でした。
【事例】終わりが見えない…C社の基幹システム刷新プロジェクト
C社は、急成長を続けるサービス業の企業です。事業拡大に伴い、既存の業務システムでは限界が見え始め、満を持して基幹システムの全面刷新プロジェクトをスタートさせました。
プロジェクトマネージャーには、エース社員のCさんが任命され、実績豊富なITベンダーも選定。経営陣の期待も高く、プロジェクトは順風満帆に滑り出したかに見えました。
忍び寄る「炎上」の影
しかし、開発フェーズが中盤に差し掛かった頃から、プロジェクトの歯車が狂い始めます。
- 進まない課題: 週次の定例会では、毎週同じ課題が「継続検討」として残り続ける。
- 終わらないレビュー: 現場担当者からの仕様確認のレビューが、いつまで経っても終わらない。「もっとこうしてほしい」という要望が後から後から出てきて、手戻りが頻発。
- 責任のなすりつけ合い: 「これはベンダーの提案が悪い」「いや、要件をきちんと固めないC社側に問題がある」と、社内とベンダーの間で責任の押し付け合いが始まる。
プロジェクトマネージャーのCさんは、連日深夜まで対応に追われました。山積みの課題を整理し、各所への根回しに奔走し、疲労困憊の状態。それでも、経営陣への報告では「少し遅れていますが、来月には挽回できます」と説明するしかありませんでした。しかし、内心では「もう、何から手をつければいいのか分からない…」と、途方に暮れていたのです。
状況を憂慮した社長は、ある決断をします。「外部の専門家の目で、このプロジェクトを客観的に診断してもらおう」。それが、PMO支援を導入するきっかけでした。
PMOは何をしたのか?「火消し」ではなく「原因究明」
C社からのSOSを受け、私たちPMOがまず取り組んだのは、燃え盛る炎に水をかけるような「場当たり的な火消し」ではありません。なぜ火事が起きたのかを冷静に分析する「原因究明」でした。
ステップ1:徹底した客観的な「見える化」 私たちは、まず利害関係のない第三者の立場で、プロジェクトに関するあらゆる情報を収集・整理しました。
- ドキュメントの棚卸し: プロジェクト計画書、課題管理表、議事録など、すべての資料を読み解き、矛盾点や抜け漏れを洗い出す。
- 全関係者へのヒアリング: Cさんや経営陣はもちろん、現場の担当者、そしてベンダー側のプロジェクトマネージャーやエンジニアにも、個別に(そして内密に)ヒアリングを実施。「本当は何に困っているのか」という本音を引き出しました。
ヒアリングと資料分析から見えてきたのは、C社の「コミュニケーションと意思決定の構造」に関する、深刻な問題でした。それを一枚の図に整理して、C社の経営陣に見せました。
そこには、誰が、誰に、何を報告し、最終的に誰が決定するのか、その流れがまるでスパゲッティのように絡み合った図がありました。
ステップ2:隠れたボトルネックの特定 分析を進める中で、私たちは一つの「奇妙な点」に気づきました。プロジェクトの遅延原因となっていたほとんどの課題が、最終的に「A部長の承認待ち」で止まっていたのです。
A部長は、非常に優秀で責任感の強い方でしたが、担当役員でもあるため多忙を極めていました。現場から上がってくる仕様に関する細かな質問事項や、ベンダーからの技術的な提案も、すべてA部長が一人でチェックし、承認しなければならないルールになっていたのです。
しかし、A部長は多忙なため、それらの確認事項に目を通す時間がなく、どんどん後回しに。その結果、A部長のデスクの上が、プロジェクト全体の巨大なボトルネックとなっていたのです。
現場もベンダーも、Cさんも、そしてA部長自身でさえ、この「承認プロセス」こそがプロジェクトを麻痺させている根本原因だとは、誰一人として気づいていませんでした。みんな、「A部長が忙しいのは仕方ない」と思い込んでいたのです。
ステップ3:具体的な解決策の提示と実行支援 原因が特定できれば、あとは処方箋を出すだけです。私たちはC社に、以下の2つの具体的な改善策を提案し、その実行をサポートしました。
- 意思決定ルールの再定義:
- 影響の少ない軽微な仕様変更は、A部長ではなく、プロジェクトマネージャーであるCさんの権限で即決できるようルールを変更。
- 一定金額以上のコスト増や、納期に大きく影響する重要な判断のみ、A部長が参加する週1回30分の「プロジェクト意思決定会議」で必ず結論を出す、という場を新設。
- コミュニケーションハブとしての機能:
- 私たちPMOが「コミュニケーションハブ」となり、現場からの質問やベンダーからの相談事項を、事前に論点を整理し、判断材料を揃えた上で意思決定者にインプットする役割を担う。
最初は「そんなことで変わるのか?」と半信半疑だったC社のメンバーも、この新しいルールを運用し始めると、プロジェクトの流れが劇的に変わったことに驚きました。
炎上プロジェクトがV字回復を遂げた3つの理由
滞っていた承認がスムーズに進み始めると、嘘のように課題が次々と解決されていきました。C社のプロジェクトがV字回復を遂げたのには、PMOが入ったことによる3つの明確な理由があります。
理由1:中立な「交通整理役」の存在 社内の人間でもなく、ベンダーの人間でもない、「プロジェクトの成功」だけをミッションとする中立な第三者がいることで、感情的な対立がなくなりました。「誰が悪いか」ではなく、「どうすればプロジェクトが前に進むか」という建設的な議論ができるようになったのです。
理由2:「作業」ではなく「管理」への集中 これまでCさんは、課題解決という「作業」に追われ、プロジェクト全体を俯瞰して「管理」する時間を奪われていました。PMOが課題管理や進捗管理といった煩雑なマネジメント業務を巻き取ることで、Cさんは本来の役割である現場とベンダーの調整に集中できるようになりました。
理由3:明確な「ルール」の再設定 炎上するプロジェクトに共通しているのは、コミュニケーションや意思決定に関する「暗黙の了解」や「属人的な頑張り」に頼っている点です。PMOは、誰が見ても分かる客観的で明確なルールを再設定しました。これにより、特定の人に負荷が集中することなく、組織としてプロジェクトを推進する体制が整ったのです。
C社が得たのは、納期だけではなかった
PMOの支援開始から3ヶ月後、C社のプロジェクトは完全に正常な軌道に戻りました。当初の計画からは2ヶ月の遅延となりましたが、もしあのまま放置していれば、半年以上の遅延、最悪の場合はプロジェクト中止という事態も考えられたため、経営陣は胸をなでおろしました。
しかし、C社がこの経験から得たのは、完成した新システムと、守られた納期だけではありません。
- プロジェクト推進ノウハウの蓄積: Cさんをはじめ、プロジェクトメンバーは、今回の経験を通じて正しいプロジェクトマネジメントの手法を学びました。
- ベンダーとの良好な関係再構築: 共通の敵(課題)に共に立ち向かったことで、ベンダーは単なる外注先ではなく、信頼できるパートナーへと変わりました。
- 組織としての成長: C社には、「問題が起きた時は、根本原因を突き止め、仕組みで解決する」という文化が根付きました。
これは、今後のC社の成長にとって、新しいシステム以上に価値のある財産となったのです。
「もうダメかも…」その時が、外部の力を頼るサインです
もし今、あなたがCさんと同じように、出口の見えないトンネルの中で一人で戦っているとしたら。あるいは、自社のプロジェクトの進捗に、漠然とした不安を感じているとしたら。
その「何かおかしい」という感覚は、多くの場合、正しいものです。そして、その違和感の正体は、プロジェクトの内部にいる当事者だけでは、なかなか見つけられないものです。
プロジェクトが炎上してからでは、鎮火にかかるコストも時間も甚大になります。少しでも「おかしいな」と感じたなら、それはプロジェクトの健康診断を受けるべきサインです。
私たちは、いきなり大規模なコンサルティング契約を結ぶようなことはしません。まずは、あなたのプロジェクトが今どのような状況にあるのか、何に困っているのか、お話をお聞かせいただくことから始めます。客観的な第三者の視点が入るだけで、見えてくる景色がきっとあるはずです。
「もうダメかもしれない」と諦めてしまう前に、一度、私たちに相談してみませんか?

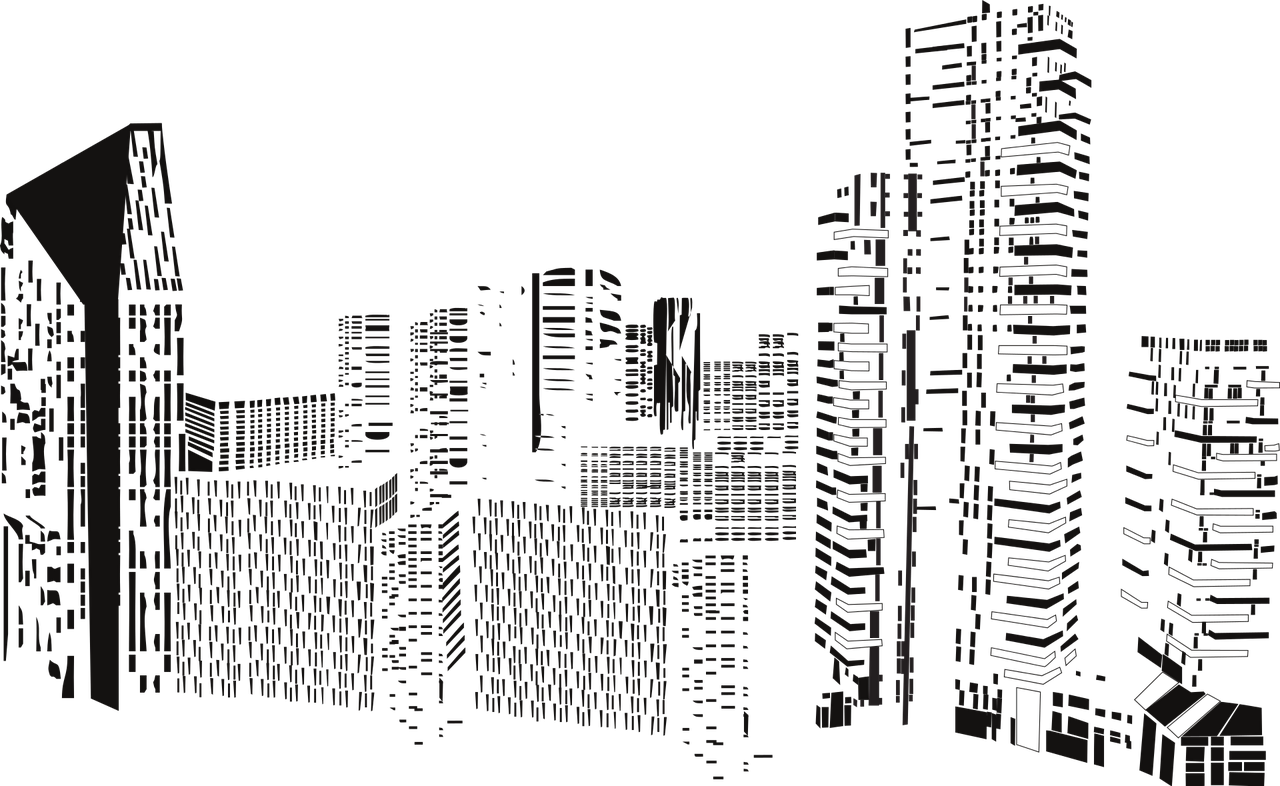

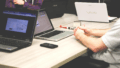
コメント