
【この記事はこんな方に向けて書いています】
✅ 「これからは内製化だ」という風潮に、少し焦りを感じている経営者の方
✅ ITの内製化を目指してエンジニアを採用したものの、プロジェクトがうまく進んでいない担当者の方
✅ 自社のIT部門の本当の実力や課題を、客観的に把握したいと考えている方
✅ IT戦略を立てる上で、「外部委託」と「内製化」の最適なバランスを知りたい方
✅ IT部門が日々の運用に追われ、戦略的な動きができていないことに課題を感じている方
「ベンダーに頼りきりでは、変化のスピードについていけない」 「自分たちでシステムを作れるようになれば、コストも下がるし、自由度も上がるはずだ」
近年、多くの企業で「ITの内製化」が重要な経営テーマとして掲げられています。確かに、内製化にはコスト削減や開発スピードの向上など、多くのメリットが期待できます。しかし、その一方で、自社の実力を正しく見極めないまま内製化の道へ進み、「こんなはずではなかった…」と頭を抱える企業が後を絶たないのも、また事実です。
ある調査によれば、中小企業において「IT人材が大幅に不足している」と回答した企業は8割以上にのぼります。この深刻な人材不足という現実から目を背け、「内製化」という言葉の響きだけで突き進んでしまうと、どうなるのでしょうか?
本記事では、「自分たちでできるはず」という思い込みから内製化プロジェクトをスタートさせ、気づけば座礁寸前の危機に陥っていたE社の事例をご紹介します。外部の専門家による「IT組織アセスメント(組織診断)」を通じて、彼らがどのようにして自社の本当の実力を知り、戦略的な方向転換に成功したのか。そのリアルな道のりを追体験することで、あなたの会社のIT戦略を見つめ直すきっかけを提供します。
なぜ多くの企業が「内製化」の罠に陥るのか?
そもそも、なぜ多くの企業が「内製化」という魅力的な言葉に惹きつけられ、そして罠に陥ってしまうのでしょうか。その背景には、内製化への過度な期待と、それに伴うリスクの軽視があります。
内製化に期待されるメリット(理想)
- コスト削減: 外部ベンダーに支払う費用がなくなる。
- スピード向上: 社内で要件を決め、すぐに開発に着手できる。
- ノウハウ蓄積: 社内に技術や業務知識が貯まっていく。
- 柔軟な変更対応: ビジネスの変化に合わせて、迅速にシステムを改修できる。
これらのメリットは、確かにその通りです。しかし、これらは全て「実現するための十分な組織能力がある」という前提条件の上になりたつものです。多くの場合、この前提が崩れていることに気づかないまま、プロジェクトがスタートしてしまうのです。
内製化に潜むリアルな罠(現実)
- 隠れた高コスト: 優秀なIT人材の採用・育成コストは高騰しており、結果的に外部委託より高くつくケースがある。
- 属人化のリスク: 特定のエンジニアしか分からない「ブラックボックス」なシステムが生まれ、その人が退職した途端に誰も触れなくなる。
- 品質の低下: プロジェクト管理や品質管理のノウハウが不足し、バグだらけの使えないシステムが出来上がってしまう。
- 進まない開発: 既存のIT部門が日々の運用に追われ、新しい開発チームをサポートできず、プロジェクトが孤立・停滞する。
「内製化」という名の航海は、羅針盤も海図も持たずに、荒れ狂う海へ漕ぎ出すようなもの。まずは自分たちがどんな船に乗っていて、どんな航海士がいるのかを正確に把握することから始めなければなりません。
【事例】「自分たちでできるはず」その思い込みが招いた危機
ここでご紹介するE社は、ECサイトを主力事業とする、急成長中のアパレル企業です。E社のE社長は、トレンドの移り変わりが激しいアパレル業界で勝ち残るため、データ分析の重要性を痛感していました。
「顧客の購買データを分析して、次のヒット商品を予測する。そんなツールを、外部に頼らず自分たちで、スピーディーに作りたい」。
E社長のこの強い思いから、データ分析ツールの内製化プロジェクトが立ち上がりました。早速、優秀なエンジニアを2名採用し、情報システム部の若手エースであるEさんをプロジェクトマネージャーに任命。誰もが、プロジェクトの成功を信じていました。
しかし、現実は甘くありませんでした。
プロジェクト開始から半年。進捗は、ほぼゼロ。初期予算のほとんどを使い果たしたにもかかわらず、動くものは何も出来上がっていません。
- 定まらない要件: マーケティング部から「こんな分析もしたい」「やっぱりあの機能も必要だ」と、次から次へと要望が追加され、仕様が全く固まらない。
- 孤立するエンジニア: 採用されたエンジニアはコーディングスキルは高いものの、E社の複雑な業務や既存システムを理解するのに苦戦。気軽に相談できる相手もいない。
- 疲弊する管理者: プロジェクトマネージャーのEさんは、各部署との調整、エンジニアのフォロー、そしてE社長への進捗報告に奔走。しかし、自身も開発経験が豊富なわけではなく、技術的な判断ができないため、ただただ時間が過ぎていくことに無力感を覚えていました。
社内の雰囲気は最悪でした。「だから素人が手を出すべきじゃなかったんだ」と冷ややかな目で見る社員もいれば、「あのエンジニアは本当に仕事をしているのか?」と疑う声も上がり始めました。E社長の鳴り物入りで始まったプロジェクトは、完全に座礁寸前だったのです。
私たちは何をしたか?第三者による「IT組織の健康診断」
「もう、自社だけでは何が問題なのかすら分からない」。追い詰められたE社長から相談を受け、私たちはまず、「IT組織アセスメント」、つまり客観的な組織診断を行うことを提案しました。手術が必要かどうかを判断する前に、まずは精密検査(健康診断)をしましょう、ということです。
ステップ1:評価の「ものさし」作り 私たちは、一般的な評価項目を当てはめることはしませんでした。まずE社長や役員の方々とディスカッションを重ね、「今回のデータ分析ツール開発を成功させるために、そして今後のE社の事業成長のために、IT組織として本来あるべき姿(To-Be)とは何か」を定義しました。具体的には、「戦略」「人材・組織」「技術」「プロセス」の4つの観点から、理想の状態を言語化していきました。これが、現状を評価するための客観的な「ものさし」になります。
ステップ2:客観的な現状把握 次に、定義した「ものさし」を基に、E社のIT組織の「現在の姿(As-Is)」を徹底的に調査しました。E社長やEさんはもちろん、採用されたエンジニア、既存の情報システム部員、そしてツールの利用者となるマーケティング部のメンバーまで、10名以上に個別のヒアリングを実施。さらに、プロジェクト計画書や議事録、設計資料なども全てレビューしました。
ステップ3:ギャップ分析と「見える化」 そして、集めた情報を分析し、「あるべき姿」と「現在の姿」のギャップを可視化しました。その結果が、このレーダーチャートです。
| 評価項目 | あるべき姿 (目標値) | 現在の姿 (評価値) | ギャップ |
| IT戦略立案力 | 5 | 2 | -3 |
| プロジェクト管理能力 | 4 | 1 | -3 |
| システム設計能力 | 5 | 2 | -3 |
| プログラミング能力 | 4 | 4 | 0 |
| インフラ運用能力 | 3 | 3 | 0 |
| セキュリティ管理 | 4 | 2 | -2 |
このチャートを見て、E社長とEさんは言葉を失いました。そして、同時に腑に落ちたのです。 彼らが採用したエンジニアの「プログラミング能力」は目標値に達していました。しかし、プロジェクトを成功に導くために不可欠な「プロジェクト管理能力」や「システム設計能力」が、致命的に不足していたのです。
例えるなら、「腕のいい大工さん(プログラマー)はいるけれど、家の設計図を描ける建築士(システム設計者)も、工事全体を監督する現場監督(プロジェクトマネージャー)もいないまま、家づくりを始めてしまった」ような状態だったのです。これでは、立派な家が建つはずもありません。
「内製化しない」という戦略的な決断
この客観的なアセスメント結果は、E社長にとって厳しいものでしたが、同時に進むべき道を照らす光にもなりました。彼は、感情論や思い込みではなく、データに基づいた冷静な判断を下すことができたのです。
その決断とは、「すべてを内製化することに固執するのをやめる」という、戦略的な方向転換でした。
アセスメント結果を基に、私たちはE社に新しいハイブリッド型のアプローチを提案しました。
| 当初の計画(完全内製化) | 新しい計画(ハイブリッド型) | |
| 役割分担 | すべて自社で開発 | 【外部パートナー】 全体の設計、PM支援、技術アドバイス <br> 【E社】 業務要件定義、一部機能の開発、将来の運用 |
| 技術選定 | 手探りで選定 | 外部知見を活かし、最適なクラウドサービス(PaaS)を基盤に採用 |
| 開発体制 | 孤立した開発チーム | 外部パートナーとE社エンジニアによるワンチーム体制 |
| ゴール | 不明確なまま停滞 | 6ヶ月後に主要機能のリリース |
この新しい計画では、E社の強みである「業務知識」と、採用したエンジニアの「プログラミング能力」を最大限に活かしつつ、弱みである「設計」と「管理」の部分を、外部の専門家が補う形を取りました。餅は餅屋に、というわけです。
この方針転換により、停滞していたプロジェクトは息を吹き返し、わずか半年後には、マーケティング部が「これが見たかったんだ!」と唸るほどのデータ分析ツールをリリースすることに成功したのです。
あなたの会社はどこを目指すべきか?IT組織の3つのタイプ
E社の事例から学べる最も重要な教訓は、「内製化は、あくまで手段の一つであり、目的ではない」ということです。そして、企業が目指すべきIT組織の姿は、一種類ではありません。私たちは、中小企業のIT組織は、大きく3つのタイプに分類できると考えています。
- タイプ1:最適化型(ITコーディネーター組織)
- 自社で開発は行わず、世の中にある優れたSaaSや外部ベンダーを最適に組み合わせ、管理することに長けた組織。多くの非IT企業にとって、最も現実的で効果的な姿。
- タイプ2:ハイブリッド型(協業推進組織)
- 今回のE社がたどり着いた姿。基盤部分は外部の力を借りつつ、自社の競争力の源泉となる部分は、小規模な内製チームで開発する組織。
- タイプ3:内製化主導型(プロフィットセンター組織)
- ITそのものが事業の核となっている企業。システム開発の全ての工程を自社で完結できる、高度な専門家集団。
大切なのは、自社の事業戦略や企業文化、そして現在の実力に合ったタイプを見極め、そこに向かって段階的に成長していくことです。その第一歩が、客観的な自己分析、すなわち「IT組織アセスメント」なのです。
自社の「現在地」を、客観的に知りたくありませんか?
「うちのIT部門は、本当はどのくらいの実力があるんだろう?」 「内製化を進める前に、客観的な意見がほしい」
この記事を読んで、少しでもそう感じられたなら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。 自社の強みや弱みを、社内の人間だけで正確に把握するのは、非常に難しいことです。私たちは、数多くの企業を見てきた第三者の視点から、あなたの会社のIT組織の「現在地」を正確に可視化するお手伝いをします。
私たちが提供するのは、単なる評価レポートではありません。あなたの会社の事業戦略とIT戦略を結びつけ、明日から何をすべきかという具体的なアクションプランまで落とし込んだ「未来へのロードマップ」です。
まずは、あなたの会社が抱える課題や目指す姿について、お話をお聞かせいただくことから始めませんか?


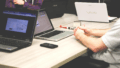
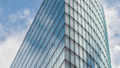
コメント