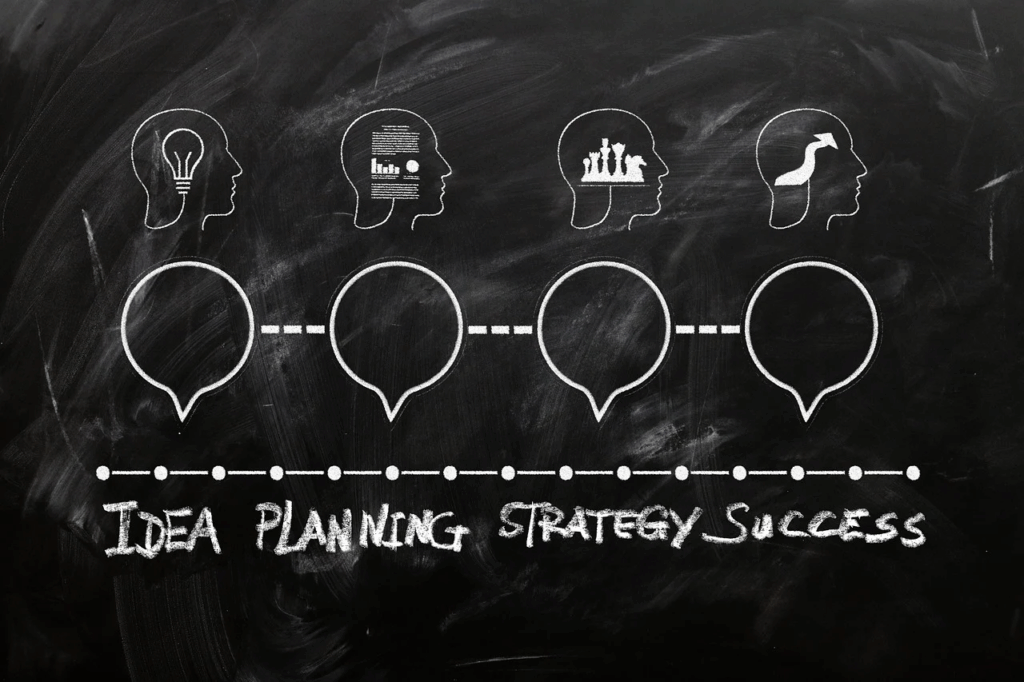
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 「準委任契約のはずなのに、客先から直接指示される…」と悩んでいるSESエンジニアの方
- 自分の現場の働き方が、もしかしたら違法ではないかと不安に感じている方
- これからSES業界で働こうと考えているが、絶対に失敗したくない方
- エンジニアを客先に常駐させているが、法律的に問題ないか確認したい企業の管理者の方
「ウチは準委任契約だから」。その言葉を信じて客先常駐したのに、気づけばクライアントの社員から毎日直接指示を受け、勤怠管理まで客先で行われている…。もし、あなたがこんな状況に少しでも心当たりがあるなら、それは「偽装請負」という、あなたのキャリアと心身を蝕む深刻な違法行為の真っ只中にいる可能性があります。これは「業界の慣習だから」では、決して済まされない問題です。私自身、この偽装請負の現場で責任の所在が曖昧なまま精神的に追い詰められ、エンジニアという仕事が嫌いになりかけた苦い経験があります。この記事では、その生々しい体験談を元に、偽装請負がなぜ生まれるのか、その具体的な見分け方、そして万が一あなたが当事者になってしまった場合に、自分自身の身を守るための具体的な対処法まで、徹底的に解説します。
結論:あなたの会社の「偽装請負」は、真っ黒な違法行為です
まず、最も重要なことからお伝えします。偽装請負とは、契約書の形式上は「請負契約」や「準委任契約」を結んでいながら、その働き方の実態が「労働者派遣」になってしまっている状態を指します。そして、これは職業安定法や労働者派遣法に違反する、明確な法律違反です。
「なぜそんなに厳しく取り締まられるの?」と思いますよね。理由は大きく二つあります。
一つは、労働者を守るためです。本来、派遣社員として働く場合、労働者は「労働者派遣法」によって、雇用を安定させるための措置や、派遣先の社員との不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」の原則など、様々な形で手厚く保護されることになっています。しかし、偽装請負の状態では、こうした法律の保護を一切受けられず、非常に不安定で弱い立場に置かれてしまうのです。
もう一つは、国の許可制度を骨抜きにしてしまうからです。労働者派遣事業を行うには、資産要件など厳しい基準をクリアし、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。偽装請負は、この国のルールを無視して、無許可で「もぐりの派遣業」を行うのと同じ行為であり、国の雇用秩序を乱すものとされています。
もし偽装請負が発覚した場合、仕事を依頼したクライアント(発注者)と、エンジニアを送り出したSES企業(受注者)の双方が、行政指導や改善命令、悪質な場合には企業名の公表、さらには罰金などの厳しいペナルティを受ける可能性があります。決して「知らなかった」では済まされない、重大なコンプライアンス違反なのです。
なぜなくならない?SES業界に「偽装請負」が蔓延する3つの構造的欠陥
違法行為であるにもかかわらず、なぜSES業界では偽装請負が後を絶たないのでしょうか。それは、「クライアント」「SES企業」「エンジニア」という三者の、それぞれの思惑や立場の弱さが、不幸な形で噛み合ってしまうという構造的な問題を抱えているからです。
- クライアント側:「法律は面倒。でも直接指示したい」という本音 クライアントからすれば、いちいちSES企業の担当者を通して指示を出すよりも、現場にいるエンジニアに直接「これお願い」と伝えた方が、圧倒的にスピーディーで効率的です。労働者派遣契約を結ぶのは、許可事業所を探したり、契約内容を精査したりと手間がかかる。「バレなければ大丈夫だろう」というコンプライアンス意識の低さが、偽装請負の引き金になります。
- SES企業側:「お客様は神様。契約を切られたくない」という忖度 多くのSES企業にとって、クライアントは売上を支えてくれる大切なお客様です。現場で多少、契約内容から逸脱した指示があったとしても、「クライアントの機嫌を損ねて、来月から契約を打ち切られては困る」という気持ちが働き、見て見ぬふりをしてしまうケースが後を絶ちません。利益を優先するあまり、自社のエンジニアを守るという本来の役目を放棄してしまうのです。
- エンジニア側:「おかしいけど、言えない…」という立場の弱さ そして、最も弱い立場に置かれるのが、現場で働く私たちエンジニアです。おかしいと感じていても、「ここで逆らったら、客先評価が下がって自分の給料査定に響くかもしれない」「自社の営業に相談しても、『うまくやってよ』と言われるだけだろう」といった諦めや不安から、声を上げることができずに黙って受け入れてしまうのです。
厚生労働省が発表する「労働者派遣事業の監督指導状況」などを見ても、毎年多くの事業所が指導を受けており、その中にはIT業界も含まれています。この「クライアント」「SES企業」「エンジニア」の三すくみの構造こそが、偽装請負という違法行為を根絶できない、業界の根深い病巣と言えるでしょう。
【実録】私が体験した「偽装請負」地獄の現場
ここでは、私が実際に経験した偽装請負の現場について、具体的にお話ししたいと思います。それは、準委任契約で、ある中堅企業の社内SEの代わりとして一人で常駐したプロジェクトでした。
入社初日から、その現場の異常さは明らかでした。
- 毎朝の朝礼での直接指示: クライアントの情シス部長が主催する朝礼に参加させられ、他のプロパー社員と同じように「今日は〇〇の対応と、△△の調査をお願いします。夕会で進捗を報告してください」と、直接タスクを割り振られました。私の雇用主はSES企業のはずなのに、業務指示は100%クライアントからでした。
- 客先のタイムカードでの勤怠管理: 出退勤は、客先のタイムカードで打刻していました。休暇を取りたい時も、自社の勤怠システムに登録した後、この部長に「お休みをいただきたいのですが」と直接許可をもらいに行く必要がありました。完全に客先の労務管理下に置かれていたのです。
- 拒否権のない出張命令: ある日、部長から「急で悪いんだけど、明日から2日間、大阪支社に行ってサーバーの設定をしてきてくれないか」と、出張を直接命じられました。準委任契約のエンジニアに、クライアントが直接出張を命じるなど、本来あり得ないことです。しかし、現場にいるのは私一人。断れる雰囲気ではありませんでした。
- トラブル発生時の責任のなすりつけ: 極めつけは、システムトラブルが発生した時です。原因は前任者が作ったプログラムのバグだったのですが、部長からは「あなたの管理不行き届きだ!」と、他の社員の前で厳しく叱責されました。自社の営業に電話で助けを求めても、「先方を怒らせないように、うまく謝っておいてください」と頼りない返事。結局、クライアントに言われるがまま、始末書まがいの報告書を書かされる羽目になりました。
この時、私が感じたのは「自分は一体、どこの会社の人間なんだろう?」という、アイデンティティが崩壊していくような感覚でした。相談できる相手もおらず、指揮命令系統も責任の所在もぐちゃぐちゃ。このままでは心が壊れてしまうと感じ、最終的には契約更新を辞退し、そのプロジェクトから離れる決断をしました。
これが境界線!あなたの現場の「偽装請負」危険度チェックリスト
私の経験は極端な例かもしれませんが、偽装請負は静かに、そして気づかないうちに進行します。あなたの現場は本当に大丈夫でしょうか?厚生労働省が示す基準を元にした、以下のチェックリストで危険度を確認してみてください。
当てはまる項目が多いほど、「黒」に近づきます。
| チェック項目 | 健全な準委任/請負 | 偽装請負の疑い |
| 1. 仕事の依頼・指示 | 自社の管理者(リーダー等)から受ける | クライアントの社員から直接、日常的に受ける |
| 2. 業務の進捗報告 | 自社の管理者に報告する | クライアントの社員に直接、管理されている |
| 3. 勤怠管理の方法 | 自社の勤怠システムやルールで管理する | クライアントのタイムカード等で管理されている |
| 4. 休暇や遅刻の申請 | 自社の管理者に申請し、許可を得る | クライアントの管理者に申請し、許可を得る |
| 5. 残業・休日出勤の指示 | 自社の管理者から依頼・指示される | クライアントの社員から直接、指示・命令される |
| 6. 作業の進め方 | 自分の裁量や自社のやり方で進められる | クライアントから手順などを細かく指示される |
| 7. 座席の配置 | プロジェクトルーム等、独立した場所で作業 | クライアントの社員の間に挟まれて指示を受けやすい |
診断結果
- 0個: 健全な現場である可能性が高いです。
- 1〜2個: グレーゾーンです。注意深く状況を見守りましょう。
- 3個以上: 偽装請負の可能性が非常に高いです。すぐに行動を起こすべきです。
もし「偽装請負」の当事者になったら?自分を守るための具体的なアクションプラン
チェックリストで「危険」と判断された場合、決して一人で抱え込み、諦めないでください。あなたには自分を守る権利と、そのための具体的な手段があります。以下の4つのステップで、冷静に行動しましょう。
STEP1: 徹底的に記録する(客観的な証拠を集める) まず最も重要なのが、偽装請負の証拠を集めることです。感情的に「違法だ!」と訴えても、証拠がなければ会社は動いてくれません。
- 業務日誌をつける: いつ、誰から、どんな指示を受けたか、5W1Hを意識して具体的に記録します。
- メールやチャットを保存: クライアントから直接指示が来ているメールやチャットの履歴は、すべてスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
- ICレコーダーで録音: 会議や打ち合わせでの直接指示の音声を録音することも、非常に強力な証拠になります。
STEP2: 自社の営業・上司に「冷静に」相談する 証拠がある程度集まったら、まずは自社の営業担当や上司に相談します。この時、感情的になるのは逆効果です。「実は、現在の働き方について懸念があります。労働局の基準に照らすと、偽装請負に該当する可能性がありまして…。集めた記録がこちらです。一度、クライアントと契約内容の再確認をしていただけないでしょうか?」と、あくまで客観的な事実と証拠に基づいて、冷静に相談するのがポイントです。
STEP3: 会社が動かなければ、外部の専門機関に相談する もし、自社に相談しても真摯に対応してくれなかったり、「それが普通だから」とはぐらかされたりした場合は、迷わず外部の専門機関に頼りましょう。
- 総合労働相談コーナー: 全国の労働局や労働基準監督署内に設置されており、無料で専門の相談員が対応してくれます。
- 法テラス: 国が設立した公的な法人で、収入などの条件はありますが、無料で法律相談ができます。 一人で悩まず、プロの力を借りることが大切です。
STEP4: 最終手段は「転職」という最強のカードを切る 忘れないでください。そもそも、自社のエンジニアを違法な状態で働かせ、それを改善しようとしない会社に、あなたの貴重なキャリアと時間を捧げる価値はありません。相談と並行して、水面下で転職活動を始めましょう。「いつでもこの環境から脱出できる」という選択肢を持つことが、何よりの精神的なお守りになります。
まとめ:偽装請負は「知らなかった」では済まされない、あなたの問題です
偽装請負は、一部の悪質な企業だけの問題ではありません。SESという働き方が存在する以上、誰もが当事者になる可能性を秘めた、業界全体の構造的な問題です。
そしてそれは、エンジニアのキャリアを停滞させ、仕事への誇りを奪い、心身を疲弊させる、決して許されない行為です。
この記事を読んで、「自分の現場も危ないかも」と感じたなら、それは見て見ぬふりをしていいサインではありません。おかしいと思った時に「おかしい」と声を上げる勇気、そして自分の身を守るための正しい知識を身につけて行動することが、あなた自身を救い、ひいては未来のエンジニアたちが健全に働ける業界を作っていくための、大きな一歩となるはずです。




コメント