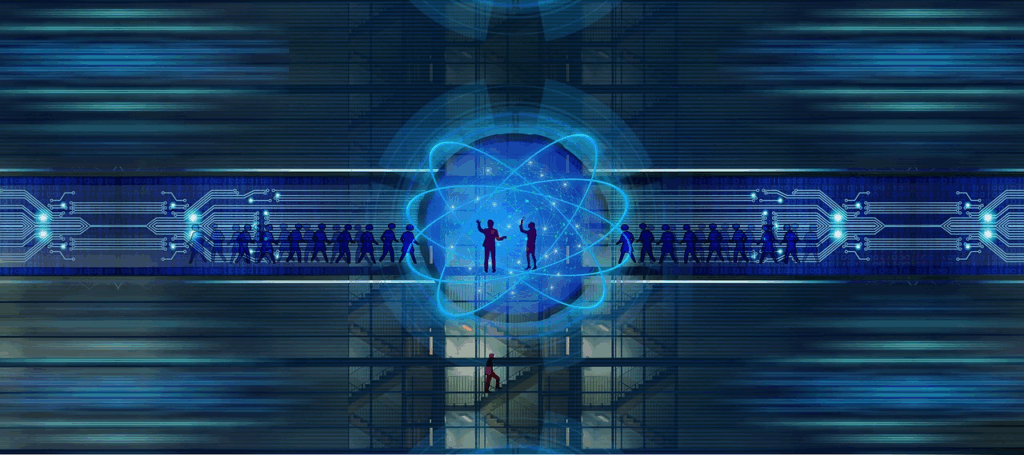
【この記事はこんな方に向けて書いています】
- 部下の若手が次々と辞めてしまい、本気で頭を抱えているマネージャーの方
- 「最近の若者は根性がない」と、つい嘆いてしまうベテラン社員の方
- 会社の離職率が高く、組織を根本から変えたいと考えている経営者・人事担当者の方
- 綺麗事ではない、現場で本当に効果があったマネジメントの極意を知りたい方
かつて、僕が率いていた部署は、地獄でした。 新卒や若手社員が、入社してたった1年足らずでバタバタと辞めていく。その離職率は、一時期60%を超えていました。
当時の僕は、本気でこう思っていたんです。 「今の若いヤツらは、根性が足りない」「少し厳しくすると、すぐに心が折れる」と。 でも、それは大きな、あまりにも大きな間違いでした。問題は、若者じゃない。100%、僕たちマネジメント側にあったんです。
その事実に気づいてから、僕が血を吐くような試行錯誤の末に作り上げ、マネージャー陣だけに共有してきた「裏マニュアル」があります。今日は、その禁断のルールを、特別に公開します。
「期待してるぞ」は呪いの言葉。まず“期待しない”ことから始めろ
裏マニュアルの第一条。そして、最も重要なルールです。 それは、「若手に、一切期待しないこと」。
「え?」と思いましたか?でも、これが真理なんです。 あなたが良かれと思ってかけている「期待してるぞ!」という言葉。それは、若者にとっては「結果を出せなければ、お前は無価値だ」と宣告する、呪いの言葉に他なりません。
上司の大きすぎる期待は、ただのプレッシャーとなり、彼らを押しつぶします。そして、「期待に応えられない自分はダメな人間だ」と、自己肯定感を木っ端微塵に破壊していく。厚生労働省の新規学卒者の離職状況を見ても、入社3年以内の離職率は常に3割前後で高止まりしています。その理由の上位には、常に「仕事内容のミスマッチ」が挙げられますが、これも元をたどれば、上司の期待と本人の能力のギャップから生まれるんです。
だから、まず「期待」するのをやめましょう。やるべきは「観察」です。この子は、何が得意で、何が苦手なのか。どんな時に喜び、どんな時に固まってしまうのか。先入観を捨てて、ただ事実として見極める。全てのスタートは、そこからです。
「いつでも相談しろ」は無意味。“相談される仕組み”を作れ
裏マニュアルの第二条。 「何かあったら、いつでも相談してこいよ」。この言葉、100%無意味なので、今すぐゴミ箱に捨ててください。
考えてみてください。新人にとって、上司なんていうのは雲の上の存在です。 「こんなことで相談したら、無能だと思われるんじゃないか…」 「忙しそうなのに、話しかけていいんだろうか…」 彼らの頭の中は、不安でいっぱいです。「いつでも」なんて言われても、その「いつ」が永遠に来ることはありません。
だから、「待ち」の姿勢をやめるんです。こちらから、強制的に「相談させる仕組み」を作る。 僕が実際に導入したのは、次の3つです。
1.週に1回15分、強制的に1on1の時間を確保する。
2.日報に「今日困ったこと・悩んだこと」の欄を必須項目にする。
3.チャットツールに、独り言を呟くための「分報」チャンネルを作る。
ポイントは、彼らが助けを求めるハードルを、極限まで下げること。相談しやすい雰囲気を作る、なんていう精神論ではなく、相談せざるを得ない「仕組み」で解決するんです。
“小さな成功体験”という麻薬を、合法的に投与せよ
裏マニュアルの第三条。 若手のモチベーションを維持し、成長させるための、最も効果的な方法です。 それは、「小さな成功体験」という麻薬を、意図的に、そして継続的に投与すること。
新人や若手が、最初から大きな成果を出せるわけがありません。そこで、マネージャーが彼らのために仕事を分解し、「これなら絶対にクリアできる」というレベルの、超具体的なミッションを与えるんです。
「A社の〇〇さんに、この件でアポイントの電話を1本入れてみて」 「この会議資料の、P5のグラフだけ作ってみてくれないか」
そして、それができたら、あり得ないくらい大げさに褒める。 「うわ、マジで助かった!ありがとう!」 「早いね!さすが〇〇さん!」
この一言が、彼らの承認欲求を満たし、「自分はこのチームの役に立っているんだ」という自己肯定感を育てます。この「小さく勝たせる」経験の積み重ねこそが、彼らを自走する人材へと変える、唯一にして最強のドーピングなんです。
若者が辞めるのは、彼らの「根性」や「やる気」の問題じゃありません。 それは全て、僕たち上司の「接し方」と「仕組み」の欠陥です。
若者を変えようとするのは、傲慢です。 変わるべきは、いつだって、僕たち旧世代の方なんですから。

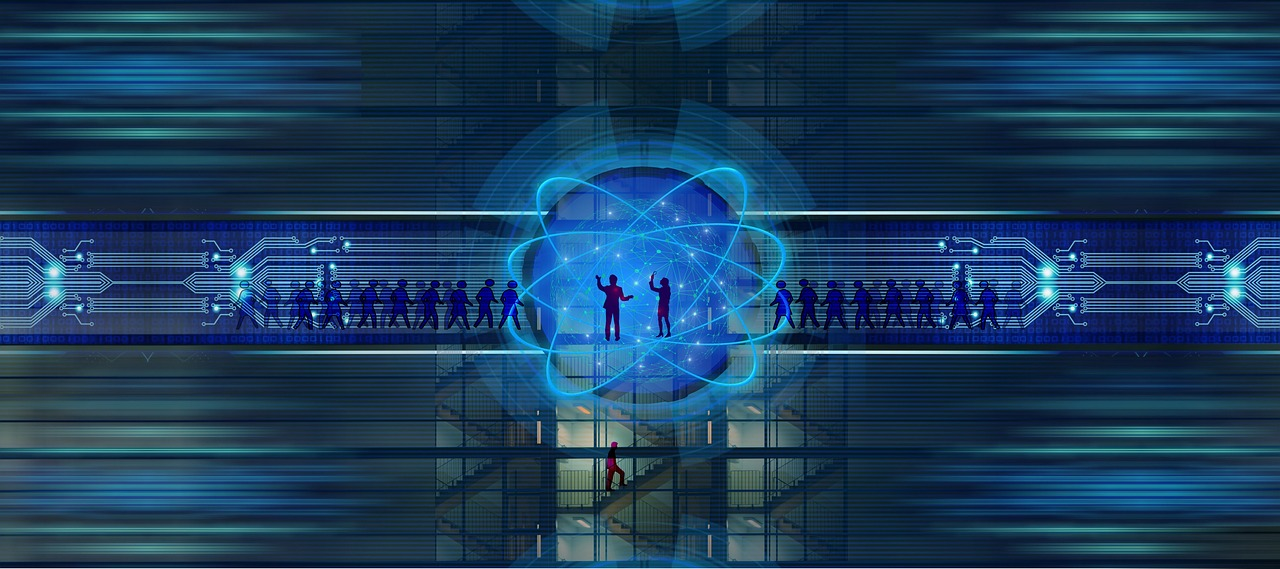

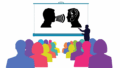
コメント